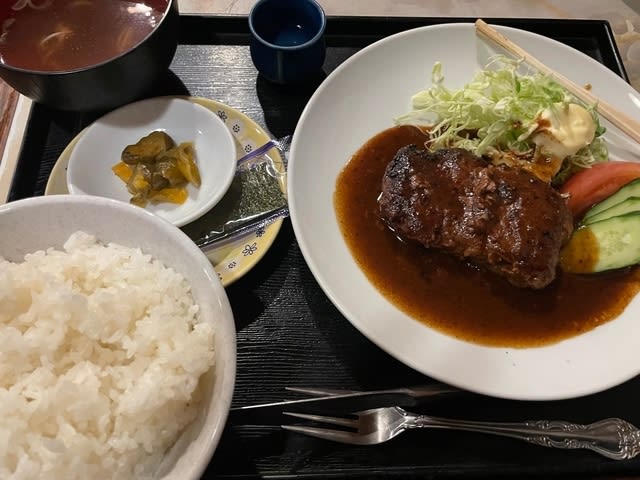実際に勉強会でお話も聞き、また、法政大学での公開発表にもうかがった吉永先生の本を読んだ。
この本の副題にはこう書いてある。
人文学から再開発を問う と。

神宮外苑の再開発をきっかけに、巻き起こった論争。
都市計画、環境学からの議論は百出しているが、いまだ人文学からアプローチはない。
ゆえに人文学からのアプローチを試みる。
そう提起されて編まれた本だ。
まず、 まえがき は ゴッホの絵を所有者が燃やしてよいか? から提起される。
それは個人の所有物を超えて みんなのもの である。ゆえに答えは [否]であろう。
翻って 都市にとって重要な場所や景観 は どうであろうか?
人々がそこに愛着や郷愁を感じ、また、誇りを感じる。なくなった場合の喪失感 を抱く。
そういう場所や景観も みんなのもの であり、価値があるのではないか、と。
それは みんなのもの たり得るのだろうか?
再開発は 土地の所有者の自由 なのか?
みんなのものだとしたら、みんなとはだれか?
それは 今それを利用している人々であり、それをつくり、育ててきた今までの人々であり、将来世代の人々であり、
また、人間以外のいきもの もみんなに含まれるのだ。
役所近くの樹冠の広がったケヤキ並木
そこから 特に 都市における緑 について論考は絞られていく。
その緑は伐採するが、替わりに他の場所に植樹するからいいじゃないか!(mitigation)
開発側が、よく言う主張である。
確かに みどりの「機能的価値(二酸化炭素吸収、気温上昇緩和、延焼防止・・・)」だけを考えればそうかもしれない。
しかし、「関係的価値」まで含めたらどうか?!
人間には「欠けがえのない存在」という感覚がある。
欠けがえのないもの それは代わりに作るからよい、では済まされないはずだ!
開発側は、その考えを近視眼的だと批判する。 それは容易なことである。しかし、その批判は一方で道徳を損なうものでもある。
そう吉永先生は指摘するのだ。
そして、理由をこう続けるのだ。
人は職場において お前がいなくても替わりはいる と言われたら その人の尊厳は傷つけられるだろう。
(仕事は近年、職人性から脱却し、いかに代替可能にシフトするかがテーマではあったのだが・・・)
人も場所も景観も、「その」人・場所・景観が焦点となった瞬間に、代替化は慎重でなければならなくなるのだ、と。
そういわれて自分もはたと立ち止まった。
というのも、
代替可能性(オマエノ替ワリハ イクラデモイル)は 現代社会がもつ人を幸せにしない病理の一つ、と最近ずっと自分は感じてきたからであった。
(それは自分が様々なバイトをしてきて現代の仕事につくづく感じてきた実感であった。)
歴史とか言い伝えとか物語とか(過去からの関係)郷愁とか愛着とか誇りとか(今の人々との関係)
緑の場合は、さらに未来の人々との関係や他の生き物たちとの関係(生態系)を考慮してよいのだ。
いや考慮すべきものなのだ。
この本はそう自分に語り、励ましてくれたのであった。
写真は 昨日の中央公園のみどりとケヤキ並木
以下備忘録
・都市計画は ここに〇〇を建てる だけでなく、ここには何も作らない ことを定めるものである。
・ドイツでは昨年7月より 気候変動への分析と適応計画、モニタリングが義務化された。
・ハンブルクでは降雨の6割を都市内に保水する。フランクフルトでは新築は屋上又は壁(地上3mの半分まで)は緑化が義務に。
・世の中は、スクラップアンドビルドからリユース型再開発に流れは来ている。
ある市のラガープラッツという工場跡地の例。
活用案が決まらず20年間テンポラリーユース(一時賃貸)に任せたら、安い家賃ゆえ若い人々が集まり、魅力ある場所になってしまった。
運動がおこり、そのまま存続となった。
★スポンジシティという考え方が隆盛してきた。(水循環を最適化する考え=緑の気化・緑陰、街路樹増やす、土に戻す、浸透、貯水して再利用)
★マルチスピーシーズ都市(多種が生き、生きられる都市)という発想。
・環境美学は、ある環境の連続性の感覚を大事にし、場所の物語を聞き取ろうとする学問。
・都市とはstrageness(驚き)と attachment(愛着)がある場所である。
・都市はしかし異常なほど日常の時間が速く進む。余暇もまた商業的に作られた労働(消費)になってしまった。
そんな中、自然はそこから隔離させ、ほっとさせてくれる存在だ。人はそこに本当の自由を体感するのではないか。
・時代は、今 バイオリージョナリズム(生態系)>(不等号) コロニアリズム(人間中心の考え方)である。
・順応的ガバナンスによる環境保全 ・でも自然は無くなったら取り戻せない!
・世界の人口の55%が都市に住んでいる。日本でも今生まれる3人に1人が首都圏生まれである。 だからこそ、都市の在り方が問われるべきなのだ。
結論)ではどうすればよいのか?!
1、市民参加との協働を促す 2,制度や計画に「自然の関係的価値」を明記する 3,緑地に対する多様な価値を共有する
4,人々の記憶や物語に緑をきちんと結び付けていく 5,評価する方法を確立する(人々の記憶を物語の形にする、GISを用いて「愛着」を可視化する)
6,多様な主体が協働できる接点を意識的に用意していく
そう書いてあった。(宇沢弘文の社会的共通資本には、そこに 専門家の職業的知見と倫理観 が加わってくる)
※)所沢市で言えば、1,3,6はもちろん意識してやってきた。
が、5はできなかったし、2は口酸っぱく言い、プロジェクトチームも作って職員一同で共有に努めたが、でも残念ながら明記まではいかなかった。
そして、次期政権によりその価値は軽んぜられ消去され、風前の灯にされてしまったように見受けられるのである。
堀口天満天神社周辺の緑の保全の際、田んぼを公有地化したの6であるし、カルチャーパークを考える会の活動等は1であろう。
また、私は勝手に物語を作って、それを宣伝していた。
それは、期せずして川を介在して同時多発的に起こった保全活動についての物語であった。
それは、「柳瀬川の最上流をきれいにする会」や「ふるさと創生の会」、「ミヤコタナゴ保存会(これは古い)」の活動であり、
上新井地区の「東川のホタルを呼びもどす会(名称不正確)」の活動であり、安松地区の「柳瀬川をきれいにする会」および、「アユ放流する活動」
や牛沼地区の「東川で生き物観察の活動」であったりするのだが、
発起したのはいずれも団塊の世代の人々であり、
思いは一つ「昔子供のころは〇〇がいた」→「これからの世代にそれを復活してやりたい」という願いであったのだ。
だから、その願いを消すことなく、この10年間が勝負、市もその心意気に呼応して「未来を見つめ 今を動い」ていきたい、というものであった。
ホタル おおむらさき タマムシ ミヤコタナゴ 鯉から鮎へ(恋から愛へ) - ガッツ藤本(藤本正人)のきょうのつぶやき
この本『都市の緑はだれのものか』の終わりの方には次のような指摘もあった。
都市計画や科学や環境学は「一般化・法則」を見出す行為、つまり、誰にでも当てはまる(替わりの効く)システムを求めるものであるが、
人文学は逆に 「替わりのない唯一の個」に焦点を当てていく行為であり、
つまり、人文学は 都市計画の面で言えば「この町」「この場所」「この木」の個別性を追究するのに適している、のかもしれない、と。