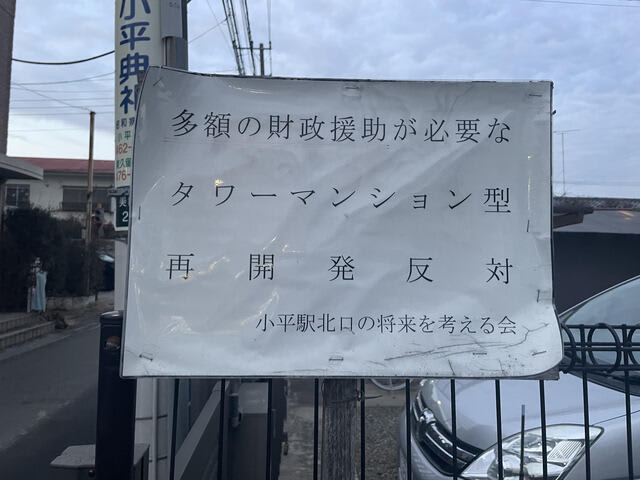多くの文明は、土を失うことで滅んでいった。
植物を養う力、つまり、豊かな表土を失って、だ。
今の農業のやり方(=慣行農業)も、その道を進んでいる。
化学肥料と化学農薬を利用し、機械と燃料を使って耕し、単一の作物をより大規模に行っていく農法だ。
化学農薬は土の微生物を殺し、肥料は流れて水(川)を汚染し、耕しては風に飛ばされ、結局、表土が奪われる。
化学の力は栄養剤とカンフル剤のようなもの。
土の力は衰え、枯渇していく。
化学製品(肥料、農薬)を注ぎ続けねば回らなくなり、機械の借金も重なって費用が掛かり、収量は減り、収益は上がらなくなる。
それでは農業の未来はない、環境保全型農法に変わらねばならない、と著者は言う。
実は、植物は、養分を直接ではなく、その一部は微生物の助けを借りて吸収している。
だから、土壌微生物が豊かな土こそ農業の基本、最も留意すべきことなのだ。
「土壌微生物」の豊富な土に戻すには、次のことが肝要と著者は言う。
1.耕さない農法(不耕起)作物残渣を残す・・・表土が流れない、微生物を養う
2.被覆作物(マルチ)の活用・・・・・・・・雑草を抑える、土に養分が返る、益虫が増える
3.多様な作物を輪作する・・・・・・害虫と病原菌を抑える
を同時にすべて行うことだ。
それにより、
(面積当たりの単一でなく総生産量)収穫量の増加、化学肥料・農薬使用の減少、労力の節減、費用の節減
ができ、結果として収益があがる、というのだ。
ただ、それは単純なことではなく、
より効果を上げるには、輪作と被覆作物の組み合わせを多様化することが必要らしい。
雑草と害虫と病原体を(真っ向からではなく)搦め手から防いでいく工夫だ。
それは、単純に昔の農法に戻る、のではなく、
新たな知見に基づく新たな手法を取り入れた昔の農法 とでもいうべきか。
しかし、環境保全型のこの農法は、まだまだ広がりを見せてはいない。
採用するのは新規就農者が多く、まじめな篤農家ほどこの農法に抵抗をしめす。
「新たな三学期制」と同じだな と自分は思った。
ただ昔のやり方に戻ることには、人は抵抗感を持つ。
単純に戻るのではなく、新たな知見も取り入れられた、そして、儲かる農法なんだと
皆が得心できるよう実績が積まれていけば、と願わずにはいられない。
(そのための方法も著者は提案している。)
また、著者は、持続可能性は言わずもがな、コストを減らすことに重点を置いて「収益」を論じている。
収益を上げるというと、すぐ大規模化とつなげてしまう私たちであったが、
売り上げが増えてもコストも増えていたら、収益は少ないのだ。
市が活き活きした街づくりで指導を仰いでいる東京芸大の藤村先生の言葉を 私は思い出した。
商業も大規模化、多店舗化で売り上げを高めようとするが、小さなお店の方が効率的なこともあるんです。
地域のことも考えると、2階に住んで1階は店舗、そういう小店舗の展開の方が街にとっていいし、
お店も収益はあがるんですよ、と。
そのほか備忘録)長い、羅列にすぎません。
・農業における4つの革命
1,犂と畜力の導入・・・村が合併し都市国家が大きくなることができた
2,土壌管理(輪作、間作、堆肥の投入)・・・借地制度が変化し、農地の集約化
3,機械化と工業化・・・農場に資本が必要に、大規模農場の拡大と都市への人の流入
4,緑の革命とバイオテクノロジーの活用・・・知的財産権付きの種など食料システムの企業支配
そして、今、第5の革命へ(環境保全型、土壌の健康を農法の中心に据えた農法)
・多様な輪作で、収量は高く、窒素肥料は1/5~1/7,除草剤は1/6~1/10に。(アイオワ大の圃場試験)
・放牧で地力を上げ、畜産効果も上げるなら、過放牧で短期間で移動させる・・・草をえり好みしない、寄生虫が伝染しない
・土壌微生物は見えない家畜である。微生物が有機物などを食べ、植物が吸収できる形に変える。
・菌根菌は重要な働き。植物のえさをつくり、植物から餌をもらう。共生関係。これは腸内細菌と人間の関係と同じ。
・温室効果ガスの15%は農業から。土壌有機物(作物残渣、被覆作物、堆肥など)を増やせば、微生物が養われ、収量も増える。そして、炭素も土中に固定化される。
・耕すことは土壌有機物の分解を速め、炭素を放出させる。土壌には空気の2倍の炭素が保持されている。
・環境保全型農法で、年0,4%土中炭素を増やせ、世界でやれば炭素放出の1/3を相殺できる。
フランスの農業大臣フォルはそれをパリ協定に提案した。
・リンの供給は有限だ。中国が半分を供給、モロッコに3/4の埋蔵がある。同時に農場や下水処理場から流れる リンで海の生態系はダメージを受けている。人糞や家畜の糞を活用する。
アメリカのすべての家畜糞を活用すれば作物が奪ったリンの85%は回収できる。
・農業に関する利益のほとんどは、農家以外の人が受けている。農家は肥料、燃料、資材の値段を決められなしい、作物の値段も決められない。設けているのは、農家に物を売る人間なのだ。
・企業が自分の製品が必要なくなるような農法を推進するわけがない。
著者の提案:
・作物保険制度と補助金を土の健康を増やすように変える。移行期間は国が支える。土壌肥沃度改善した農家に報奨金を出す。
・土壌炭素を増やすことに、炭素排出権を与える。1%土壌炭素を失うと、1エーカー当たり平均66ドルの自然資本を失うことに相当する。
・公的なランドバンクをつくって、労務で支払うことで抵当権流れの農地などを若い人が買えるようにする。
・家畜をどの農家も飼って、作物残渣や刈り株を食べさせる。村に小さな肉加工工場を配置する。
・有機農法というより不耕起も含めた「土壌にやさしい」ブランドをつくり、広く消費者も活用できるようにする。
・技術と農業化学製品は役に立つ。が、これも道具に過ぎない。農家をその気にさせるには、実例を見せるしかない。その方が儲かることが分かればよい。実験農場を各地に設けること。実践者のネットワークを活用する。
・HUMUS(腐植)とHUMAN(人間)はラテン語の同じ語根を持つ。
同じくディビッド・モンゴメリーの本『土の文明史』
『土の文明史』を読む - ガッツ藤本(藤本正人)のきょうのつぶやき (goo.ne.jp)