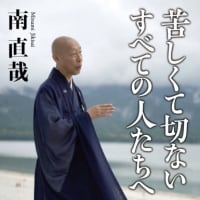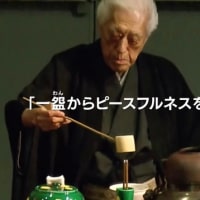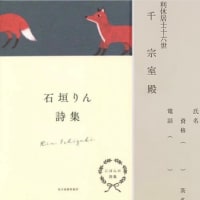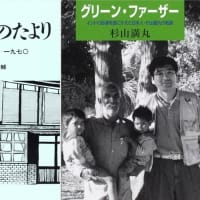コロナ禍になってからでしょうか、本棚に積読したまま気になっていた本を、優先的に読み進めるようにしています。これらの本を読んだ人生と、そうでない人生とが、はっきりと違うものの様に感じられるからです。
それから、解説書は何冊も読んでいながら、肝心の原典を読んでいなかったものなど、今さらのように読み始めています。今度の誕生日で公的に「高齢者」と呼ばれるようになると、この書物との関係を持てるのは、これが本当に最後の機会だ、という思いが強くなるのです。おそらくもう、やり直しはないのだと。
そんなことを考えていると、詩人の吉野弘さんが『花と木のうた』(青土社)という本のなかで、茶園の花について書いているのを思い出しました。
美味しい茶葉が育つよう豊富な肥料が施される茶園の木には、花がほとんど咲かないといいます。恵まれた環境に自足してしまって、花を咲かせるなどという面倒くさいことは忘れてしまうのです。また、花を咲かせるには大量の栄養を消費するので、葉に回るべき栄養を確保するためにも、茶園経営にとってはむしろ好都合なことなのだそうです。
そのうえ、花が咲いて獲れた種から育てるような栽培法では、せっかく交配で作った新種の品質を一定に保つことができません。そこで茶園は「取り木」と言って、挿し木とほぼ同じ原理の繁殖法で、クローンを増やすのだそうです。
管理社会に生きざるをえない我々の、生きることの貧しさを暗示するような話ですが、驚くのはその後の話の展開です。「取り木」という繁殖法を教えてくれた茶園の「若旦那」が、後日、老木の花について語ってくれて、吉野さんは次に引用するように、その話に深い感銘を受けます。
その後、かなりの日を置いて、同じ若旦那から聞いた話に、こういうのがありました。
ー 長い間、肥料を吸収しつづけた茶の木が老化して、もはや吸収力をも失ってしまったとき、一斉に花を咲き揃えます。
花とは何かを、これ以上鮮烈に語ることができるでしょうか。
(『花と木のうた』所収「茶の花おぼえがき」より)
管理されない生と、命懸けで向き合いたい。もう遅いのかもしれないけれど、生きてきた証を残さないわけにはいかない。そんな思いと、老木の咲かせる花とが共鳴するのでしょう。
気になっているものを放っておいたことは、弛緩し切った「取り木」として生きたことに当たります。むろん、それでよしとしてきたのは、自分自身なのですが。
だとするならば、吸収力を失ってしまった老木が一斉に花を咲かせたように、行動のひとつひとつを、花を咲かせるようなものにしたい。今になって痛切にそう思います。