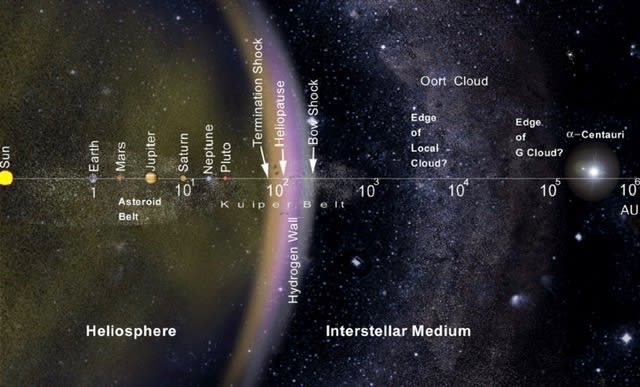緊急事態宣言のあいだ休みだったお茶の稽古も10月から再開されます。
今年の風炉の稽古は短いものでしたが、7月の研究会で業躰先生(裏千家家元の内弟子の先生)に厳しく指導していただいたことは、よい勉強になりました。あれから2か月以上が経過して、すっかり点前の感覚も緩んでしまったかもしれず、もう一度気を引き締めて練習にかからねばと思います。
さて、日暮れどきに家のまわりを早歩きするようにしていて、日毎に表情を変える星々を眺めるのが日課になっています。この時期の夜空の星の、なんとも言えない優しさを表した言葉がないものか探していたのですが、星にまつわる茶席の掛軸は、七夕の時期のものがほとんどで、今の時期の夜空については月に関するものが大半を占めています。
そんななか、秋の星空そのものを語ったものではないものの、次の言葉を見つけました。
主客在大円之中(主客、大円の中に在り)
「大円」は本来もっと抽象的なものを指すのでしょうが、私には秋の夜空の天蓋を連想させます。あの星々のなかのひとつが、こちらに向けて優しい光を放っていて、こちらもそれに応えるような、ちょうど主客が思いを相照らし合う印象です。
正岡子規の次の歌が、その感覚に近いように思います。
真砂なす数なき星のその中に吾に向ひて光る星あり
この歌は、寝たまま外の様子がわかるよう、高浜虚子が障子戸に設てくれたガラス越しに、夜空を仰いで詠んだもののようです。病床を見舞ってくれる友人や、看護で支えてくれる母の優しさも、子規にとって「吾に向ひて光る星」だったのでしょう。
連作「星」には、先の歌に続いて、次の歌が掲げられています。
たらちねの母がなりたる母星の子を思う光吾を照せり
この歌ではもっとはっきりと、慈愛に満ちた星の光が詠われています。
穏やかな他者受容が、やがて自己をも受容させる、そういう場こそが茶席の醍醐味です。「大円」とは、敢えて言えばこの穏やかな自他受容の場を指すのだと思います。
●こちらもよろしくお願いします→『ほかならぬあのひと』出版しました。