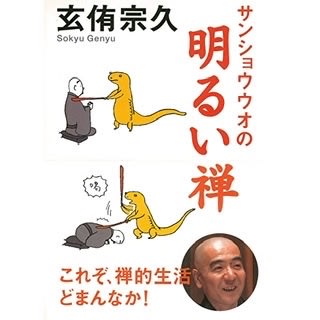
玄侑宗久がかつて、明るく生きることを「明度の高い生活」と呼んで、次のように語っていました。
誰でも子供の頃は、今鳴いたカラスがもう笑った、などとからかわれたことがあるだろう。そう、人は泣いていた時間を捨て、新たに展開した笑いの時間を生きるのである。禅ではそれを「放下」という。
放下し続けるのが生きることだし、死とは一切の放下ということだろう。
一瞬ごとに、「今」という一瞬が死んでいく。完全に死ねば、次の一瞬に前の一瞬が重ならない。重ね塗りにならないから、いつでもその色合いは鮮やかになる。楽しくとも哀しくとも、鮮やかなのである。(『サンショウウオの明るい禅』文春文庫 202頁)
子供たちの無邪気な姿に戻ることができれば、どんなに素晴らしいことでしょう。今日で終わる2021年を「放下」して、新しい年を明るく迎えればと思います。
と同時にこうも思います。
今年も色々な人の温かい気持ちに触れて支えられたり、どうしようもない哀しみに耐えたりしたのだけれども、それらを単に忘れ去ることではなく、その堆積のうえに間違いなく今日があるのだと。
そして、染色家の志村ふくみが語っていたことを思い出しました。
植物にもっとも多く見られる緑という色を植物から引き出して、糸に染め出すことはできません。それではどうするかというと、刈安などから作った黄色の糸を藍に掛け合わせることで、初めて緑という生命の色を引き出すことができるのです。太陽の光をいっぱいに浴びて育った植物から採られる黄色の糸に、甕で発酵させてできる藍を掛け合わせることによって、緑という生命の色が生まれます。決して黄と藍を「混ぜ合わせる」のではなく。
一瞬一瞬を「放下」することで、その一瞬の明度は増すのでしょう。同時にその一瞬を掛け合わせる、交わらせることで、全く新しい命の色を醸し出すことができるのだと思います。
私という器のなかで、明度を失わない今が掛け合わさって命の色が紡ぎ出されるとすると、それもまた明るい姿ではないでしょうか。
※※※※※※※※※※※
今年は自費出版という冒険をしました。ブログのなかで拙著をご紹介いただいた方もおられて、どんなに励まされたか知れません。来年が皆様にとって良い年でありますようお祈りします。



















