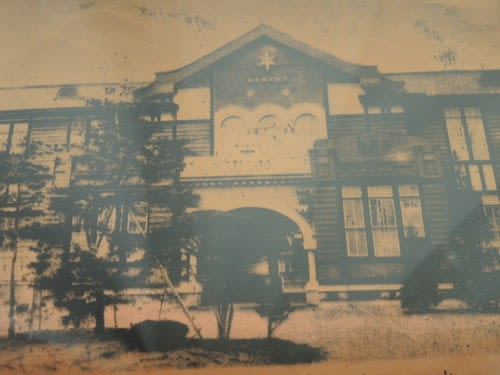仏教には、人は色々な世界に繰り返し生まれかわって生きてゆくという輪廻思想があり、その世界が6つあるので、六道輪廻というのだそうです。六道は、地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道だそうで、その一つ一つを地蔵の分身である6種の地蔵が守護しているのだそうです。こうした六地蔵の信仰は、日本独自のものだそうです。水戸にも色々な六地蔵があります。

仏性寺(栗崎町1984)
山門を入って本堂に向かう参道の途中にあります。天明9年の建立のようで、水戸市指定文化財になっています。天明の飢饉の餓死者供養のために村の寄付で建てられたそうです。ただ、向かって左から2体目の地蔵は、後年に制作されたもののようです。

六地蔵寺(六反田町767)
地蔵堂内に、寺名の由来である六地蔵が安置されています。地蔵堂は、法宝蔵とともに、徳川光圀が建てたそうです。

大井神社(飯富町3475)
大井神社の墓地付近にある六角灯籠形の、六地蔵石幢(せきどう)です。同じようなものが、県立歴史館庭や、常照寺墓地にもあります。

天徳寺(河和田町914-1)
天徳寺の六地蔵は、仁王門内の仁王像が安置された部屋の裏側に、左右各3体ずつ、本堂を向いて納められています。

光台寺(上水戸3-1-39)
墓の入口付近にあり、東日本大震災で倒壊した六地蔵を、震災犠牲者供養もこめて再建したそうです。