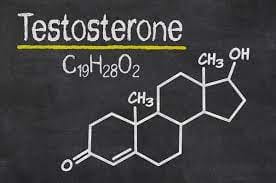なぜ女子中高生の「自殺」が増えた? マスコミ報道の影響「ウェルテル効果」も背景に
今も増え続けてますかね
10・20・2020
30歳以下の若い女性の自殺が増えている。ことしはコロナ禍で一斉休校や自粛生活が強いられたほか、5月に女子プロレスラーの木村花さん、7月に俳優の三浦春馬さん、9月に女優の竹内結子さん、そして今月には、女性ロックバンド「赤い公園」の津野米咲さんの自殺が相次いで報じられた。専門家は「若年層の自殺対策の無策が招いた」と指摘する。はたして若い女性たちに何が起きているのだろうか。(ライター・渋井哲也)
若年層に効果的な自殺対策ができていない
まず、一般論として、日本の自殺者数は、女性よりも男性のほうが多く、10万人あたりの自殺死亡率も高い。 ピーク時の2003年は、年間計3万2845人(うち女性9464人)が自殺していたが、2012年以降、年間自殺者数が減少傾向にあり、2019年には2万169人(うち女性は6091人)まで減っていた。
背景には、2006年に自殺対策基本法が成立して、「自殺は個人の問題ではなく、社会的要因」として位置付けられたことがある。同年、貸金業規制法が改正されて、借金の総量規制と同時に利息の上限が決められたこともあり、中年男性の自殺者数が大幅に減少していった。 しかし、10代の自殺者数は減少の幅がせまく、自殺死亡率は上昇傾向にある。若年層に効果的な自殺対策ができていないためだ。

とくに女子中高生の増加率が顕著となっている
グラフ1(厚生労働省の「地域における自殺の基礎資料」をもとに筆者が作成)

特に、ことしは、新型コロナウイルス感染拡大防止によって、全校一斉休校の処置がとられたり、非常事態宣言の外出自粛もあった。休校や宣言が解かれても、子どもたちにとって、重要である年度末から年度初めに学校に行けなかったことは、人間関係の形成に大きく響いたとする見方がある。
警察庁によると、2020年8月の1カ月間の自殺者数は、速報値で全国で計1854人。昨年2019年8月と比べて251人、16%増加した。うち女性は650人で、昨年より約40%も増えている。男性も6%増の1199人。自殺者数自体は男性のほうが多いが、女性の自殺が大幅に増加している。
とくに30代以下の女性の自殺は昨年より74%も増加し、193人が亡くなっている。 2020年9月も計1805人で、2019年9月と比べると、143人、8.6%増加した。ここでも女性は27.5%の増加となっている(男性は0.4%の増加)。
顕著なのは女子中高生だ。厚生労働省の「地域における自殺の基礎資料」に基づく筆者作成のグラフ1で、2018年1月から見てみると、女子中学生の月別自殺者数は、今年8月が最も多い(16人)。過去10年間の8月で見てみると、過去最多の自殺者数になっている。 女子高校生も同様の傾向だ(グラフ2)。
過去10年で、8月で自殺者が20人を超えるのも初めてだった。女子大生の自殺者数もやはり同様で、8月の自殺者が10人を超えたのは、東日本大震災があった2011年と翌2012年以来となっている。 夏休み明けのタイミングで子どもたちの自殺が増えると言われている(9月1日問題)。
ことしは夏休みが変則的で、8月中に夏休みが開けた地域が多い。夏休みが前倒しになったことで、9月1日問題も前倒しになったのではないかという見方もある。 自殺問題にくわしい中央大学客員研究員の高橋聡美さん(精神看護学)は次のように話す。
「若年層に限らず、全体で増えているので、社会全体の問題が大きいと思いますが、コロナ対策で、休校措置となり、子どもたちが犠牲になったことは、たしかです。しかも卒業、入学といった一生に一回の区切りをしっかりとつけないまま、新年度に突入して、友だちに会えず、とりわけ進学した子たちは新しい友だちができないまま夏を迎えました。
心理的に孤独感を増強させたことは間違いないでしょう」(高橋さん) 警察庁の統計でも、ことし8月は、20歳未満の自殺についての「原因動機」で最も多かったのは「学校問題」だ。しかし、なぜ、女子中高生に顕著に自殺者が増えたのかの説明ができない。
ウェルテル効果を受けやすい若年層に影響が出た」
グラフ2(厚生労働省の「地域における自殺の基礎資料」をもとに筆者が作成)
ことし5月に女子プロレスラーの木村花さん、7月に俳優の三浦春馬さんが自殺した。有名人の自殺や、それに関連した自殺報道の影響はどうだろうか。 一般に、有名人の自殺報道は、若年層に影響を与えうると言われている。1986年、アイドルの岡田有希子さんが自殺したときには、週刊誌で自殺現場の写真が掲載されて、テレビでも現場から中継された。こうした過度な報道の影響からか、あと追い自殺があったとも言われている。
「相次ぐ芸能人の自殺があり、WHOの『自殺報道ガイドライン』が守られていない報道に国民がさらされて、ウェルテル効果(マスメディアの自殺報道に影響されて自殺が増える現象)を受けやすいとされる若年層にその影響が強く出たと考えられます」(高橋さん)
東日本大震災のあった2011年5月、前年同月比で自殺者が19.7%も増えたことがあった。同年5月13日からの1週間は2011年の日別平均自殺者数を大きく上回っていた。実は、同年5月12日にタレントの上原美優さん(享年24)が自殺していたのだ。 このあと若年層の女性の自殺者数が増えたことから、自殺報道があったためとの分析がある。
警察庁によると、女子中学生の自殺は3人から4人、女子高生は7人から11人、女子大生が12人から18人に増えた。 一方、7月になると、それぞれ女子中学生は1人、女子高生は5人、女子大生は10人に減少している。一時的な要因だったのだろうか。5月は、震災の影響もあり、毎年3月に迎えるピークがずれて、全体的に増加傾向だった。
「コロナ不安・コロナ不況のしわ寄せが若年層や女性にきた」
現場レベルでは、さまざまな声が上がっている。たとえば、望まない妊娠の相談が増えたことだ。 厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、10代や20代の中絶件数は、2003年前後から減少傾向にあるものの、若年層ほど、より体に負担がかかる「第8~11週」で中絶手術をする割合が多い。そのため、メンタルヘルスへの影響も計り知れないのだ。
今年のデータについては、発表は来年になるため、その詳細は現段階ではわからない。望まない妊娠からの中絶が増えたのであれば、若年女性たちの中で、健康リスクや自殺リスクが高くなっているとも言えなくもない。
また、女性が被害にあうことが想定される事件が増加している。ことし8月までの統計で、ストーカー規制法違反が15.4%、DV法違反事件は11.1%増えている。ただし、昨年との比較で、若年女性の自殺が多い地域と性犯罪(強制性交等罪、強制わいせつ罪)の認知件数の増減とは必ずしも一致しない。 たとえば、若年女性の自殺が増えた大阪府では、強制わいせつ罪は減少している。
自粛ムードによって、屋外での犯罪が減ったとも考えられる。ストーカー規制法違反もDV法違反事件も地域別の統計が未発表であるが、屋内での犯罪が増えたということは、身近な相手からの被害にあったり、目撃するケースが増えた可能性が高い。
「女子の自殺が増えたことの要因としては、“妊娠相談や虐待相談が増えている“という、相談窓口の現場の声もありますので、自粛生活の中で、性的な被害が少なからずあったということは、考えなければならないと思います」(高橋さん) ことし9月の自殺者数の詳細なデータは公表されておらず、関連するデータについて、各専門家の分析が出そろっていない。
そのため、7月以降の女性の自殺者数増加、特に8月の女子中高生の増加については、断定的な結論は出せない段階だ。しかし、この点は注視していく必要がある。
「コロナ禍以前に、子どもの自殺は減っておらず、先進国の中でも最悪な状況がずっと続いています。加えて、コロナ不安・コロナ不況のしわ寄せが若年層や女性にきたのだと思います。若年層の自殺対策の無策が招いた数字だと私たちは謙虚に受け止めなければなりません。 子どもの自殺対策では、SOSの出し方教育ばかり強調されますが、大人たちのSOSの受け止め方の力量のほうがむしろ問題です。命と心のつなぎとめることのできる姿勢を私たちは身に付けていかなければなりません」(高橋さん)
●生きづらさを感じている方々へ(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/r2_shukan_message.html