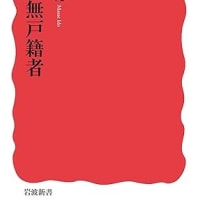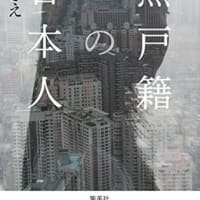先日「日本映画専門チャンネル」で放送された『大病人』を観ました。この映画は1993年5月29日に公開された伊丹十三の脚本・監督作品です。Wikipediaからあらすじを引用すると、
>
老境を迎える大物俳優兼映画監督の向井武平(三國連太郎)は、癌に冒された作曲家を自ら演じ、同じ病で妻に先立たれるというストーリーの映画を製作していた。
酒好きで胃薬を常用している向井は、ある日、自身の体の異変に気づき、離婚寸前の妻・万里子(宮本信子)のすすめで、万里子の学生時代の友人である外科医・緒方(津川雅彦)が勤務する病院を受診する。検査の結果、既に末期状態の胃癌であった。緒方から告知を受けた万里子は、緒方とともに本人には告知をしない道を選んだ。ところが、向井は病院内で知り合った患者仲間(三谷昇)から悲惨な癌患者(高橋長英)の実態を知らされ、自分に抗癌剤が点滴されていることに気づく。
向井は激しく緒方をなじり、緒方も向井の扱いに苦悩する。その後、混乱した向井は担当看護婦(木内みどり)を口説いたり、愛人である映画の共演女優(高瀬春奈)を病室へ連れ込んだり、挙句の果て衝動的に自殺を図ったりするが、緒方たちとの対話を通じて、自らの最期の迎え方を決断する。
ということになります。
つまりこの映画では、三国連太郎(すみません。新字で表記します)扮する主人公は、死の宣告を受けることになってしまったわけです。現在でこそ基本がんであることは患者に告知されますが、93年当時は必ずしもそうでなかったわけです。この映画はもちろんフィクションですが、当然伊丹自身の考えが表象されているはず。この映画自体は、配給収入7億円と、伊丹の前作『ミンボーの女』の配給収入15億5千万円と比較すると、半分未満というわけで興行的には不満足なものでしたが、このようなことをストレートに映画のテーマとした伊丹の感覚の鋭さはさすがだと思います。ただ伊丹自身は、このような悩みとは無縁な形で自ら命を絶ってしまったのですが(1997年12月20日のことですから、だいたい26年前の今頃です)。
そして、前にもとりあげたことがありますが、当時人気絶頂と言って過言でなかった、司会者である逸見政孝氏は、この年の9月6日に、自らががんであることを公表する記者会見を行い、9月16日に、13時間にも及ぶ大手術を受けましたが、10月23日に腸閉そくで体調が悪化、当日予定されていた一時帰宅は中止、その後ついに病院を出ることもなく、11月初旬に抗がん剤の投与を始めるも強い副作用でさらに衰弱、12月25日に亡くなりました。つまりちょうど記事発表の本日の30年前です。逸見氏は1945年2月生まれとのことで、ご存命なら記事発表時点で78歳ということになります。
逸見氏は映画好きだったそうですが、氏が『大病人』を鑑賞したかは私の知るところではありませんが(伊丹監督作品ですから、鑑賞している可能性は少なくありません)、ともかく彼は、自らの病状その他を社会に公表することを選んだわけです。
逸見氏の記者会見の評価についてはここでは論じないとして、ともかく逸見氏の記者会見によるがんを患っていることの公表は、ご当人はそこまでの影響があると予想していなかったのかもしれませんが、社会のパンドラの箱を開けてしまったということなのでしょう。現在いろいろな芸能人ほかが自分の病気を公表したり取材に応じている。逸見氏でなくてもほかの誰かが先駆者になったのでしょうが、ともかく逸見氏という好き嫌いはともかくとしてきわめて知名度の高い人物があのような記者会見で自分ががんを患っていることを公表したことにより、やはり社会の死生観や死にいたる可能性がある病気への態度について、日本人の考えその他が、それをどう評価するかはともかく相当に変化したということがいえるかと思います。
さてここで興味深い記事をご紹介します。逸見氏の手術を執刀した東京女子医大の羽生富士夫教授(故人)の弟子である林和彦東京女子医大がんセンター長(肩書は記事発表当時)の話です。2018年の記事です。林氏は、羽生教授の最後も看取りました。
>
羽生先生は1993年、テレビキャスターだった逸見政孝さんのスキルス性胃がんの手術も執刀しました。僕は留学の準備中だったので、逸見さんが末期であったにもかかわらず、羽生先生が手術をしてしまった理由はわかりません。僕ならば、おそらくやらない手術です。「なんとかなる」という思いがあったのかもしれません。
このくだりを初めて読んだ際、近藤誠氏のような部外者なら何言ったって別に構いませんけど(なお林氏は、近藤氏とも共著を出しています)、いくらご当人が死んだあととはいえ、直系の弟子がよくここまで言ったなという気は正直しました。実際問題として、逸見氏は手術後3か月で亡くなり、ついに一時退院どころか帰宅すらできず、しかも11月からの抗がん剤投与にいたっては、ほぼ寿命を縮めただけでしょう。で、抗がん剤はともかく、この時逸見氏が受けたような大手術は、現在ではもはやされなくなったらしい。これも、いずれそのような手術は淘汰されたのかもですが、逸見氏の手術後における予後不良ぶりが世間で知れ渡ったことが、このような事態になった大きな要因であることは否定できないでしょう。逸見氏の死が、日本の医療への大きな反面教師にならなかったか。そんなことは逸見氏の知ったことではもちろんありませんが、結果的にはそうなりました。
たぶんですが、『大病人』と逸見氏の記者会見とその死が同じ年になったのは、偶然ではあるとしても、このような映画が製作され、がんのような非常に予後が厳しい病気の公表をも(理由はともかくとしても)厭わないという態度が、歯車がかみ合うように進んでいくことを可能とする時期だったのでしょう。映画を作った伊丹はそのような時代の流れにそって製作したのでしょうが、逸見氏はそんなことを考える余裕もなかったのかもしれませんが、つまりはそのような時代の変化にのっとってあの記者会見が開かれたということなのでしょう。そういったことが、日本人の死への心がまえから具体的な治療方法などにも大きな影響を及ぼしたのだと思います。そういえば死を迎える場所というのも、病室でなく自宅でのそれをのぞむとか(『大病人』では、主人公は自宅で亡くなります)、時代によっていろいろ変化します。これからもこのような問題はいろいろ変わります。それこそ伊丹の映画ではありませんが、葬式のありかたがどんどん変わっていくことと同じなのでしょう。