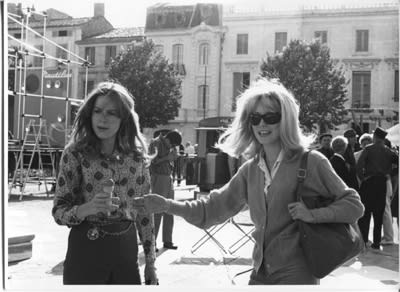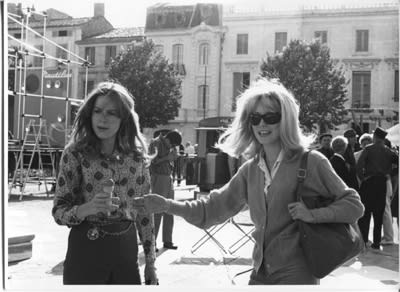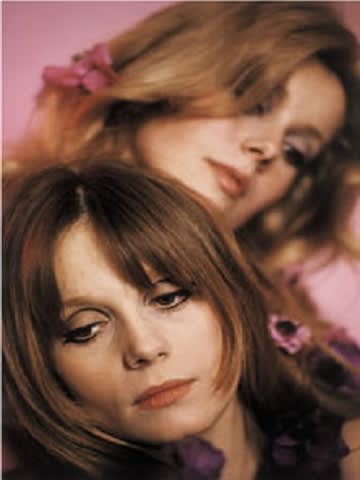ちょっと前の「毎日新聞」に興味深い(ていうか、だいたい想像のつく内容ですが)
記事がありました。全文引用しましょう。
>ザ・特集:悩む原子力専攻学生
原子力に未来はあるのか--。福島第1原発で起きた最悪の事故は、この国の原子力産業の先行きに暗い影を落としている。そうしたなか、この国の未来を切り開くエネルギーであると信じて、原子力を専攻する学生たちの目に、今回の事故はどう映っているのか。若き原子力エリートの悩める心に迫った。【浦松丈二】
◇「今こそ専門家必要。自負持ち勉強したい」 でも…揺らぐ進路「皆迷っている」
東京大学五月祭の初日(5月28日)。カラフルな看板の模擬店が並ぶキャンパスに黒いスーツ姿の学生たちがいた。「東大生と学ぶ原子力」フォーラムを企画した工学部有志約20人。旧原子力工学科の流れをくむシステム創成学科環境・エネルギーシステムコース(学年定員48人)の3、4年生たちだ。1960年に創設された原子力工学科時代から脈々と業界リーダーを輩出してきた。福島の事故後、有名になった武藤栄・東京電力副社長や近藤駿介・原子力委員長らはOBだ。また、原子力安全委員会の班目春樹委員長は原子力工学科(当時)で教えてきた。とかく閉鎖的と批判される「原子力村」だが、東大の原子力学徒OBが中核を担っている、というのが大方の見方だ。
「福島の事故後、(原子力分野に)就職するにしても進学するにしても、覚悟が必要になったのは事実です。ただ、今こそ専門家が求められていると思います。そういう自負を持って勉強していきたい」。フォーラムを中心になって企画した4年生の杉山達彦さん(21)はそう話す。
100人以上の聴衆が大教室を埋めた。学生5人が登壇し、事故経緯や放射線が健康に及ぼす影響、火力や太陽光など代替エネルギーについて、あらかじめ準備したスライドを映しながら説明していった。5人は「一人一人がエネルギーを自分の問題として考えてほしいのです」と締めくくった。
福島問題の関心の高さを示すように、この日のフォーラムでは活発な質疑応答が繰り広げられた。その多くは、放射線量の単位など専門的な知見に関するものだった。そして、最後に4列目に座っていた横浜市の会社員(49)が質問に立ち、こう切り出した。「原子力は長期的に日本のためになるかどうか。ご意見をお持ちであればお聞かせ願いたい」。空気の流れが少し変わった。
壇上の学生たちが顔を見合わせる。押し出されるようにしてマイクを握った杉山さんは「私が大事だと思っているのは、0か100か、という強い議論に押されることなく、総合的に今後のあり方を考えていくことです」と答えた。緊張した様子が見て取れた。これで時間切れだった。
■
原子力の専門教育が始まって半世紀余。「この間、さまざまな変遷があった」と話すのは、フォーラムに来ていた東大大学院工学系研究科総合研究機構長の寺井隆幸教授(57)。杉山さんらの先輩に当たる。「システム創成学科は、原子力だけでなくエネルギー全般について広く学んでいます。その前身の原子力工学科時代は、原子力だけを勉強してきたのですが……」
学科再編のきっかけは、スリーマイル島(79年)、チェルノブイリ(86年)という、二つの原発事故の影響だったという。
東大の原子力工学科は93年、「システム量子工学科」に再編され、2000年には再び他学科と統合され、「システム創成学科」として生まれ変わった。門外漢が見たら、これが原子力関係の学問とは想像できないかもしれない。学問の名前から「原子力」の文字を消し去ることで、何やら物事の本質を見えにくくしているよう。
こうした動きは東大だけでない。京大など他の旧帝大でも相前後して、開設されていた原子力・原子核工学科などといった学科名から「原子力」「原子核」といった文字が消えた。
「それでも」と寺井教授は言葉を継いだ。「5年ほど前から、世界的なエコエネルギーの潮流に乗って原子力が見直され始め、『原子力ルネサンス』なんて呼ばれていたのですよ。やっと風向きが変わってきたと思っていたところに、今回の福島の事故が水を差してしまった。主に米国メーカーの基本設計でつくられた、福島第1原発は津波の想定が甘かったのです。女川原発は被災した住民が避難してきたというのに……」と悔やむ。言葉の端々から、米国依存の設計ゆえに壊滅的な事故につながった--と言っているふうにも聞こえた。
■
一方、学生たちは原子力をどうみるのか。フォーラムで原子力を論じた杉山さんは「卒論では原発の安全評価など、大学院は電気系かなあ」と、意外なことを口にする。そして「僕だけじゃないんですよ。原子力国際専攻を目指していた同級生たちも迷っているようです」と打ち明ける。詳しい理由は明かさなかったが、福島の事故が影を落としているのは間違いあるまい。
同級生の田儀(たぎ)和浩さん(21)は「がんの治療に役立つ放射線や陽子線の研究をしたいと考えています。事故を受けて放射線が健康に及ぼす影響に関心を持つようになりました」と話す。
業界も学生の原子力離れに危機感を募らせる。業界団体の日本原子力産業協会は学生を対象に就職説明会を開催している。担当の政策推進部統括リーダーの木藤啓子さんは「昨年は来場者がぐんと増えたのですが、正直、今年はやってみないと分からない状況です」と顔を曇らせた。昨年12月に東京と大阪で開催した説明会には前年比7割増の1903人が参加した。今年は東電が募集を見送り、浜岡原発を停止した中部電力もどうなるか分からないという。
原子力産業の人材不足は日本だけの問題ではない。国際原子力機関(IAEA)が04年にフランス原子力庁のサクレー研究所で初開催した人材育成に関する国際会議。核燃料サイクル開発機構企画部長として派遣された森久起さん(62)=現・原子力研究バックエンド推進センター専務理事=は指摘する。「先進国の原子力産業は本格的なスタートから40年が経過して世代交代期に入っていますが、若手の人材確保が国際的な課題になっています」。ドイツなどの脱原発の動きも影響しているようだ。
森さんは名古屋大学工学部原子核工学科2期生。黎明(れいめい)期に原発の研究者を志した。「私が大学に入ったころは四日市ぜんそくの公害が大きな社会問題になっていました。公害問題から原子力に魅力を感じたのです」とふり返る。
福島の事故では、東電の工程表通りに収束したとしても原子炉処理までの長いプロセスと放射性廃棄物の回収、処理、管理という課題が横たわる。これを解決できるのは原発の専門家しかいない。
森さんは話す。「まだまだ学問としての原子力工学は必要なのです。日本の原子力が試練に立たされているなか、若い学究者の英知が求められているのです」
前出、東大生の杉山さんによると、今回のフォーラムにかかわった約20人の3、4年生のなかで、大学院で原子力専攻を決めた学生はいないという。
==============
「ザ・特集」は毎週木曜掲載です。ご意見、ご感想はt.yukan@mainichi.co.jp ファクス03・3212・0279まで
毎日新聞 2011年6月2日 東京朝刊
(引用ここまで)
常識的に考えて、これからの時代に原子力の分野に優秀な学生が集うってことはほとんど望み薄でしょうね。
(コメント返しはもうすこしお待ちください)