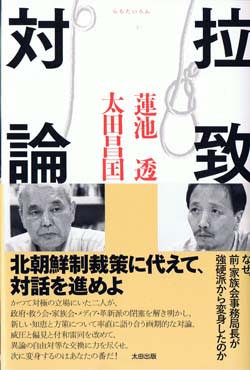このブログ、全然映画を見たって記事を書いていませんね。調べてみると、こちらの記事以来。っていいますか、最近大学院が忙しい(っていうのも事実ですが)と称して映画を全然見に行っていません。これではいけませんので、11月22日(スカーレット・ヨハンソンの誕生日)、神田の岩波ホールに、アニエス・ヴァルダ監督の「アニエスの浜辺」を見に行きました。

だいたい私、映画は渋谷で見ることがほとんどです。東京でたくさん映画館が固まっているところって、銀座、池袋、新宿、渋谷(順不同)あたりでしょうが、いろんな映画館でやっている映画は渋谷で見ますし、渋谷でしかやっていない映画を見ることがまた多いのです。
そういう意味で言うと、岩波ホールってほんと長い間行っていません。ここで上映された映画自体は結構見ているんですが、二番館で見ることがほとんどで、驚くほどこの映画館に足を運んでいません。なぜかはさっぱりわからないのですが、これからは反省してもう少しここで映画を見ることにしました。やはり岩波ホールという映画館の貴重さを考えれば、私も微力ながら可能な限り支援しなければいけませんから。
さてさて、今回見に行った映画の監督であるアニエス・ヴァルダは、ジャック・ドゥミの奥さんです。かつてこのブログで「ベルサイユのばら」の実写版についての記事を書きました。ドゥミはあの映画を監督した人です・・・って書いたら名誉が棄損されちゃいますか。やはり「シェルブールの雨傘」の監督というべきですかね。

この映画はともかくカトリーヌ・ドヌーヴがきれいです。見ていない方はぜひ見てください。損はしないと思いますよ。
この映画は、女性映画監督ですでに80歳を超えているアニエス・ヴァルダが、自らの人生、映画への想い、夫や子供、孫たちへの想い、ゴダールをはじめとするヌーヴェルヴァーグの連中からハリソン・フォードら米国滞在中に知り合った映画人との交流その他その他について、浜辺(フランス語でplage)をモチーフにして語っていく映画です。ドキュメンタリー映画というか自伝映画というべきか、エッセイ映画(シネマ・エッセイっていうんですかね)です。
しかしこのような映画を製作できたアニエス・ヴァルダは幸せ者ですね。ふつうなかなか映画監督はこのような映画は製作できないし、しても本国どころか遠く日本まで上映されて私のような人間がブログで記事にしちゃうんですから。恵まれた女性です。
私の見に行った11月22日は、3連休の谷間で最終回でした。観客を観察すると、若いカップルは皆無、高齢なカップル数組、男同士、女同士がほとんど、あとは単独の観客でした。若い観客が多かったのですが、いかにも映画が好きそうな(たぶん私もそういう風に見られていたんだろうなと勝手に考えます。)人たちばかりでした。それはそうですよね。楽しい連休にこの映画を見に来る人は、映画好きのはずです。
予告編は、アンジェイ・ワイダの「カティンの森」でした。12月5日からの上映です。これは見ないとね。ワイダ自身、この事件で父親を失っています。
さて映画ですが、ベルギーの北海の海岸で、なにか得体のしれない撮影を始めるアニエス・ヴァルダの姿が映し出されます。そしてギリシア人の父親をもっている彼女の幼少時代から話は始まります。
1928年ベルギーのブリュッセルで生まれた彼女は、少女時代を過ごした家を現在の持ち主の行為で何十年振りかに訪れます。そして戦争に翻弄された十代後半の時代、パリに来て美術学校に通った時代、写真家として活動した時代、ジャック・ドゥミとの出会いなどなどが語られます。
彼女はもともと写真家として活動をしていたのですが、1955年に映画製作を始めます。当時女性の映画監督はとても珍しい時代でした。
そしてかつて映画を撮影したロケ地を訪れます。彼女が1950年代に撮影したときに子供だった人も、当然ながらすでに老人といっていい年齢です。懐かしさっと旧交を温めながら、長い歳月が重くのしかかります。
それにしてもこのシーンを見ていると、彼女って人格者なんだなと思います。でなければ、このようなシーンを撮るのは困難でしょう。
1962年、彼女はジャック・ドゥミと結婚します。彼とは、1990年の彼の死まで夫婦関係にありました。
彼女は2人の子供に恵まれます。長女のロザリー・ヴァルダは、この数年は活動していないみたいですが、映画衣装の仕事をしています。調べてみると、ゴダールの映画「パッション」(メル・ギブソンの映画ではありませんよ、当然ながら)の衣装も担当しています。また、前掲の「ベルサイユのばら」でも衣装見習みたいなことをしているみたいですね。お父さんの親心なのかな。
そして、彼女は「シェルブールの雨傘」で、最後のシーンで車の中にいるカトリーヌ・ドヌーヴの娘役でも登場しています。クレジットにはありませんが、なかなかかわいい子です。
長男のマチュー・ドゥミは1972年生まれで俳優を今もしています。しかしそうすると、彼ってアニエスが44歳の時に生まれた子供ですか。当時としてはすごい高齢出産ですね。
そして(私の好きな)ジェーン・バーキンもアニエス・ヴァルダの映画に出演しています。「カンフー・マスター!」ではマチューと共演しました。

当方、この映画は勉強不足で未見ですので、見たらこのブログで記事を書きます。ジェーンのほうも、実の娘たちから母親まで大集合するという一種のお遊び映画ですが。
そしてカリフォルニアでのしばらくの滞在のエピソードも紹介されます。ちょうど、ヒッピー・ムーヴメントやフラワー・ムーヴメントの時代でした。ヴェニス・ビーチに滞在して映画製作を模索します。このときハリソン・フォードともすれ違ったりしたりします。個人的には、アメリカでのエピソードは正直すこしだれました。
ほかにもジム・モリソン(ドアーズのヴォーカル)など、アーカイヴ映像におったまげるような人たちが続出します。顔の広い女性です。
しかし夫のジャック・ドゥミがエイズを患ってしまいます。偏見を恐れて彼(女)らはこの事実を伏せます。この映画によって、ドゥミがエイズで死亡したことが公表されたということのようです。以前は死因は白血病とされていました。
彼女はドゥミの少年時代を描いた「ジャック・ドゥミの少年時代」を製作します。まさに彼の死が訪れる前にこの映画を完成させるために。この映画のクランクアップの直後の1990年10月27日、ジャック・ドゥミは亡くなります。
死の直前のやせ衰えた夫の姿を、カメラはとらえます。ある意味、これ以降のアニエス・ヴァルダは純粋な劇映画を製作していないことからもわかるように(「百一夜」は完全なフィクションではないと思います)、たぶん劇映画としてはこれ以上の作品はつくれないという彼女なりの思いがあるのでしょう。
それにしてもこの映画での浜辺のシーンは美しいですね。真夏の込み合う海岸でなく、荒涼とした海岸の風景もいいものです。
岩波ホールでの上映は12月4日までですが、たぶん全国のミニシアターで上映されることになるでしょう。映画好きでないと見ても面白くないでしょうが、でも悪くないと思います。よろしかったらどうぞ。

だいたい私、映画は渋谷で見ることがほとんどです。東京でたくさん映画館が固まっているところって、銀座、池袋、新宿、渋谷(順不同)あたりでしょうが、いろんな映画館でやっている映画は渋谷で見ますし、渋谷でしかやっていない映画を見ることがまた多いのです。
そういう意味で言うと、岩波ホールってほんと長い間行っていません。ここで上映された映画自体は結構見ているんですが、二番館で見ることがほとんどで、驚くほどこの映画館に足を運んでいません。なぜかはさっぱりわからないのですが、これからは反省してもう少しここで映画を見ることにしました。やはり岩波ホールという映画館の貴重さを考えれば、私も微力ながら可能な限り支援しなければいけませんから。
さてさて、今回見に行った映画の監督であるアニエス・ヴァルダは、ジャック・ドゥミの奥さんです。かつてこのブログで「ベルサイユのばら」の実写版についての記事を書きました。ドゥミはあの映画を監督した人です・・・って書いたら名誉が棄損されちゃいますか。やはり「シェルブールの雨傘」の監督というべきですかね。

この映画はともかくカトリーヌ・ドヌーヴがきれいです。見ていない方はぜひ見てください。損はしないと思いますよ。
この映画は、女性映画監督ですでに80歳を超えているアニエス・ヴァルダが、自らの人生、映画への想い、夫や子供、孫たちへの想い、ゴダールをはじめとするヌーヴェルヴァーグの連中からハリソン・フォードら米国滞在中に知り合った映画人との交流その他その他について、浜辺(フランス語でplage)をモチーフにして語っていく映画です。ドキュメンタリー映画というか自伝映画というべきか、エッセイ映画(シネマ・エッセイっていうんですかね)です。
しかしこのような映画を製作できたアニエス・ヴァルダは幸せ者ですね。ふつうなかなか映画監督はこのような映画は製作できないし、しても本国どころか遠く日本まで上映されて私のような人間がブログで記事にしちゃうんですから。恵まれた女性です。
私の見に行った11月22日は、3連休の谷間で最終回でした。観客を観察すると、若いカップルは皆無、高齢なカップル数組、男同士、女同士がほとんど、あとは単独の観客でした。若い観客が多かったのですが、いかにも映画が好きそうな(たぶん私もそういう風に見られていたんだろうなと勝手に考えます。)人たちばかりでした。それはそうですよね。楽しい連休にこの映画を見に来る人は、映画好きのはずです。
予告編は、アンジェイ・ワイダの「カティンの森」でした。12月5日からの上映です。これは見ないとね。ワイダ自身、この事件で父親を失っています。
さて映画ですが、ベルギーの北海の海岸で、なにか得体のしれない撮影を始めるアニエス・ヴァルダの姿が映し出されます。そしてギリシア人の父親をもっている彼女の幼少時代から話は始まります。
1928年ベルギーのブリュッセルで生まれた彼女は、少女時代を過ごした家を現在の持ち主の行為で何十年振りかに訪れます。そして戦争に翻弄された十代後半の時代、パリに来て美術学校に通った時代、写真家として活動した時代、ジャック・ドゥミとの出会いなどなどが語られます。
彼女はもともと写真家として活動をしていたのですが、1955年に映画製作を始めます。当時女性の映画監督はとても珍しい時代でした。
そしてかつて映画を撮影したロケ地を訪れます。彼女が1950年代に撮影したときに子供だった人も、当然ながらすでに老人といっていい年齢です。懐かしさっと旧交を温めながら、長い歳月が重くのしかかります。
それにしてもこのシーンを見ていると、彼女って人格者なんだなと思います。でなければ、このようなシーンを撮るのは困難でしょう。
1962年、彼女はジャック・ドゥミと結婚します。彼とは、1990年の彼の死まで夫婦関係にありました。
彼女は2人の子供に恵まれます。長女のロザリー・ヴァルダは、この数年は活動していないみたいですが、映画衣装の仕事をしています。調べてみると、ゴダールの映画「パッション」(メル・ギブソンの映画ではありませんよ、当然ながら)の衣装も担当しています。また、前掲の「ベルサイユのばら」でも衣装見習みたいなことをしているみたいですね。お父さんの親心なのかな。
そして、彼女は「シェルブールの雨傘」で、最後のシーンで車の中にいるカトリーヌ・ドヌーヴの娘役でも登場しています。クレジットにはありませんが、なかなかかわいい子です。
長男のマチュー・ドゥミは1972年生まれで俳優を今もしています。しかしそうすると、彼ってアニエスが44歳の時に生まれた子供ですか。当時としてはすごい高齢出産ですね。
そして(私の好きな)ジェーン・バーキンもアニエス・ヴァルダの映画に出演しています。「カンフー・マスター!」ではマチューと共演しました。

当方、この映画は勉強不足で未見ですので、見たらこのブログで記事を書きます。ジェーンのほうも、実の娘たちから母親まで大集合するという一種のお遊び映画ですが。
そしてカリフォルニアでのしばらくの滞在のエピソードも紹介されます。ちょうど、ヒッピー・ムーヴメントやフラワー・ムーヴメントの時代でした。ヴェニス・ビーチに滞在して映画製作を模索します。このときハリソン・フォードともすれ違ったりしたりします。個人的には、アメリカでのエピソードは正直すこしだれました。
ほかにもジム・モリソン(ドアーズのヴォーカル)など、アーカイヴ映像におったまげるような人たちが続出します。顔の広い女性です。
しかし夫のジャック・ドゥミがエイズを患ってしまいます。偏見を恐れて彼(女)らはこの事実を伏せます。この映画によって、ドゥミがエイズで死亡したことが公表されたということのようです。以前は死因は白血病とされていました。
彼女はドゥミの少年時代を描いた「ジャック・ドゥミの少年時代」を製作します。まさに彼の死が訪れる前にこの映画を完成させるために。この映画のクランクアップの直後の1990年10月27日、ジャック・ドゥミは亡くなります。
死の直前のやせ衰えた夫の姿を、カメラはとらえます。ある意味、これ以降のアニエス・ヴァルダは純粋な劇映画を製作していないことからもわかるように(「百一夜」は完全なフィクションではないと思います)、たぶん劇映画としてはこれ以上の作品はつくれないという彼女なりの思いがあるのでしょう。
それにしてもこの映画での浜辺のシーンは美しいですね。真夏の込み合う海岸でなく、荒涼とした海岸の風景もいいものです。
岩波ホールでの上映は12月4日までですが、たぶん全国のミニシアターで上映されることになるでしょう。映画好きでないと見ても面白くないでしょうが、でも悪くないと思います。よろしかったらどうぞ。