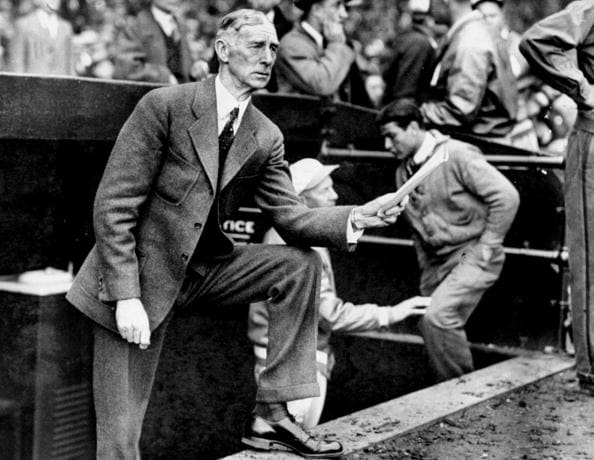御嶽山の噴火は、実に最悪のタイミングで起きたと思います。なにしろ、①紅葉シーズンの②週末土曜日の③正午近くです。これにおまけに④天気が良かったから、まさに最悪です。
御嶽山 大噴火!
上の動画は、NHKのニュースでも放映されました。
当たり前ですが、登山というのも年がら年中山が込んでいるということはないわけで、込むシーズンがあり、込む曜日があり、込む時間があります。そして、その日の天気があります。今回は、山頂に人が多くいる要素が、片端からそろってしまっています。こうなるとどうしようもありません。亡くなったか、ケガをしたか、何とか無事に下山できたかは、正直運でしかありません。今回の噴火は、たぶん山岳遭難の規模としては戦後史上最悪でしょう。噴火自体の災害とかではなく、山岳遭難としては、1963年の薬師岳の愛知大学の遭難や、記憶に新しい2009年の大雪山系トムラウシ山での大量遭難などと比較しても非常に大規模な山岳遭難です。もちろん今回の遭難は1つのパーティーの遭難ではありませんが、ほぼ同じ時に単独の山で起きた遭難という点では、そうそうめったにない規模の山岳遭難です。1991年の雲仙普賢岳の火砕流による大災害は、犠牲者は登山者でなくマスコミ、その関係者(タクシー運転手など)、公務員(自治体職員、警官、消防団員)、山岳学者らです。
それでNHKのカメラが、ちょうど噴火の直後の映像を撮影したというのがまさに上に書いたタイミングを象徴しているわけで、つまりNHKは、紅葉を撮影しようと考えてこの取材をしていたわけです。そういう時期にこのような噴火が起きるというのも、全く予想がつかない(いくら群発地震が起きていたとはいえ、それは気象庁の判断でも「危険」という認識ではなかったわけですから、これまたどうしようもありません)ことです。悪天候の遭難とかなら、冬山は避ける(あるいはそれなりの覚悟をして行く)、悪天候なら無理をしない(トムラウシ山の遭難は、つまりは悪天候で無理に出発して、それでどうにもならなくなったケースです)という判断もできます。天候だったらネットなりラジオなりで天気図もわかりますから、低気圧が接近しているとかは分かるし、あとは自分の判断で小屋にとどまるとかそもそも登山を中止することもできます。トムラウシ山で無理に出発した理由は、同じ日に同じ会社のツアーのパーティーが遭難したパーティーの宿泊した山小屋に入る予定だったので、そうすると山小屋に収まりきれないので出発を強行したというのが公然となっています(最終的な判断をした添乗員兼チーフガイドの人は亡くなっているので真相は不明ですが、まずそのような考えがあったのは間違いないところでしょう)。詳細は、下の書籍参照。

また台風などは発生する季節も決まっていますし、天気予報でだいたいのことは分かりますから、その時はレジャーを控えるとかいろいろ対応はできます。分かって無茶をする人間も存在しますが、それは個人の問題であって、ある意味仕方ないことです。
しかし火山の噴火というのは、地震などと同様、雲仙普賢岳の際のもののように噴火が繰り返されていてそれであのような大火砕流が発生したものなどは登山者などいるはずもありませんが、突発的な噴火というのは当然ながら予想が難しいので、なってしまったらどうしようもないですよね。誰も噴火することを前提に山に登るわけもないわけで(研究者とかだって、そんなに危険なところへは当然行きません)、火口の近くにいて噴火でもされたら目も当てられないとはこのことです。
そうこう考えてみますと、いまの時代「休火山」とか「死火山」とかいうものはすでに学術用語としては使われないようですが、火山に登るからには、もちろん富士山であっても、最悪の事態というのは考えなければいけないかもですね。富士山はこの何百年噴火していませんが(宝永大噴火が、1707年)、御嶽山は1979年に噴火、というわけで、そんなに安全な山でもありません(といいますか、Wikipediaの「死火山」の記事にもあるように、79年のこの山の噴火が、「死火山」という言葉の定義に大きな疑問符をつける結果となったわけです)。もちろんめったなことでそんなことに遭遇するわけでもありませんが、最悪の事態というのはいろいろあるわけで、富士山だって噴火しないわけじゃないくらいの考えではいたほうがいいと思います。少なくとも火山は、火山でない山よりは危険です。それは考えないといけません。
もう一つ、今回の件にかぎった話ではありませんが、個人が容易に写真のみならず動画を撮影できて、それを容易に不特定多数の人間が閲覧できるようになった時代というのもすごいですよね。今回でも、かなり臨場感のある動画がいろいろニュース番組でも使われていました。それこそ公共放送であるNHKだって、YouTubeの動画をニュース番組に使用するくらいですから、いろいろな動画がいろいろなところで見られる時代だということも考えさせられます。動画にかぎらず、HPなりブログなりツイッターなりフェイスブックなりで自分の意見なり行動なりを不特定多数に発信して、それで時に苦情が殺到して「炎上」なんて事態になることもありますが、あらためてネット時代というのはすごいものだなと思います。いい悪いはともかく、油断のならない時代です。
そして、やはり登山届も考え直す必要がありますね。保険と同じく、何もなければ意味がないものなので、「面倒」「無意味に個人情報が警察に知られる」とかでおよそ提出されませんが、家族に渡すくらいのことはしておいたほうがいいのでは。様式を作って、必要なところだけ書けばいいようにしておけば、2回目からはそんなに面倒でもないでしょう。
といいつつ私も、登山はしませんが、海外をほっつき歩いている際は、どこにも連絡先を伝えないこともありますから(一応旅行の届けは職場にしますが、未定の場合もある)、そんなにえらそうなことはいえないか。
あ、それからどうでもいい話ですが、登山者が行方不明になったりして、消息がつかみにくい場合は、警察はその人の自宅のPCなどを調べます。その場合、アダルトサイトとかしょうもないサイトをひんぱんに閲覧していたり、しょうもない写真や動画を保存しておくとそれも確認されますので、そんなことは心配しても仕方ないことかもしれませんが、一応知っておいてください。無事に帰ってきたはいいが、奥さん(夫)と家庭不和になるということもなくはない。