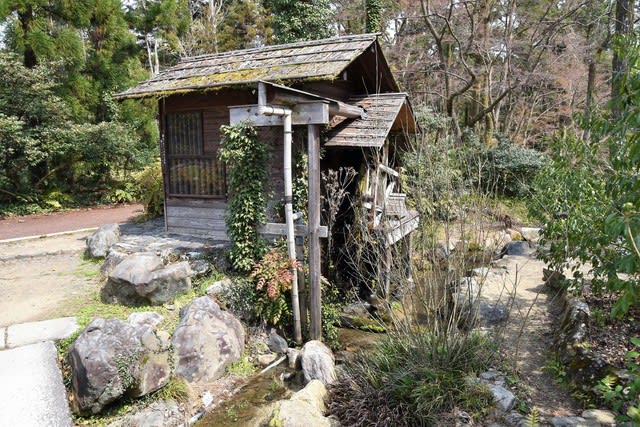3月28日に大阪市鶴見区にある「咲くやこの花館」に行ってきました。

咲くやこの花館は、今回の関西旅行の中で、京都府立植物園と共に必ず訪れたい目的地でした。
公式HPにある、「館長挨拶」によると、この植物園は次のように紹介されています(抜粋)。
「咲くやこの花館」は、1990年に開催されたEXPO’90「国際花と緑の博覧会」のメインパビリオンとして大阪市により建設されました。「咲くやこの花館」では、「花の万博」のテーマでもある「自然と人間との共生」を継承し、「熱帯から極地までの広範囲の植物」を種々の手法で栽培し紹介しています。訪ねていただくだけで世界中の植物に出会える、世界的にも数少ない施設です。
館全域で、分類、進化、気候と形態、文化、有用性、栽培など植物の重要な分野が学べます。生きた教材で、大切な地球を知る体験をしていただけたらと願っています。 ヒマラヤの青いケシや日本のコマクサ、そして熱帯スイレンなどは開花調整し、一年中見られるほか、季節の花も含め常に300種類以上の花を常に楽しむことができます。
季節の花の展示会、興味深いテーマのイベントなどの開催もあります。 また、館内フラワーツアーや咲くや塾による植物の重要な情報紹介もあります。 およそ5500種、15000株のさまざまな植物は皆様に世界の花旅、そして憩いのひとときをお届けできることでしょう。
館内に入ると、先ず館内フラワーツアーを申し込み、ツアーが始まるまでの時間で、高山植物室を観に行きました。
中でもヒマラヤの青いケシ、メコノプシス ベトニキフォリアとメコノプシス グランディスは、是非とも見たいお花でした。普段観ることができない、あるいは一生観ることができないかもしれないお花を、きれいな状態で見せていただけることは幸せです。
■メコノプシス ベトニキフォリア





■メコノプシス グランディス

フラワーツアーでの説明によると、これらのお花はヒマラヤの3800mの高地に咲きます。この植物園では種子を冷凍庫で保存し、咲かせたい時期に合わせ冷凍庫から出し、温度管理をしながら発芽~開花させるとのことです。
このような手段は展示植物園での理にかなった栽培法で、研究所などでも同様の方法で開花調整がされています。
数人の植物園のスタッフの方とお話ししましたが、皆さんとてもお花に対する愛情が深く大切に育てられていることが分かり、嬉しくなりました。
さて、フラワーツアーの参加者は5人で、スタッフの方は見ごろのお花を選んでとても丁寧に説明してくださいました。
途中写真を撮る時間も十分取れて、また、気に入ったお花をツアー終了後、再び観に行くこともできました。
ツアーで見学した植物室ごとに観ていきましょう。
■熱帯雨林植物室
トロピカルオーキッド、熱帯スイレンなどが見ごろでした。どのお花も色彩が鮮やかで、香りにも特徴があります。

昨夜開花したオオオニバス(スイレン科オオオニバス属)です。今夜ピンク色に変わりその後枯れます。


熱帯スイレンです。最後の1枚はニンファエア 'オータムクラッシュ'という名前のお花です。




■熱帯花木室
ブーゲンビレア(オシロイバナ科ブーゲンビレア属)がきれいでした。珍しいヒスイカズラ(マメ科ヒスイカズラ属)も見ることができました。


■乾燥地帯植物室
何といっても、サボテンのお花がきれいでした。毎日、きれいに咲いているお花を選んで展示を入れ替えるそうです。


■高山植物室
ヒマラヤの青いケシの他に、世界の高山植物、チューリップやスイセンの原種が見ごたえがありました。
ヨーロッパアルプスに自生するエーデルワイス(和名は西洋薄雪草、キク科ウスユキソウ属)です。

北アメリカ西岸中部に自生するレウィシア コチレドン(スベリヒユ科レウィシア属)です。

礼文島に自生するレブンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ族)です。このお花は自生地に行ってお花畑を観たいです。

千島列島に自生するチシマルリオダマキ(キンポウゲ科オダマキ属)です。

北アルプスなどに自生するシナノナデシコ(ナデシコ科ナデシコ属)です。このお花は白馬岳などで自生しているのを観ました。

チューリップ(ユリ科チューリップ属)の原種です。



スイセン(ヒガンバナ科スイセン属)の原種です。

ムスカリ(ヒアシンス科ムスカリ属)の原種です。

これで関西紀行①~④はお終いです。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
リンク⇒ 関西紀行(その③花博記念公園鶴見緑地)

咲くやこの花館は、今回の関西旅行の中で、京都府立植物園と共に必ず訪れたい目的地でした。
公式HPにある、「館長挨拶」によると、この植物園は次のように紹介されています(抜粋)。
「咲くやこの花館」は、1990年に開催されたEXPO’90「国際花と緑の博覧会」のメインパビリオンとして大阪市により建設されました。「咲くやこの花館」では、「花の万博」のテーマでもある「自然と人間との共生」を継承し、「熱帯から極地までの広範囲の植物」を種々の手法で栽培し紹介しています。訪ねていただくだけで世界中の植物に出会える、世界的にも数少ない施設です。
館全域で、分類、進化、気候と形態、文化、有用性、栽培など植物の重要な分野が学べます。生きた教材で、大切な地球を知る体験をしていただけたらと願っています。 ヒマラヤの青いケシや日本のコマクサ、そして熱帯スイレンなどは開花調整し、一年中見られるほか、季節の花も含め常に300種類以上の花を常に楽しむことができます。
季節の花の展示会、興味深いテーマのイベントなどの開催もあります。 また、館内フラワーツアーや咲くや塾による植物の重要な情報紹介もあります。 およそ5500種、15000株のさまざまな植物は皆様に世界の花旅、そして憩いのひとときをお届けできることでしょう。
館内に入ると、先ず館内フラワーツアーを申し込み、ツアーが始まるまでの時間で、高山植物室を観に行きました。
中でもヒマラヤの青いケシ、メコノプシス ベトニキフォリアとメコノプシス グランディスは、是非とも見たいお花でした。普段観ることができない、あるいは一生観ることができないかもしれないお花を、きれいな状態で見せていただけることは幸せです。
■メコノプシス ベトニキフォリア





■メコノプシス グランディス

フラワーツアーでの説明によると、これらのお花はヒマラヤの3800mの高地に咲きます。この植物園では種子を冷凍庫で保存し、咲かせたい時期に合わせ冷凍庫から出し、温度管理をしながら発芽~開花させるとのことです。
このような手段は展示植物園での理にかなった栽培法で、研究所などでも同様の方法で開花調整がされています。
数人の植物園のスタッフの方とお話ししましたが、皆さんとてもお花に対する愛情が深く大切に育てられていることが分かり、嬉しくなりました。
さて、フラワーツアーの参加者は5人で、スタッフの方は見ごろのお花を選んでとても丁寧に説明してくださいました。
途中写真を撮る時間も十分取れて、また、気に入ったお花をツアー終了後、再び観に行くこともできました。
ツアーで見学した植物室ごとに観ていきましょう。
■熱帯雨林植物室
トロピカルオーキッド、熱帯スイレンなどが見ごろでした。どのお花も色彩が鮮やかで、香りにも特徴があります。

昨夜開花したオオオニバス(スイレン科オオオニバス属)です。今夜ピンク色に変わりその後枯れます。


熱帯スイレンです。最後の1枚はニンファエア 'オータムクラッシュ'という名前のお花です。




■熱帯花木室
ブーゲンビレア(オシロイバナ科ブーゲンビレア属)がきれいでした。珍しいヒスイカズラ(マメ科ヒスイカズラ属)も見ることができました。


■乾燥地帯植物室
何といっても、サボテンのお花がきれいでした。毎日、きれいに咲いているお花を選んで展示を入れ替えるそうです。


■高山植物室
ヒマラヤの青いケシの他に、世界の高山植物、チューリップやスイセンの原種が見ごたえがありました。
ヨーロッパアルプスに自生するエーデルワイス(和名は西洋薄雪草、キク科ウスユキソウ属)です。

北アメリカ西岸中部に自生するレウィシア コチレドン(スベリヒユ科レウィシア属)です。

礼文島に自生するレブンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ族)です。このお花は自生地に行ってお花畑を観たいです。

千島列島に自生するチシマルリオダマキ(キンポウゲ科オダマキ属)です。

北アルプスなどに自生するシナノナデシコ(ナデシコ科ナデシコ属)です。このお花は白馬岳などで自生しているのを観ました。

チューリップ(ユリ科チューリップ属)の原種です。



スイセン(ヒガンバナ科スイセン属)の原種です。

ムスカリ(ヒアシンス科ムスカリ属)の原種です。

これで関西紀行①~④はお終いです。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
リンク⇒ 関西紀行(その③花博記念公園鶴見緑地)