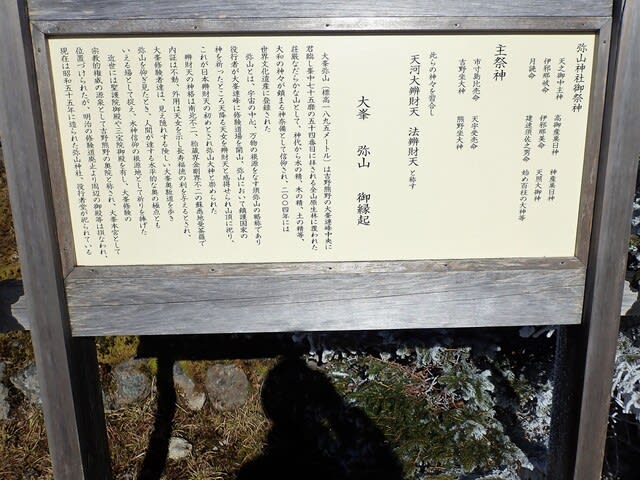新型コロナウイルスで明け暮れた2020年。
ブログの記事から1年を振り返ってみます。
先ずは山行から振り返ってみましょう。
元旦の朝を赤城山の地蔵岳山頂で迎えました。元旦の「旦」という字は、地平線から昇る太陽を表しています。
まさにその太陽を拝み、一年がスタートしました。

同月19日には、毎年冬の恒例行事となった赤城山黒檜山に登りました。

2月には黒斑山と茅ヶ岳に出かけました。黒斑山(浅間山の外輪山)は3度めで、いずれも冬に登っています。

茅ヶ岳には初めて出かけました。深田久弥さんの終焉の地。いい山を最後に選ばれたと思います。

3月から5月は、新型コロナウイルスの流行で山行を自粛しました。その中で唯一登ったのが、緊急事態宣言が出る前に出かけた大菩薩岳でした。
車で出かけ、誰とも会うことなく帰ってきました。丸川峠から見た富士山が美しかったです。

緊急事態宣言が解除され、6月に伊吹山に出かけました。早朝出発し午前中に下山したので、ほとんど人とは会いませんでした。
あいにくの曇り空ででしたが、お花がきれいで、小鳥の鳴き声もほとんど途切れることなく、満足のいく山行でした。

7月に入ってすぐに平ヶ岳に出かけました。コロナ自粛後の初めての本格的な登山で、行程21km、4万9千歩あまり、14時間の山行になりました。
この山はまさに花の山です。名前の通り頂上部が平たく、湿原が広がっています。そこに百花繚乱の高山植物が咲き乱れていました。

平ヶ岳から下りて、そのまま同級生との白山に出かけました。今年は南竜ヶ馬場のケビン(貸し切りのコテージ)を利用しました。
雨のなか、誰もいない早朝の南竜庭園の散策は思い出に残りましたが、ここでの高山植物の時期にはまだ早いようでした。

8月には再び白山に入りました。私にとって15回目の白山で、初めて北部からの入山でした。
加賀禅定道を歩くのも初めてで、これまでに歩いた越前禅定道、美濃禅定道と合わせて、3禅定道を全て歩けたのは大きな喜びでした。

9月の初めには、山の師匠夫妻と共にテント泊で赤岳に登りました。私にとって八ヶ岳は3度目で、赤岳は初登頂でした。
山に入って、山仲間と、山を語るのは最高にいいものです。ワインを飲みながら暗くなるまで語り合いました。

9月末から10月にかけて、鳥海山と月山に出かけました。どちらの山も私には初めてでしたが、何故か懐かしさを覚えました。
「いつか来たような、そして、いつかまた来るだろう、この山に」


10月末には荒島岳にも登りました。ここから見る白山はとりわけ素晴らしいです。いつかこの山頂に泊まり、朝夕の白山を観てみたいと思います。

そして、今年の山仕舞いは奈良の八経ヶ岳でした。ずっと来たい山でした。良い時期に登ることができました。
これで私の百名山巡りも52座になりました。同じ山に何度も行っていますが、それでも半分を過ぎました。さて、残りの人生でいくつまで行けるでしょうか。

続いて、撮ったお花をご覧いただこうと思いましたが、あまりにも数が多く整理できません。
6月に出かけた伊吹山、7月の平ヶ岳で撮った写真から、いくつかご覧いただきます。
タツナミソウ(伊吹山)

オドリコソウ(伊吹山)

シロバナイワカガミ(平ヶ岳)

タテヤマリンドウ(平ヶ岳)

ハクサンコザクラ(平ヶ岳)

また、白山の高山植物については、8月に白山花紀行を更新しました。その中から2葉をご覧いただきたいと思います。
タカネマツムシソウ

タカネナデシコ

次に、鳥については、毎年七次川調整池に来る鳥を撮っています。
今年は出かける頻度が増しました。あわせて水鳥以外も撮り始めました。
どれも最近の写真なので再掲は避けようと思いましたが、1つだけ選ぶとすると、この写真になると思います。
11月に撮影した、6羽のヒナを連れたハクチョウの大家族です。最近も時々姿を見かけますが、元気にしています。

最後に、植物クロスワードについて書いておきます。
クロスワードの掲載を8月から始めました。はじめは出題の間違いもありましたが、皆さまのお蔭様で今月まで続いています。
おまけのクイズも始めて、自己評価(≒手前味噌)ながら好評なようです。
さて、ここまで、今年のブログをまとめてみました。
ご覧いただいた皆様には、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
最後の最後に、おまけのクイズを出してお茶を濁します。
正解は挙げませんので、ご自由にお楽しみくださいませ。
次の(1)から(8)は日本のことわざです。①から⑧に入る適当な言葉を語彙らんのア~コの中から選び、記号で答えなさい。
(1) ( ① )の耳に念仏。
(2) ( ② )に釘。
(3) 言わぬが( ③ )。
(4) ( ④ )の祭り。
(5) ( ⑤ )八百。
(6) ( ⑥ )は災いの元。
(7) ( ⑦ )たけだけしい。
(8) ( ⑧ )で茶を沸かす。
■ 語彙らん
ア. アト イ. ウマ ウ. ヌカ エ. ハナ オ.スガ
カ. ウソ キ. クチ ク. ヌスット ケ. ヘソ コ.アベ
2021年が明るく希望の持てる年になりますように、そして皆様にとって良い一年となりますようお祈り申し上げ、今年のブログ納めとさせていただきます。
ありがとうございました。
来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ブログの記事から1年を振り返ってみます。
先ずは山行から振り返ってみましょう。
元旦の朝を赤城山の地蔵岳山頂で迎えました。元旦の「旦」という字は、地平線から昇る太陽を表しています。
まさにその太陽を拝み、一年がスタートしました。

同月19日には、毎年冬の恒例行事となった赤城山黒檜山に登りました。

2月には黒斑山と茅ヶ岳に出かけました。黒斑山(浅間山の外輪山)は3度めで、いずれも冬に登っています。

茅ヶ岳には初めて出かけました。深田久弥さんの終焉の地。いい山を最後に選ばれたと思います。

3月から5月は、新型コロナウイルスの流行で山行を自粛しました。その中で唯一登ったのが、緊急事態宣言が出る前に出かけた大菩薩岳でした。
車で出かけ、誰とも会うことなく帰ってきました。丸川峠から見た富士山が美しかったです。

緊急事態宣言が解除され、6月に伊吹山に出かけました。早朝出発し午前中に下山したので、ほとんど人とは会いませんでした。
あいにくの曇り空ででしたが、お花がきれいで、小鳥の鳴き声もほとんど途切れることなく、満足のいく山行でした。

7月に入ってすぐに平ヶ岳に出かけました。コロナ自粛後の初めての本格的な登山で、行程21km、4万9千歩あまり、14時間の山行になりました。
この山はまさに花の山です。名前の通り頂上部が平たく、湿原が広がっています。そこに百花繚乱の高山植物が咲き乱れていました。

平ヶ岳から下りて、そのまま同級生との白山に出かけました。今年は南竜ヶ馬場のケビン(貸し切りのコテージ)を利用しました。
雨のなか、誰もいない早朝の南竜庭園の散策は思い出に残りましたが、ここでの高山植物の時期にはまだ早いようでした。

8月には再び白山に入りました。私にとって15回目の白山で、初めて北部からの入山でした。
加賀禅定道を歩くのも初めてで、これまでに歩いた越前禅定道、美濃禅定道と合わせて、3禅定道を全て歩けたのは大きな喜びでした。

9月の初めには、山の師匠夫妻と共にテント泊で赤岳に登りました。私にとって八ヶ岳は3度目で、赤岳は初登頂でした。
山に入って、山仲間と、山を語るのは最高にいいものです。ワインを飲みながら暗くなるまで語り合いました。

9月末から10月にかけて、鳥海山と月山に出かけました。どちらの山も私には初めてでしたが、何故か懐かしさを覚えました。
「いつか来たような、そして、いつかまた来るだろう、この山に」


10月末には荒島岳にも登りました。ここから見る白山はとりわけ素晴らしいです。いつかこの山頂に泊まり、朝夕の白山を観てみたいと思います。

そして、今年の山仕舞いは奈良の八経ヶ岳でした。ずっと来たい山でした。良い時期に登ることができました。
これで私の百名山巡りも52座になりました。同じ山に何度も行っていますが、それでも半分を過ぎました。さて、残りの人生でいくつまで行けるでしょうか。

続いて、撮ったお花をご覧いただこうと思いましたが、あまりにも数が多く整理できません。
6月に出かけた伊吹山、7月の平ヶ岳で撮った写真から、いくつかご覧いただきます。
タツナミソウ(伊吹山)

オドリコソウ(伊吹山)

シロバナイワカガミ(平ヶ岳)

タテヤマリンドウ(平ヶ岳)

ハクサンコザクラ(平ヶ岳)

また、白山の高山植物については、8月に白山花紀行を更新しました。その中から2葉をご覧いただきたいと思います。
タカネマツムシソウ

タカネナデシコ

次に、鳥については、毎年七次川調整池に来る鳥を撮っています。
今年は出かける頻度が増しました。あわせて水鳥以外も撮り始めました。
どれも最近の写真なので再掲は避けようと思いましたが、1つだけ選ぶとすると、この写真になると思います。
11月に撮影した、6羽のヒナを連れたハクチョウの大家族です。最近も時々姿を見かけますが、元気にしています。

最後に、植物クロスワードについて書いておきます。
クロスワードの掲載を8月から始めました。はじめは出題の間違いもありましたが、皆さまのお蔭様で今月まで続いています。
おまけのクイズも始めて、自己評価(≒手前味噌)ながら好評なようです。
さて、ここまで、今年のブログをまとめてみました。
ご覧いただいた皆様には、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
最後の最後に、おまけのクイズを出してお茶を濁します。
正解は挙げませんので、ご自由にお楽しみくださいませ。
次の(1)から(8)は日本のことわざです。①から⑧に入る適当な言葉を語彙らんのア~コの中から選び、記号で答えなさい。
(1) ( ① )の耳に念仏。
(2) ( ② )に釘。
(3) 言わぬが( ③ )。
(4) ( ④ )の祭り。
(5) ( ⑤ )八百。
(6) ( ⑥ )は災いの元。
(7) ( ⑦ )たけだけしい。
(8) ( ⑧ )で茶を沸かす。
■ 語彙らん
ア. アト イ. ウマ ウ. ヌカ エ. ハナ オ.スガ
カ. ウソ キ. クチ ク. ヌスット ケ. ヘソ コ.アベ
2021年が明るく希望の持てる年になりますように、そして皆様にとって良い一年となりますようお祈り申し上げ、今年のブログ納めとさせていただきます。
ありがとうございました。
来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。