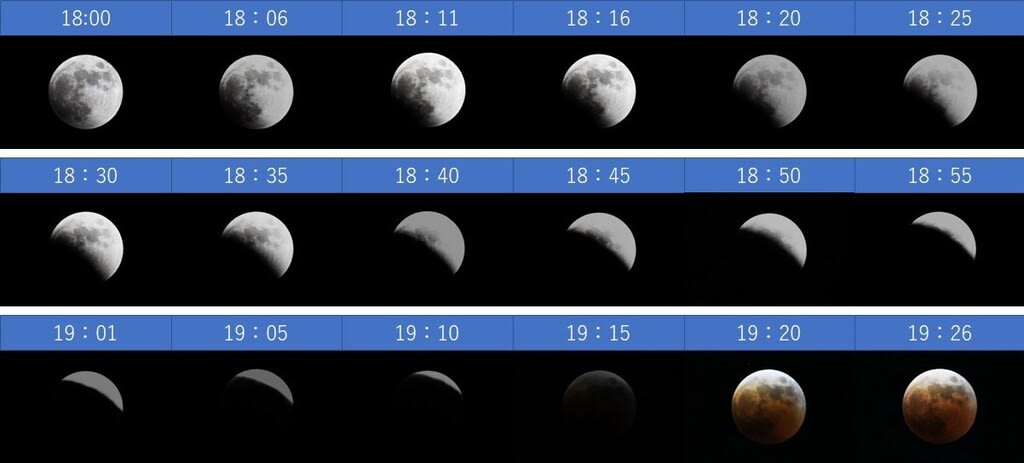ほぼ1ヶ月ぶりに谷津干潟へ出かけました。
前回出かけたときは、カモの種類が少なくて残念でした。さて、今回はどうでしょう。
先ず、淡水池へ行ってみました。いつも数種類のカモがいるところです。
ところが、どうしたことでしょう? カモどころか、1羽の鳥の姿も見えません。
気を落として干潟へ向かうと・・
そこにいるのはダイサギとカワウだけ。
中には、婚姻色が出ているものが数羽混じっていました。
■カワウ
Great Cormorant
カツオドリ目ウ科
Phalacrocorax carbo
河鵜/L81cm W129cm

双眼鏡で干潟を隈なく見渡すと、遠くにカモらしき群れが見えました。
行ってみると、先ず見つけたのは数羽のカルガモでした。
これではテンションが上がりません。カルガモもうつむいてしまいました。
■カルガモ
spot-billed duck
カモ目カモ科マガモ属
Anas zonorhyncha
軽鴨/L61cm


先へ進むと、潜水を繰り返しているカモが見えました。
スズガモの♀のようでした。似ているカモにコスズガモがいます。

コスズガモの翼帯の白色部が次列風切に限定されるのに対し、スズガモは白色部が初列風切にも及んでいます。
間違いなくスズガモでした。
■スズガモ
Greater Scaup
カモ目カモ科ハジロ属
Aythya marila
鈴鴨/L45cm


スズガモは海水域を好むカモです。谷津干潟ではよく見かけるカモのようです。
下の写真の、左の3羽は♂の成鳥、右の1羽は♂のエクリプスのようです。

こちらは♀です。嘴の基部周辺に大きな白色部があるので、遠くからでもよく目立ちます。

スズガモは潜水を繰り返していました。






さらに進むとヒドリガモがいました。
■ヒドリガモ
Eurasian Wigeon
カモ目カモ科マガモ属
Anas penelope
緋鳥鴨/L49cm


さらには、オカヨシガモも確認できました。
■オカヨシガモ
Gadwall
カモ目カモ科マガモ属
Anas strepera
丘葦鴨/L50cm

潟の西の端の方にはマガモがいました。ヒドリガモなどと混群を作っていました。
■マガモ
Mallard
カモ目カモ科マガモ属
Anas platyrhynchos
真鴨/L59cm

最後に、ダイサギが大勢集まって大騒ぎしている様子です。
この日はボラがたくさん入ってきていました。他の小魚もいたかもしれません。
ダイサギが集団で猟りをするのは聞いたことがありません。潮の流れの関係でこの場所に小魚が集まったため、このような光景が観られたように思います。
ダイサギ以外の鳥も混じっていますが、種の判別は出来ませんでした。

この日潟にいたカモは、全部で数百羽程度だったと思います。写真を上げなかった中に、オナガガモ、ホシハジロもいたように思います。
特に珍しいカモはいませんでしたが、たくさんのカモを観られてよかったです。
年内にまた訪ねたいと思います。