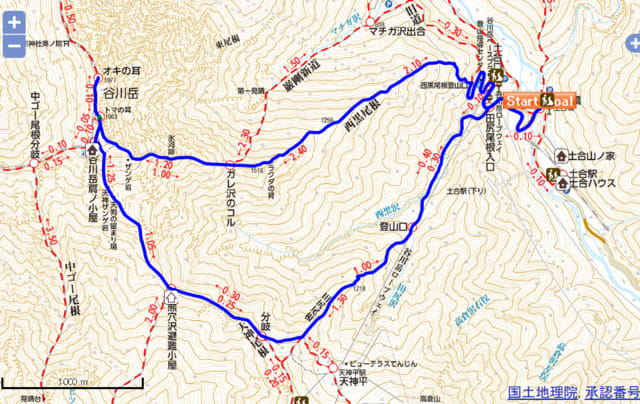ブログにも赤い実の投稿が増えてきました。
我が家では、ナンテン、ソヨゴ、マンリョウ、センリョウが赤い実をつけます。
◇ナンテン
ナンテン(南天)は、メギ科ナンテン属の常緑低木です。
中国原産で、日本では西日本、四国、九州に自生していますが、古くに渡来した栽培種が野生化したものと考えられています。


既に小鳥に食されて、実の大半がなくなりました。小鳥が真っ先に食べる実です。
◇ソヨゴ
ソヨゴ(戦、冬青、具柄冬青)は、モチノキ科モチノキ属の常緑小高木です。
風に戦(そよ)いで葉が特徴的な音を立てる様が名前の由来とされています。
中国、台湾および日本の本州中部、四国、九州に分布し、本州における分布の北限は新潟県と宮城県です。
開花期は5~6月頃で、雌雄異株のため、雌株があっても近くに雄株が無ければ結実しないとのこと。


毎年、木いっぱいに赤い実をつけます。この実も小鳥が食しますが、人気はいまいちです。
この木は以前スズメのねぐらになっていましたが、最近は場所を変えたようです。
◇コムラサキ
コムラサキ(小紫)は、シソ科ムラサキシキブ属の落葉低木です。
ムラサキシキブとは別種ですが混同されやすく、コムラサキをムラサキシキブといって栽培していることが大半のようです。
全体によく似ていますが、コムラサキの方がこぢんまりとしています。個々の特徴では、葉はコムラサキは葉の先端半分にだけ鋸歯があり、ムラサキシキブは葉全体に鋸歯があることで区別できます。(Wikipediaより抜粋)

この木は、以前ムラサキシキブとして投稿したことがあります。
ヒヨドリなどが食しますが、センリョウやナンテンほど人気がないようです。
リンク⇒赤い実をつける木々- 近所の散歩道(千葉県白井市)2018/11/20
我が家では、ナンテン、ソヨゴ、マンリョウ、センリョウが赤い実をつけます。
◇ナンテン
ナンテン(南天)は、メギ科ナンテン属の常緑低木です。
中国原産で、日本では西日本、四国、九州に自生していますが、古くに渡来した栽培種が野生化したものと考えられています。


既に小鳥に食されて、実の大半がなくなりました。小鳥が真っ先に食べる実です。
◇ソヨゴ
ソヨゴ(戦、冬青、具柄冬青)は、モチノキ科モチノキ属の常緑小高木です。
風に戦(そよ)いで葉が特徴的な音を立てる様が名前の由来とされています。
中国、台湾および日本の本州中部、四国、九州に分布し、本州における分布の北限は新潟県と宮城県です。
開花期は5~6月頃で、雌雄異株のため、雌株があっても近くに雄株が無ければ結実しないとのこと。


毎年、木いっぱいに赤い実をつけます。この実も小鳥が食しますが、人気はいまいちです。
この木は以前スズメのねぐらになっていましたが、最近は場所を変えたようです。
◇コムラサキ
コムラサキ(小紫)は、シソ科ムラサキシキブ属の落葉低木です。
ムラサキシキブとは別種ですが混同されやすく、コムラサキをムラサキシキブといって栽培していることが大半のようです。
全体によく似ていますが、コムラサキの方がこぢんまりとしています。個々の特徴では、葉はコムラサキは葉の先端半分にだけ鋸歯があり、ムラサキシキブは葉全体に鋸歯があることで区別できます。(Wikipediaより抜粋)

この木は、以前ムラサキシキブとして投稿したことがあります。
ヒヨドリなどが食しますが、センリョウやナンテンほど人気がないようです。
リンク⇒赤い実をつける木々- 近所の散歩道(千葉県白井市)2018/11/20