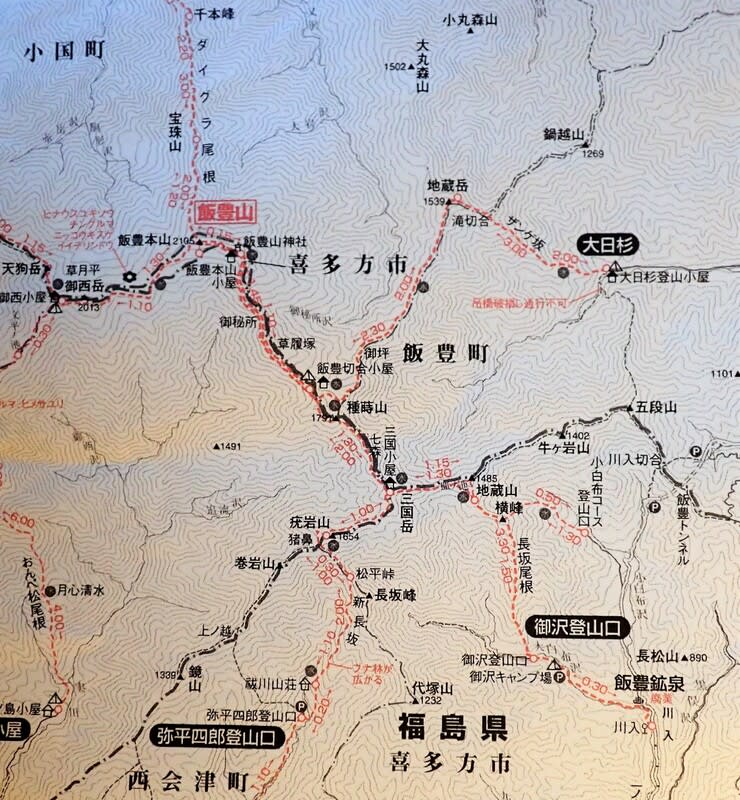8月27、28日、越後三山の最高峰・中ノ岳(標高2085m)から、兎岳(標高1926m)を経由して、利根川水源の山・大水上山(標高1831m)、さらに進んで丹後山(標高1809m)を巡る1泊2日の山旅を、山の師匠と一緒に楽しんできた。
中ノ岳へのアクセスは、関越道の六日町インターから三国川(さぐりがわ)沿いに15kmほど東に進むと、三国川ダムの先の十字峡登山口に着く。

三国川ダムは、1992年に完成したロックフィル式のダムで、高さが119.5mあり、魚野川の流域では最大の規模である。
このダムの完成のお陰で、十字峡登山口までの道路も全線が2車線の立派な舗装路となっていて、車でのアクセスは極めて良かった。
さて、今回の山行だが、1日目は十字峡を出発して中ノ岳に登頂後、頂上直下の避難小屋で泊る。
出発地点から山頂までの標高差は1629mある。途中の日向山(標高1561m、中ノ岳5合目)までを、先ずはご覧いただくことにしたい。

5時30分、十字峡登山センター脇の駐車場に到着。
休日には満車になることもあると聞いていたが、平日のこの日は3台が停まっていた。

軽く朝食を摂って、5時54分、登山センター前の、越後三山登山口入口(標高456m)から登山開始。
いきなりコンクリートで固められた急坂を登っていく。

しばらく進むと地面は土に変るが、急坂は変らない。

風はなく、とにかく暑い。
前夜も熱帯夜で、十分な睡眠が取れなかったのが応える。
6時36分、1合目に到着。周辺は藪で、この辺りはやや平らになっている。
ちなみに、この登山道は5合目までは見晴がない。1合、2合と順に石標があるのが救いである。

1合目を過ぎると、さらに傾斜が急になった。顔や首の汗を手ぬぐいで拭いながら登る。

ホツツジ(ツツジ科ホツツジ属)が咲いていた。この先かなり上の方までホツツジは見られた。

急登が続くが、花を見ると本当に癒される。

崩れやすい岩場。鎖が設置されていた。

急登は2合目の直前まで続いた。

7時44分、2合目に到着。寝不足と暑さでふらふらになり、横になって5分ほど休んだ。
写真は余裕の山の師匠。

2合目を過ぎると傾斜が緩やかになった。順調に高度を上げていくが暑さが身に応える。
実をつけた樹木が現われる。見たことはあるが、名前が分からない。
なつみかんさんからコブシではないかと教えていただきました。図鑑を見るとコブシかタムシバのようです。なつみかんさん、ありがとうございました。


師匠はこんな写真も撮っていた。


8時37分、3合目を通過。
ナナカマド(バラ科ナナカマド属)の実も色づき始めていた。

この樹木も名前が分からない。
なつみかんさんからアブラツツジではないかと教えていただきました。なつみかんさん、ありがとうございました。
アブラツツジはツツジ科ドウダンツツジ属の落葉低木で、本州の中部地方以北に分布します。中ノ岳周辺の山々でも確認されています。
花期は5~6月で、枝先から長さ2~3cmの総状花序が垂れ下がり、白い花を5~10個つけます。
果実は蒴果で、長さ4~5mmの楕円形をしています。

9時22分、4合目を通過。
こちらはリョウブ(リョウブ科リョウブ属)だと思う。
日本に自生するリョウブ属は1種で、南北アメリカやアジアには60種ほどが知られているとのこと。
目立つ木ではないので、花が咲いていないと見逃すだろう。

道端にオニアザミ(キク科アザミ属)が現われた。この先、たくさん現れた。


そして、10時43分、ようやく5合目の日向山に到着した。
ここで休んでいた先行者に追いついた。
ザックを下ろして大休止とする。朝ごはんに食べる予定だった海苔巻きの残りを食べ、昼食に用意したおにぎりは晩ごはんに回すことにした。
水分は適宜摂っていたが、2.5L持ってきた飲料水が足りるか心配になる。

5合目で、初めて目指す山、中ノ岳が見えた。中ノ岳から右には、翌日歩く稜線が長々と続いていた。

越後三山の最高峰・中ノ岳、利根川水源の山・大水上山を巡る山旅 ②(日向山~池の段)に続く。