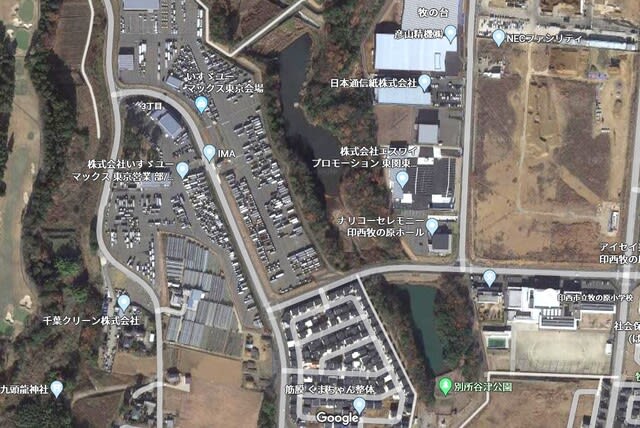先日、庭に来るメジロの動画を載せました。
すると「癒やされる~っ」と嬉しい感想をいただきました。
そこで、新たに動画を撮り直し、30分バージョンに編集しました。
お暇なとき、お時間がたっぷりあるときにご覧ください。
庭に来るメジロ(30分 編)
キャスト:メジロさん(2羽)
プロディース:shu
カメラ:shu
すると「癒やされる~っ」と嬉しい感想をいただきました。
そこで、新たに動画を撮り直し、30分バージョンに編集しました。
お暇なとき、お時間がたっぷりあるときにご覧ください。
庭に来るメジロ(30分 編)
キャスト:メジロさん(2羽)
プロディース:shu
カメラ:shu