夏が終わりに近づくと ・・・
夏が終わりに近づくと
いつも夜更けに物悲しさを覚える
夏が終わりに近づくと
明日への庶幾に満ちた感情より
昨日までの苦杯の情感が甦る
夏が終わりに近づくと
新進気鋭な人との出逢いより
会者定離は世の常を思い知る
夏が終わりに近づくと ・・・ 。
■ 昭和懐古 ■
“案分” が
あった昭和という時代
“加勢” が
できた昭和という時代
柔らかな人の心
緩やかな時の流れ
そのアナログな潮流こそ
心を癒していたかもしれない
我々の昭和という砌
第五大成丸
嫁さんは仕事、
昼飯を作って食べるのが面倒になり、娘二人を誘い千里中央へ
ランチのついでに買い物 ・・・・・ いや、買い物のついでにランチ ・・・・・
まあ、どちらでもいいのですが、とりあえず出掛けました。
広場では、
「第9回こいや祭り」 とやらで、たくさんの若者が色とりどりの衣装を纏って元気
一杯に踊っています。それぞれのチームでメンバー構成も衣装も踊りも違います。
また、チームごとにテーマやコンセプトを持って踊りに取り組んでいるようです。
そう言えば、
ゴールデンウィークに兵庫県高砂市の商業施設(ショッピングセンター)でも
こうした祭りに遭遇しました。若者を中心に “踊りたい!” が増えているのだ
と思います。少し視点を変えれば、“どこかで、何かで、発散したい ・・・ ” と
いうことかもしれません。自己表現とまでは言えませんが、自己確認をしたい
という表れであったり、同じ価値観の仲間探しなのかもしれません。
仲間と踊ることで、
「楽しくなる」 「スカッとする」 という感覚を共有しようとしているのだと思います。
一生懸命に踊って汗している姿、少し緊張しながらも笑顔が溢れ楽しんでいる
若者の様子は、なかなかエエもんです。それに比べうちの冷めた娘たちは ・・・
結局、私は1時間余り一人で踊りを見ていました。
( 私は意外とこんな若いヤツらが好きです )
ちょっと驚いたことが ・・・
この踊りに参加していたあるチーム(大人数のグループ)の若者たちは、自分たち
の出番が終わって帰る際、エスカレーターを使わず、階段の端っこを一列になって、
他の人の迷惑にならないように静かに地下鉄の改札まで行儀よく進んで行った
のです。ただそれだけのことなのですが、当たり前のことが当たり前でなくなった
今の時代に “これはどうしたことか ・・・ ?” と、少し嬉しい戸惑いを覚えました。
たぶん今の時代、
親や学校の先生が “一列になって歩きなさい” “静かに迷惑の掛からないように”
と言っても聞かない子どもが多いはずです。小学校や中学校では完全に学校崩壊
になっているところもあると聞きます。親(先生)と子ども(生徒)には、お互いの
言い分があり、どうしても、それぞれの立場からの正論を持ち出し、衝突してしまい
ます。最終的には、子ども(生徒)が悪いと言わないまでも、親(先生)は 「大人」
という冠を翳して “正しい” を押し通すことが多いものです。子どもには 「子ども」
という冠しかなく、負かされることが多いものです。その不平不満を発散しきれず
ストレスとなり、そのうち ・・・
逆に今の時代、
子ども(生徒)が親(先生)を理解できる環境になれば、自分たちの “正しい” を
自分たちでちゃんと作れる能力は、大人(親や先生)より絶対に上だと思います。
もちろん、それを実践し高めていくパワーとスピードも上でしょう。もっと大人が
若者を信用してやるべきですし、もっとそれぞれを認めてやるべきなのでしょうね。
この部分は私も大人(親)として反省しきりです。どこかに “まだまだ子どもやから
解ってない” と勝手に決めつけているところがあるような気がします。意外と
子どもの親離れを望んでいるような言い方をしながら、実は、親が子離れできない
部分が多くの親にはあるのかもしれませんね。
ランチに話を戻します。
お蕎麦屋さんで娘たちと食べている時、二つ隣の席に家族4人が座りました。
お父さんとお母さんと子ども(小学校低学年の女の子と幼稚園くらいの男の子)
でした。ごく普通の家族です。しかし、食べ物を注文している時から、両親は
それぞれ自分の携帯電話を触っているのです(たぶんメールの打ち込み)。
結局、料理が運ばれてくるまで両親ともに子どもとは一言も会話をせず、向かい
合っているお互いとも目を合してなかったように思います。しかし、夫婦が喧嘩を
している様子でもありません。その光景が非常に不自然で、同じ子を持つ親
として何とも不安で、大人としてこの上なく不快でした。
数年後を想像すると、
あの子どもたちも自分の携帯電話を持つようになり、家族4人で出掛けても
それぞれの携帯電話だけを見て、それぞれ他人のように時間を過ごすのです。
家族って何なのでしょう ・・・ ? 親って ・・・ ? 子どもって ・・・ ?
やはり、最初の責任は ・・・ 「大人(親や先生)」 にあったのではないでしょうか。
今日、
私が見た若者たちの笑顔があの若者たちの本当に素直な笑顔だとすれば、
その同じ笑顔を自分の親や先生に日頃見せている若者は何人いるのだろう?
と、ふと思いながら踊りを見ていた私自身、親として、大人としての在り方を
再考すべきなのだろうと深く反省をした一日となりました。
■ こんたく堵 ■
何かに縋り
何処かに逃避しているのは
子たちではなく大人たちだろう
「子は親を映す鏡」 でなく
「子は親そのもの」 である
子は
親を正面から見てマネしているのではない
子は
親の後姿を素直ににコピーしているだけ
親は
それに気づかず子の足りないを指摘する
親は
自分で自分の足りないを指摘しているのだ
要は
親と子は鏡のように左右反対ではなく
同じ方向を向いている左右対称なのである
親が右手を上げれば子も右手を上げる
そのまんま!なのである
第五大成丸
先日、
能勢町(大阪府豊能郡)で自家有機野菜を美味しく食べさせてくれる
『 しゃらん ど らーは (Sharan de Raaha) 』 というレストランへ行ってきました。
7月の終わり頃、
ふらっと能勢をドライブしている道中、道の駅の中に野菜の直売所があり、
不揃いのトマトや胡瓜、茄子、オクラ、大葉などの野菜が安かった(何でも1袋
100円前後だった)ので買って帰ったのですが、これが “なんでこんな甘いん?”
と思うほど、それぞれの野菜本来の甘味が溢れ、素直に “旨い!” と感動
しました。野菜の新鮮さ以上に気持ちが新鮮になったような気がして ・・・ 。
ということもあり、
何度か能勢近辺を探索していて見つけたレストランの一つなのですが、
帰ってからネットでお店のHPや他ブロガーさんの記事を読んだのですが、
印象としては “少し構えたレストランかなぁ?” でした。先日、昼から時間が
取れましたので、急遽、予約も入れず訪問してみました。
自宅から一般道で約1時間、
ランチタイムに間に合うかどうか ・・・ 到着した時、午後2時を過ぎていました。
隣接の駐車場は満車で、約100m離れた臨時の駐車スペース(畑の畔道?)を
使わせて頂きました。その長閑な雰囲気と空気が心を癒します。
店内に入ると、
客席スペースは思ったほど広くはなく、どちらかといえば、手造り感があり
アットホームで寛げる内装で、“構えた感じのレストラン” ではありませんでした。
ホールで接客をしておられる若い女性(奥様だった)の笑顔とリズムが心地よく、
一層、寛げる雰囲気になっています。
さて、メニューですが、
一般的なランチメニュー(ランチタイムのサービスメニューなど)は無いようで、
カルトメニューからオーダーしました。行く前から、薪をくべて石窯で焼くピッツァ
だけはどうしても食べたかったのですが、実際に行くと、サラダやパスタも気に
なります。ただ、2人だったのでそう何品もオーダーできません。クルマだった
こともありアルコールも ・・・ 。結局、隣のテーブルの料理ポーションを見て、
「ピッツァ」 「パスタ」 「野菜の薪窯焼き」 をそれぞれ一皿ずつオーダーしました。
「ピッツァ・マルガリータ」 という名前だったと思います。
生地は弾力がありモチモチです。焦げ目のところを口に入れると、まるで
お餅を食べているような感じです。写真では判りづらいですが、一般的な
宅配ピザ屋のMサイズ以上はあると思うのですが、脂っけやベタつき感が
全然なく、何枚でも食べられそうな食感と味わいです。“旨かった!” です。
次回は、「ピッツァ・ラーハ」 を ・・・
帰り際にシェフに聞いたところ、パスタは最近メニューに加えたそうです。
まだまだ試行錯誤だということでしたが、このパスタも美味しかったです。
ただ、名前が ・・・ 間違いがあってはいけませんので割愛させて頂きます。
幅10cmもあろうかというタリアテッレにジャガイモと自家製ソーセージを加え、
クリームソースで絡めたパスタだったと思います(自信なし)。タリアテッレの
ボイル加減が特に良かったです。確かにソースも大事ですが、パスタや
具材(じゃがいも)の茹で加減も大きなポイントだと思います。近頃、街場で
よくある “何でもかんでもアルデンテ” なお店はどうなのでしょうかねぇ ・・・ 。
次回は、自家製のベーコンが入ったパスタを ・・・
生の野菜です。
“次の一品の前に食べて、焼いた状態と比べてみてください” と提供して
くださいました。非常にサプライズな印象でした。ここ最近、能勢の野菜を
生で食べていましたので、私たちには感動というより納得な味でしたが、
初めて訪れた方々は感動するでしょうね。そして、その後の “焼き” に ・・・
「季節野菜の薪窯焼き(9品)」 だったと思います。(メモしてくればよかった ・・・)
野菜はオーダーが通ってからカットしているようです。古い野菜やカットして
時間が経った野菜を焼くと早く焦げてしまうそうです。新鮮な状態でそのまま
石窯へ ・・・ これがポイントなのでしょうね。オリーブオイルにバルサミコ酢を
加えたドレッシングとハーブ入りの七味唐辛子が添えられていましたが、
ほとんどの野菜がそのまま食べて美味しいものばかりです。もちろん、焼けば
旨いだろうと予想のつく玉葱や茄子、パプリカは当然ですが、トマトやオクラ、
胡瓜なども焼くことで、素材が持っていた本来の甘味が引き出されていることが
よく解ります。とても美味でした!
次回は、秋野菜・冬野菜を ・・・

「オープンエアキッチン」 で作業をしているオーナーシェフです。
写真の承諾は得ましたが、ブログ掲載までは了解を得ていませんので、
あえて顔が判る写真は使用しませんが、自身の考えや理想をしっかり持った
キリっとした男前です。(ちなみに奥様はチャーミングで可愛らしい女性です)
“基本的に自分のところで作っている野菜しかお客様には提供しない” という
ポリシーでお店をやられているようです。敷地内の見えるところにも野菜や
ハーブを栽培されていました。また、自家製のベーコンやソーセージを仕込む
ためのスモーカーもあり、薪をくべてピッツァや季節野菜を焼き上げる石窯も
手造りだということです。
全ての部分で、“こだわり” という言葉より、“譲れないもの” という気持ちの
ニュアンスを感じるお店でした。また、その環境をお二人で切り盛りされている
若いご主人と奥さんの人柄も少し垣間見えたような気がして、非常に癒された
ランチタイムでした。( お店を出た時には4時を過ぎていました )
ほんとうに、ごちそうさまでした!!
また訪問させて頂きます。
■ 造形憧憬 ■
飲食店の店名を出して評価することは本意ではない
ただ、「二升五合」 や 「楽時々益」 のカテゴリーでなく
“ものづくり” として 「造形憧憬」 で表しておきたいお店
飽食の時代を超えて尚、暴食に向かおうとしている
街場にある 「食」 の基本を見直すために ・・・
第五大成丸
「播州ハム」 は、創業から50年以上、
真面目にハム・ソーセージ造りをしている老舗です。
今ではメディアやネットの普及で全国区になりました。
「播州ハム」 は、
姫路駅から西へ徒歩5分位の場所にある小さな工場で造られています。
早朝、中央市場でバイトし、学校帰りに駅前をうろついていた高校時代から
その存在は知っていましたが、その当時は、テレビの影響を大きく受ける時代
でしたから、大手ハム会社と並んでいると見劣りしていた記憶があります。
時代が変わり、
素材重視の本物志向や健康を意識した無添加の味などが求められています。
結果、昔ながらの “ものづくり” を継承している環境や職人が見直されています。
何か流行ると皆が右を向き、何か問題が起こると皆が左を向く他人依存な時代。
何とも可笑しげな話です。もうそろそろ消費者それぞれが責任を持って自己選択
しなければならない時代ではないでしょうか。もちろん、供給側も ・・・ 。
三代目のご主人は、
「どうすれば、地方の正直なハム屋の存在をお知らせし、まじめに造るハムを
買っていただけるのだろうか?」 と日々悩んでいたそうです。そんな時、あの
阪神淡路大震災(1995年)が起こり、ボランティア活動でインターネットと出会い、
ネットショップを立ち上げ、ハムの販売を開始したそうです。お客様から届く
「おいしかった」 というメールに社員共々感動したそうです。
要は、
いくら真面目に美味しいものを造っても、世間に認知されなければ自己満足で
終わってしまいます。その認知のキッカケ作りのツールとしてネットを活用する
ことは非常に良いことだと思います。但し、物を売るためだけに活用すると必ず
シッペ返しがくることを忘れてはなりませんが ・・・ 。
「播州ハム」 の約束(表題のみ)
◆ 肉を選ぶ ・・・ おいしさは良い肉選びから始まる。
◆ 塩を知る ・・・ ハム造りには化学調味料はいらない。
◆ 手を抜かない ・・・ 受け継いだ納得できる作業を守る。
◆ 炭火で焼く ・・・ 熟練の技と経験が問われる。
“こだわり”
と表現すれば、そうかもしれませんが、昔から “ものづくり” をしている環境や
職人にとっては、至極、当たり前なことではないかと私は感じます。
「こだわることにこだわらず、こだわらないことにこだわる」 これは、私が仕事に
取り組む時のポリシーです。“こだわり” なんて人に言うべきものではないという
意味です。“こだわり” は自身の中にあるもので、偶々、仕事や作業を通して
一端が他人に見えるだけのものです。それで済ますべきではないでしょうか ・・・ 。
工場横にある直売店で少しだけ買って帰りました。
スモークが得意ではない私ですが、ここのハム・ソーセージは大丈夫です。
赤ワインを ・・・ と思いましたが、ボンレスハムはそのままスライスして、
ボロニアソーセージも軽くソテーした程度で食べたかったので、ちょっとクセの
あるスパークリングワインを合わせてみました。まあ、悪くはなかったのですが、
やはり軽めでスパイシーな赤ワインあたりがあれば良かったかも ・・・ 。
■ 造形憧憬 ■
この情報過多で無分別な時代において
ほんまもんの “ものづくり” を表現するのは
ややもすれば、オリンピックで金メダルを取る
のと同じくらいむずかしいことかもしれない
なら、金メダルを目指すより、使い手の笑顔を
集めてみるのも悪くないのかも ・・・
第五大成丸
夏空にモクモクと沸き立っていた積乱雲が少し弱々しく
名残惜しそうに RUMION のリアボディーに映り込んでいる。
熱い熱い戦いの末、
第90回の全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)は、
北大阪代表 「大阪桐蔭高校」 が見事な優勝で幕を閉じました。
日本各地で地方予選が始まった頃、
テレビニュースでは、“今年も暑い(熱い)季節がやってきました!”
と、アナウンサーが伝えます。そして、一月後、本大会が終われば、
“時折、涼しい風が吹き抜け、季節は確実に秋に向かっています。”
というナレーションがお決まりのように流れる。
苦しい練習を毎日繰り返していると、
“夏って何でこんなに長いんや!?” と思う高校球児は多かったはず。
地方予選を戦い抜き、長年の夢だった甲子園を掴んだ球児たちは慌ただしく
本大会へ ・・・ そして、勝ち上がり決勝戦まで勝ち進んだ球児たちの口からは、
“長いようで短かった夏。もっと、もっと続いてほしかった。” という感想が ・・・ 。
( これが、“青春” ってヤツでしょう! ・・・ か? )
今年も “熱い夏” をありがとう!
■ 楽時々益 ■
「色即是空、空即是色」
“この世のすべての事物は空である”
という教えを理解するのは難しい
たしかに、空は掴みどころがなく
常に形を変えながら見せてくる
世の中、どうしようもなく難儀である
ただ、その一瞬一場面であっても
自分が見た空の大きさと鮮やかさを
しっかり脳裏に焼き付けておけば
それが 「あの時見た空」 となって
心のアルバムに残り、そして甦る
第五大成丸
帰省して自由に行動できる時間があれば、
私は家族とは別行動で出向く場所が数ヶ所あります。
「R250」 から行ける数ヶ所の港(港湾)や海岸線です。
今回の帰省は一泊二日だったので、
単独で自由に行動できる時間はありません。仕方なく、家族も連れて ・・・
今思えば、
子どもたちが小さい頃は、実家を拠点としてあちらへこちらへとよく遊びに行った
ものでしたが、ここ数年はほとんど同じパターンで数日を実家で過ごすだけの
帰省になっていました。子どもたちにとっては、楽しみというより家族の半強制な
参加行事として捉えるようになってきていたようです。
元々、
私はアウトドアが好きではなく、山や川へキャンプに行くという習慣もなく、一日中
海で仕事をしていた家業の影響なのか、夏になっても海に行きたいとも思わず、
子どもたちを海水浴にもほとんど連れて行ってやらなかったことに気づきました。
私が子どもの頃、
親父の仕事関係を中心に、親戚も含め大人数でバスをチャーターして、季節に
応じて、松茸狩りに栗拾い、梨狩りや葡萄狩り、花見に温泉 ・・・ などなど
あちこち連れて行ってもらったものでした。ただ、子どもの頃、酔っ払いの大人が
嫌いで、身内が団体で動いて盛り上がることに少しトラウマもあります。
その中で、
毎年、親父の船で写真にある 「家島諸島」 へ海水浴に出掛けたことは今では
大きな想い出です。( 今は海上保安庁がうるさいので無理ですが ・・・ )
おふくろたちがこれでもかというほど沢山作った弁当とビールやジュースを積み
出発します。麦藁帽子を被り、大人はなぜか皆、白いシャツに黒いサングラスを
掛けているのです。( これは昭和なイメージでしょうか ・・・ )
私は毎年、
その海水浴に一人二人友達を誘います。たぶん、その友達も未だに非日常な
想い出として脳裏に残っているはずです。船の舳先から海に何度も飛び込み
日が傾くまで遊んだことを ・・・ 。
実家が
「釣具屋」 の友達がいました。( 今も地元で親父さんの後を継いで釣具屋経営 )
その釣具屋の主催で毎年、大きな船をチャーターして一泊の釣り大会が行われ
ていました。その友達が私を誘ってくれたので何度か連れて行ってもらいました。
正直、釣りは好きではありません。どうも性分に合いません。ただ、その友達とは
波長が合い、親父さんとも話が合いましたので、一緒に過ごすことが楽しかった
記憶が残っています。( 釣りの好きな人の気持ちが少し解ったような ・・・ )
人間関係には
“波長” という感覚、たぶん、それぞれの価値観の確認が大きく影響を与えている
のではないでしょうか。それはお互いの好き嫌いだけではなく、自己主張や相手の
気持ちを汲むという人間としてのコミュニケーション能力にも波及しているような
気がします。子どもの頃に、できるだけその活動を活発にしておくことは重要だと
感じます。( 偏った人間関係が偏った人間性をつくってしまうのかも ・・・ )
家島諸島の写真は、
赤穂御崎に近い海岸線から撮りました。家族を連れて赤穂までドライブに ・・・
予約ができなかったナポリピザで有名な 「SAKURAGUMI」 に “ひょっとして” を
期待して行ってみましたが、あっさり断られました。( 次回、もっと早く予約を! )
仕方なく、坂越にある 「海の駅 しおさい市場」 へ向かいました。ここは、家業の
港湾工事で毎日仕事に来ていたところなので地元感覚です。埋め立てて綺麗に
整備された港を見ると、冬の寒い時期に親父と一緒に仕事した想い出が蘇ります。
さて、
子どもたちにはこのルートどう見えたのでしょうか?
海が見えて景色の良いドライブコース、という印象しかなかったかもしれません。
街では駅前の表情が変われば、街自体の印象は変わります。道沿いにあった
お店が変われば、街に集まる人の層も多少変わります。港や海岸線も同じです。
私はその変化の確認の為に、時間が許す限りクルマを走らせたいと思うのです。
街で街の変化を視るように ・・・
■ こんたく堵 ■
今、自分が辿っている道は
昔、誰かが切り開いて歩いた道だ
という感覚を常に持ちたい
一人では何もできないのだから ・・・
第五大成丸
書写山から姫路市街を見渡して ・・・
私が高校卒業まで住んでいた街。もう大阪の方が長くなってしまいましたが、
この街には実家があり、親兄弟や親戚、友人知人もたくさん住んでいます。
今回の帰省は一泊二日。
“行ったことないとこ行こうや!” と末娘が一言。確かに、ここ最近は帰省しても
ワンパターンな日程で済ませていました。特に、一泊二日だとそうなります。
ちょっとヘンですが、本屋で一般旅行者のように街の情報誌を家族で漁ります。
それでも、
新しい飲食店の情報は新鮮であり実質的に役立ちます。しかし、この街には
遊べるところがありません。“無い” と言うと語弊がありますが、“遊びに行きたい”
ところが無いのです。もっと言えば、“連れて行きたい” ところが少ないのです。
ただ、
誇れる場所がない訳ではありません。世界文化遺産ともなった国宝姫路城は
誰に言っても否定されることはありません。しかし、子どもが何度もリピートしたい
場所ではありません。サファリパークや動物園、水族館などの施設に行けば
一日楽しく遊べます。が、“この街へ来てわざわざ○○○” という範疇で捉えれば、
行くたびに満足感・満足度は低下してしまいます。
家族が言います。
“ 東京ディズニーランドみたいな遊園地があれば ・・・ ”
“ 北海道の旭山動物園のような動物園を造ったらええのに ・・・ ”
“ 沖縄の美ら海水族館みたいな水族館やったら行ってみたい ・・・ ”
と。たしかにオッサンの私でもそう思います。が、そう簡単にはいきませんよね。
結局、
需要側の言い分を供給側が丸飲みできるかといえば、それは難しい相談です。
ましてや、自治体が主体となれば ・・・ 。街(都会)に住んでいると、大体の欲求は
満たされるものです。供給側は採算ベースを持ちつつも、どこまで満たすべきかを
計りながら進めることができます。鬩ぎ合いはあるにせよ、持ちつ持たれつの関係
で成り立ちます。しかし、そこには甘えも生まれます。
ですから、
地方が都市部に劣等感さえ持たなければ、北海道の動物園や沖縄の水族館の
ような発想が生まれる可能性はあります。都会では出し得ない存在感も示せる
かもしれません。そうした地方の存在感はその街自体の存在意義に他なりません。
いかに “どんな街にしたいか(するのか)” を誰かが持つかどうかだと考えます。
この街の最大の問題は、
大きな都会でもなく、辺鄙な田舎でもない、中途半端なロケーションの街だと
いうことです。歴史含め育むべきものと未来へ向けて創造すべきもののバランス
が取れていません。また、バランスを取ろうとする者を支援するような街質もあり
ません。“何かできることはないのか?” と、ふと考えている自分に気づいた時、
歳相応かもしれませんが、これまで自身の成り立ちに関わった街や人に対して、
自分なりに思慮することは無意味ではないと思えるようになり、この街の問題点が
これまで自己中心的な思慮を繰り返してきた自分自身とクロスオーバーします。
写真は、
ハリウッド映画 「ラストサムライ」(主演:トム・クルーズ) のロケ地にもなった
「書写山」 からの眺望です。それこそ、あの姫路城の天守閣には何度か登って
いますが、この書写山には行ったことすらありませんでした。家族もお初でした。
康保3年(966) 性空上人によって開かれ、比叡山と同じ天台宗の修行道場である
お寺 「天台宗別格本山 書寫山圓教寺」 があります。本当に恥ずかしい話ですが、
私自身、正式な名前を初めて知りました。
今回、
拝観を目的に来たわけでなく、ラストサムライの撮影が行われた場所が見れたら
・・・ と、麓から出ているロープウェイに乗ってみたい、という軽い気持ちで上がって
来ましたので、志納所の前まで行って、そこそこ大きな(広い)敷地であることと、
ロケ現場であった「護法堂拝殿」 と 「開山堂」 という施設が、その敷地の一番奥
の方にあるということが判明 ・・・ 即座にUターンして展望台へ向かいました。
( また、改めて拝観に来たいと思います )
たぶん、
この市街地の景色を上層から見たのは初めてです。 Google で見る航空写真より
やはり “実物” がいいものです。“こんな地形やったんや!” 灯台下暗しです。
ここに来る車中での事、子どもたちから “この標識にある地名何て読むん?” と
何ヶ所かで質問されました。ほとんど答えられたのですが、私も知らない地名が
数ヶ所ありました。大阪は読み方の難しい地名がたくさんあることで有名ですが、
地方でも難しい地名はあるものです。しかし、それが自身の育った街にあるにも
関わらず、まったく “知らない” というのはやはりちょっと恥ずかしいものです。
自身が
生まれた街、育った街、住んでいる街くらいは “知るべき” だと感じた一日でした。
■ 街的興趣 ■
人 道 街
人なり 道なり 街なり
人なりに 道なりに 街なりに
興味を持たなければただの言葉
興味を持てば興趣が増すだろう
第五大成丸
毎年、盆と正月には実家へ帰省します。
今年もお墓参りを兼ねて家族で帰省しました。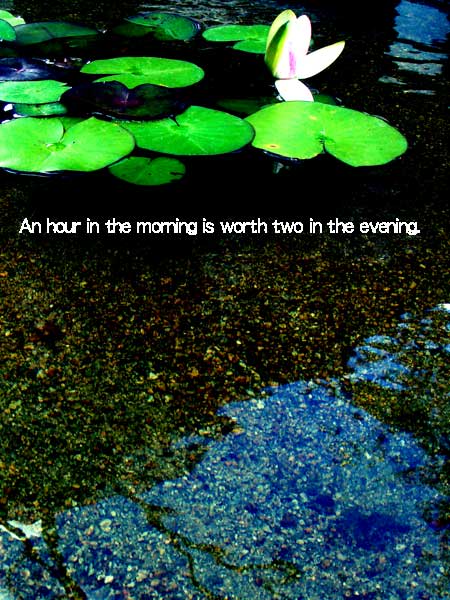
今回、
上の娘はバイトが入っていて帰省できなかったのですが、嫁さんと息子が
同じ日に休みを取ることができましたので、珍しく家族4人がクルマに同乗
しての移動となりました。
ここ数年、
それぞれの仕事やプライベートのスケジュールが合わず、誰かが一日遅れて
電車で追い掛けて来たり、数時間の滞在でトンボ返りしなければならないことが
あったりと、最初から最後まで纏まって動くということができないことが多くなって
いましたので、クルマもゆったり7人乗れるエスティマから5人乗りのコンパクトな
ルミオンに乗り換えた(ECO換えした)という経緯がありました。ただ、乗り換えた
途端に、なぜか4人5人と纏まって乗ることが増えました。皮肉なものです。
さて、
ガソリン価格高騰の影響でしょうか、それともカレンダー(前半)なのでしょうか、
高速道路は例年ほどの渋滞はなく、意外とスムーズに流れておりました。まあ、
混んでも片道100㌔ほどの道のりですので、ひどく疲れたり我慢できないような
状態になることはないのですが、一応、渋滞でエアコンが効かなくなるなどの
可能性(ルミオンに4人乗車の車内環境)も考慮して、朝早く(5:00 a.m.)スタート
したお陰で、渋滞にはほとんど遭わず7時前には実家に到着してしまいました。
“涼しいうちに墓参りを ・・・”
ということで、荷物を置くとすぐにお墓へ向かいました。小学校の裏手、小高い
山裾にある墓地へは、お寺さん横の小道を通るのですが、毎年、お盆の時期は
木々に張り付いた蝉(セミ)たちが、これでもかというほど 「蝉時雨コンテスト」 を
開催しているものなのですが、今年は例年ほど鳴いていないような気がしました。
朝早かったせいか、それとも、温暖化の影響がここにも ・・・ そうだとしたら、
環境の変化が生態系にも深刻な影響を及ぼしているのかもしれませんね。
8時前、
お墓参りを済ませて実家へ戻ると、何故か、昭和時代の 「喫茶店のモーニング
サービス」 の話題となり、“昔、250円でコーヒーにトースト、サラダとゆで卵、
フルーツも付いてたかなぁ ・・・” と私が言うと、嫁さんが “うちの近所はもっと
すごかった ・・・” と、他人がやっているお店なのに、妙な自慢合戦となりました。
当たり前ですが、息子たちには全くイメージできないようです。
ということで、
「喫茶店のモーニングサービス」 を求めて動くことになりました。
すると、おふくろが “モーニングやったらええとこあるから行こや!” と ・・・ 。
「R250」 を西に向かうこと約20分、そこには、270席もあるビュッフェスタイルの
大きなバイキングレストランが ・・・ 私たちが求めていたお店とは全く違いました
が、朝7時半から11時まで、何と 「大人480円」 で食べ飲み放題(取り放題)です。
それは “ビュッフェレストランの破格で豪快なモーニングサービス” でした。
( こんな価格設定で儲け出てるのぉ ・・・ ??? )
店内は、
お盆休み(夏休み)ということもあり、小学生のいる家族連れでいっぱいでした。
街場にあるシティーホテルのランチバイキング以上のメニュー(品数)でした。
プレートに載りきらないほど料理を盛り付けている子どもたち、ロールパン・
クロワッサン・蒸しパンなどパン全種類を制覇している若い兄ちゃんと姉ちゃん、
何種類ものサラダにこれでもかというほどのドレッシングを掛けているメタボな
オヤジ群、家と同じ?ようにご飯とお味噌汁を食べておられるお年寄り夫婦、
大盛のカレーライスを両手に持って額に汗しているオバサン ・・・
それこそ、十人十色。 色々な人(家族)が存在するものです。( スゴイ!)
どちらかというと、
わが家は夜行性の家族ですので、朝からこれだけタイトに行動するのは
何年ぶりのことだったでしょうか。ただ、このお店の“モーニング風景” には
呆気に取られながらも、わが家族もそれなりに楽しめたお盆の早朝でした。
■ こんたく堵 ■
昔の諺、
“早起きは三文の○”
まんざら捨てたものではない
今日、「得」 ではなく 「徳」 が
当て嵌まったからかもしれない
第五大成丸
久々のアルコール摂取です。
“手ぇーが震えまするぅ~” ・・・・・ 冗談です。

体調を崩して20日以上経ちました。
まだ薬が手離せない状態ですが、少しずつ快方に向かっているように感じます。
まず、見ただけで胃が膨張しそうで口にできなかった油ものや辛いものなど
刺激の強い料理を少し食べてみたいと思うようになってきたこと、カラダよりも
頭が全く受けつけなかったアルコールを徐々に脳みそが欲するようになってきた
こと、“これって、快方(解放?)に向かってるんちゃうかぁ! ・・・ ?”
病み上がりのカラダ。さて、最初に流し入れるアルコールは ・・・
やはり、ワインにしました。家に白のスティルワインの在庫がありません。
唯一、野菜室に入っていたスパークリング(スペインのカヴァ)を頂きましょう。
少し氷水に浸けて適温まで冷やします。コルクを開けてフルートグラスに注ぎます。
少量を口に含みます。口の中に冷たさが広がり、その後すぐに、発泡した細かな
気泡と甘味が広がります。なかなか、ええ感じです!久しぶりに、ええ感じです!
( なんか、生き返った気分ですなぁ! )
さて、次は ・・・
調子に乗ってもダメみたいです。
( しゃ~ない、今日はこの辺でやめとったるわぃ! )
何せ、酒の肴もなく、おかずは 「しゃぶしゃぶ」 です。( なんか違うでぇ ・・・ )
脂肪の少ない豚赤身肉の超薄スライスと笹身かと思うほどの鶏胸肉のスライス
が申し訳ない程度浮いているオリジナル?のお鍋です。もちろん、野菜と豆腐が
メインです。甘いごまダレ禁止!ポン酢に大根おろしをい~っぱい入れて食べる
ように指導を受けました。“あぁ、ありがとうございます!”
( 早よう、ステーキかなんか喰いながら赤ワインを飲みたいもんですなぁ ・・・ )
1+1=3 CAVA/Brut
■ ワイン 名 : 1+1=3(ウ・メス・ウ・ファン・トレス)/ブリュット
■ 生産者 : ジョセップ・ピニョル
■ 原産国 : スペイン
■ 地 方 : ベネデス
■ 品 種 : チャレッロ45% パレリャーダ30% マカベオ25%
■ 上 代 : 2,205yen
~以下リアルワインガイド18号より抜粋~
ラベルに大きく記された 「1+1=3」 のデザインがとても印象的なスペインの
スパークリング。これは自社栽培、自社ビン詰めの、シャンパーニュで言う
ところのレコルタン・マニピュランと同じ。扱うインポーターは 「ドメーヌ・カバ」
と名付けているが、確かにぴったりだ。品質はこの価格帯のスパークリング
としてはかなり秀逸。ミツ、酵母の品の良い香り。とても澄んだ味わいは適度
なほろ苦さが良好で、妙な甘さやベタつきは皆無のキレの良いもの。シャン
パーニュ大手メゾンのスタンダード品(5千円台)と同等の品質。
(リアルワインガイド87+点、パーカー89点、タンザー88点)
「Guardiola de Font-Rubí」 というカヴァの聖地で、長年に渡ってカヴァ最高品質
のぶどうを栽培してきたピニョル家。わずか30ヘクタールの畑で収穫量が少ない
こともあって、そのぶどうは現地ワイナリーの間で 「幻のぶどう」 と言われ、高値
で取引されてきました。一方、スペイン最高のメルローと言われるスーパー・スパ
ニッシュワイン 「カウス・ルビス」 を擁するペネデスのトップワイナリー 「カン・ラ
フォルス・デルス・カウス」 のエステーベ家。2000年、両家は手を結び、共同で
このワイナリーを設立しました。栽培・醸造をトップレベルで一貫させた相乗効果
として誕生した、従来のものとは次元が異なるカヴァ。これぞ 「1+1=3」 。
“栽培に、秘訣とかノウハウとかはありません。すべてを完璧にやるだけ!”
“この世のものではないような、言葉では表現できないような 「幻想的なカヴァ」
を造りたい!” というジョセップ・ピニョルは、趣味も持たず余暇もとらず、
シーズン中は1日4時間睡眠でほとんどぶどう栽培のみに生きる求道者です。
「幻」 と言われるにはそれだけの理由があるのです。(あるHPより抜粋)
ヤバイです!
家の中が 「健康」 というキーワードに毒され始めています。

今回、
自身の不摂生が招いた結果とはいえ、半月以上も病が続くと情けないものです。
家ではめっきり “重篤な病人” 扱いです。そして、次から次へと食べ物や飲み物
の健康チェックが行なわれています。元々、肉しか食べないという偏食でもなく、
野菜や海藻、豆類中心の食生活は苦痛ではありませんが、さすがに何日も続くと、
調子が良くても、カラダの脂分が減って何となくカサカサしてきたような気分になる
ことは事実です。
昨日、
どうしてもカレーが食べたくなり、月に数回通っている 「インディアンカレー」 の
店先へ ・・・ しかし、さすがにここのカレーの刺激は弱っている胃に負担を掛け
そうでしたので、ぐっと我慢して何とか回避しました。そのまま帰宅するつもりでした
が、やはりちょっぴり刺激がほしいという気持ちは抑えられず、「船場カリー」 で
牛肉とご飯少なめなビーフネギカリーをオーダーしてしまいました。
今朝、
ちょっと心配だった例の胃の痛みや膨張感はなく、いつも以上に快調でした。
昼には、悪い癖で “今日は丼ものなら食べれるかも?” と独り言を言いつつ、
とあるお店へ ・・・ 親子丼をオーダー。鶏も卵もかなり久しぶりのような感覚です。
“折角やから、もうちょい旨い店に行けば良かった・・・” とちょっと後悔しつつも、
刑務所から何年かぶりにシャバに出てきて、飲食店にかけ込んだ人間のような
気分です。 ( まあ、そんな大層なもんやないし、そんな経験もないけど ・・・ )
というように、
少しずつ本来の不摂生な要素が顔をのぞかせている懲りないオッサンですが、
今回、病気になってから続けているものがあります。写真にも写っている 「青汁」
です。これまで、咽喉が渇くと子どもと同じように、意味なくジュースやコーヒーを
ガブ飲みしていたのですが、ミネラルウォーターと 「青汁」 を摂るようになりました。
思ったほど青臭さや飲み難さはなく、少しクセのある抹茶のような味ですんなり
飲めるのです。逆に、“ほんまにこんなんカラダにええのん?” という不信感すら
生まれます。まあ、疑うより信じて続けることが大事なのでしょうが ・・・ 。
現在、
飲み易い 「大麦若葉」 の青汁を飲んでいますが、「あしたば」 と 「ケール」 も
試してみようと思います。料理の素材選びや味付け、その料理に合うお酒を
セレクトするという仕事同様に、自身のカラダに合ったものをちゃんとカラダに
問い掛けながら見つけるという工程を自分なりに経てみようと思います。
『 北京オリンピック ( BEIJING 2008 ) 』 が無事?に開幕したようですね。
開会式での選手入場前セレモニーの内容に賛否両論が持ち上がり、あるテレビ
番組では、大国のおごりや共産主義の引き締めの為に使っているなどの見解を
述べられる方もおられました。常々、“スポーツを政治の道具にしてはならない!”
といった論調を示している方だけに、スポーツの祭典に対する感想を求められて
の発言としては、“どちら(誰)がスポーツに政治を持ち込んでいるのか?” と
逆に言いたくなる向きもあります。もう少し、スポーツと政治を素直に切り分けて
ポジティブな視点で観ることも大事ではないでしょうか ・・・ 。
確かに、今回の聖火リレーのあり方など一連の流れやプロセスを見る限り、
「平和の祭典」 と呼ぶには無理があることも事実ですが、政治的策略を除いた
見地で、中国がこのオリンピックを成功させたいという姿勢を示していることを
素直に評価することから始めないと、それこそ 「平和の祭典」 など、今の世の中、
どこにも生まれようのないものとなってしまうのではないでしょうか ・・・ 。
とにかく、私は開会式の制作指揮に当たった映画監督チャン・イーモウ氏の
センスの良さにまず拍手を送りたい気分です。今までのオリンピックには無かった
大胆かつ繊細なオリジナリティーが散りばめられた表現手法だったと感じました。
もちろん、中国という歴史ある大国の色濃いお国柄がベースにあることも事実
ですが、その長い歴史色と振興著しい現在色のセッションに心惹かれました。
( 今、日本に一番足りないもののような気がします )
羽織袴や着物を着て、刀まで携えて行進してほしいとは思いませんが、
自国の民族衣装やカラーを身にまとい行進している他国の人々を見ていると、
“なぜ、日本人は日本らしさを隠したり減らしたりしているのか?” という疑問に
ぶつかることがあります。季節を考えれば、暑苦しい他国ブランドのスーツを着る
より、浴衣地などの日本素材のオリジナルスーツで、胸ポケットに 「侍」 という
漢字の刺繍でもあしらえば、外国人選手から羨ましがられること間違いなしです。
( まあ、私のこの感覚は飛び過ぎてズレているかもしれませんが ・・・ )
要は、“日本らしさ” の新しい表現を高めなければ、一層、世界の人々から
“人マネの上手な国” という評価で終わってしまうような気がします。
もっと、積極的に! もっと、主体的に!! 自国の表現を ・・・
柔道女子48kg級の 谷亮子選手は3連覇ならず 銅メダル でした。
柔道男子60kg級の 平岡拓晃選手は あっさり 2回戦敗退 でした。
私は柔道の経験はありませんので、偉そうなことを言える立場ではありませんが、
特に、ここ十数年のヨーロッパやアメリカ大陸など他諸国の柔道を見ていると、
“これが柔道?” という内容の選手(国)が多く、オリンピックや世界選手権などの
大きな大会までもが、「ポイント制で勝つことを優先」 を師事するきらいがあり、
柔道着に始まり、畳、技の判定基準など大きく変わってきたように思います。
もちろん、多くの選手が公平に競技できるように、悪いところや不都合な要素を
改善すべき部分は改善することは大事だと思います。ただ、柔道がスポーツで
ある前に、「武道」 であるということをなぜ、日本はもっと強く言えなかったのか?
・・・ どうしても、そこに疑問というか、日本人としてイライラが芽生えます。
( 試合を見てると余計ににストレス溜まります! )
そんな中、日本人選手は本来の組み合って技を決めるという自分たちの柔道が
正しいと思いつつも、結局、“勝つため” に、外国人選手に合わせているような
流れが続いています。たぶん、このままでは柔道に魅力を感じない日本人が
増えるのではないでしょうか。今一度、日本は “どういう柔道を目指すのか” を
考えるべきではないでしょうか。
谷選手の負け(指導1つ分)も、試合時間残り1分を切って、組み手争いで指導を
受けたわけですが、日本人からすれば、不可思議な判定であったことは事実です。
ただ、過去にも、篠原選手の判定など不可思議で納得し難い判定があったことは
承知の事実です。今更、審判の顔を見ても遅い!ということになります。と、すれば、
なぜ谷選手は組まなかったのか? ・・・ 組めなかった!・・・ 確かにそうだったかも
しれませんが、それでは勝てませんよね。もっと言えば、自分の納得できる柔道
には近づかないのではないでしょうか ・・・
( 3位決定戦での柔道をなぜ初めからしなかったのか ・・・ )
簡単な話、組み手争いは放棄して相手に先に組み手を与える。というところから
勝機を見出すような創意工夫の柔道が日本には必要なのではないでしょうか?
5分しかない試合時間のほとんどを組み手争いに費やし、一向に技を掛け合う
という格好にはならない。やっている選手も見ている観客も何が楽しいのか???
本来の武道としての柔道、日本人が望むような柔道で、ブレずに血気盛んに
勝負できる新しい柔道家の出現を期待したいものです。
( ポイントを計算するより、自身の技を磨き、大技を仕掛けようぜ! )
■ 楽時々益 ■
“好きこそ物の上手なれ”
上手になれば好きになれるかも ・・・
いや、好きだから上手になりたい!
そんな素直な気持ちを持ち続けたい
上手になっても嫌いになれば意味がない
好き!楽しい!がベースにあってこそ
益もあるものである
第五大成丸
今日が最終日となった 「オーサカキング2008」 も
今年で5回を数える毎日放送主催のイベントですが、
すっかり大阪の夏の風物詩となった感があります。
今年は 「オーサカキンギョ」 とか ・・・
真夏の炎天下、
大阪城内で行われているイベントです。人がごった返す祭りやイベント、
暑くて逃げ場(休憩所)のない場所が苦手な私はもちろん行きません。
特に、今年は体調不良もあり、自宅待機のスペシャリティーになりそうです。
一方、嫁さんと末娘は、毎年(5回)皆勤賞です。( 信じられへん! )
ここ数年、
東京(お台場)でも同様に放送局が主催のイベントが毎年催されていますが、
いずれも、番組との連携を図った戦略が予想以上にイメージアップに繋がったり、
新たなキャラクターを生み出したりしている気がします。やはり、そのキーワードに
なっているのは、“足を運んで楽しいことに参加する” ということだろうと思います。
「上げ膳、据え膳」
という言葉がありますが、街で生活していると多少なりともそれに近い恩恵?を
受けているものです。交通機関の充実や商業施設での過剰なほどのサービス、
ネット社会の利便性向上などは、昔ほど自分が動かなくても状況が動かせる
という環境、また、動くにしても昔ほど労力や体力を使わなくて済むという意味では、
「上げ膳、据え膳」 の社会だと言えます。( ほんまにこのままでええのん? )
ただ、
その弊害として、生活習慣病の増加や環境汚染など、待ったなしで社会全体が
取り組まなければならない大きな課題が生まれていることを世の中のほとんどの
人が感じ始めています。その中で “自身が何をすべきか?” までは行かない
までも、それぞれが “何かできないか” という視点には近づいている気がします。
その一つの行動として、余暇の楽しみ方にエコロジーを組み入れた提案などが
注目を集め人気にもなっているのだと感じます。ここ最近、開催されている公共
や自治体のイベントでは、必ず 「ECO(エコ)」 が付いてきます的な流れですが、
どの年齢層でもそのことに関してはほとんど抵抗感がないように感じます。
日曜日の昼下がり、
わが家に居るのは私ひとりです。息子と上娘はバイト、嫁さんと末娘は嫁の実家
へ墓参りに ・・・ 。体調がイマイチの私はクーラーの効いたリビングでエコの話を
偉そうにブログに打ち込んでいるという、まあ、何とも理不尽でええかげんな話の
オッサンですよね。
もう少し日が陰ったら、久々に散歩に出て少し汗を掻いてみようと思います。
( まだフラフラするので無理はできませんが ・・・ )
早いもので、体調を崩してから10日が過ぎました。
今日は何とかPC前に座れましたので、病気の経過および
病気になって感じたことや発見したことををアップしたいと思います。
前回のブログアップは、流れというか ・・・ 勢いというか ・・・
22日、救急搬送され応急処置から外来病棟での検査と診察 ・・・
まるでツアー旅行に行って有名観光地を分刻みで見て回るような慌ただしい
体験をし、帰宅しても尚、気持ちが高揚したまま変なテンションでブログを
打ち込んでしまったかもしれません。しかし、そのテンションも数時間で終わり、
すぐにまた、あのシクシクとした痛みと不安が腹部全体を襲いました。
翌朝、
痛みは多少あるものの、前日のように我慢できないレベルは完全に脱して
いましたので、食事は抑え気味に摂ったものの、行動はいつもと同じように
開始しました。が、しかし、炎天下の大阪の街を2時間ほど歩き回っていると、
胃の膨張感とカラダの倦怠感が襲ってきました。即行で帰宅して検温すると
37.5°の熱があり、夕方には布団に入りました。そして夜、食事もできず痛みと
微熱が続きます。翌日も同じ状態が続き、少し精神的に疲れが出始めました。
26日、
変わらぬ病状に苛立ち始め、“薬が合ってないのかも ・・・” と勝手な素人診断で
その日は薬を服用するのをやめてました。が、結果、これが悪化させる一因だった
かもしれません。夜半過ぎ、またあの激痛と膨張感が襲ってきました。急いで処方
されていた頓服(痛み止め)を飲んだのですが、全く効く様子がありません。2時間
ほど我慢しましたが、改善する気配がありませんでしたので、またもや救急へ ・・・
救急では、
前回受けて週明けに結果が出る組織検査を待たないと大きな手当はできない
と告げられ、痛み止めの注射と点滴を打つだけの処置を ・・・ それでも少し、
カラダと気分が楽になり、何とか夜が明ける前に帰宅できました。それから2日間、
安静状態で自宅に篭っていました。気づけば、この一週間、酒はおろか、食事も
胃に負担の掛からない麺類や豆腐、消化の良い野菜を少量しか食べておらず、
たぶん記憶する限り、生まれて一番長くまじめに “摂生(節制)” した気がします。
( “食べなかった” というより “食べれなかった” という状態でしたが ・・・ )
29日、
微熱は続いていたものの、我慢できないほどの痛みはほぼ消え、自分で
クルマを運転して検査結果と問診を受けるために病院へ向かいました。悪性の
病巣がないかどうかの組織検査の結果は陰性でした。検査対象の部分に関しては
“大きな題はないでしょう!” という先生の見解でした。一応、ホッとしましたが、
腹痛の原因が見えないところにある可能性も含め、“CT検査をしておきましょう!”
ということで、31日に再検査となりました。
31日、
体調はこの2日でだいぶ改善されていました。(これは自己診断です)
病院に着くと直ぐに、検尿と採血に向かいました。ちなみに、この病院、カード型
の診察券を玄関口にある機械に挿入して受付表を取り出すところから始まり、
清算や薬の処方なども患者さん自身が機械を操作して済ませるセルフ方式に
なっています。私はまったくの機械音痴ではありませんが、それでも最初、少し
戸惑いました。当然ですが、病院ということでお年寄りの方も多いのですが、
意外と使いこなしている人が多いことに私は驚きました。
CT検査に向かいます。
半ドーム型の機械が前後に動きながら撮影をし、患部を輪切りに投影することで
臓器等に異常がないかを診る検査ですが、血管に 「ヨード造影剤」 という液体を
投与して尿管や胆管を造影することで、より正確な診断ができるということです。
造影剤を注入すると、カラダが異常に熱くなります。事前に説明はあったものの、
不安になるほど熱くなります。“吐き気や呼吸がしにくいようでしたら遠慮せずに
おっしゃってくださいね” と優しく言ってくれるのですが、実際、そうなったらどう
処置するのだろうか?といったことを短い時間の中で想像しながら私は仰向けに
なったままジッとして検査を受け終えました。検査結果は5日の予定です。
たぶん、何も問題はなく大丈夫ですよ!という結果になるような気がします。
やはり、原因はストレスなのか ・・・ ? ( これも自己診断ですが ・・・ )
今現在、
まだ体力は普段の半分程度しかないと思いますが、最初の一週間に比べれば
食事も食べられるようになってきましたので、“もう大丈夫!” という気分です。
まず動けるカラダに戻すことが先決ですが、今回の経験で気づいたことが多々
あります。その一つとして、これは私の仕事にも大きく関わることなのですが、
“「うまい!」 や 「美味しいもの」 は個々の味覚によって違う” ということは常々
周囲にも伝えてきたことなのですが、“同じ人間でも健康時にうまいと感じたものが
病気の時にはそうは感じないものである。逆に、健康な時には見向きもしなかった
ものが美味しいと感じることすらある。” と付け加えておきたいと思います。
そして、
健康な人に対する商品や食材あるいは味の訴求提案は街に溢れていることに
気づきます。逆に、病に伏している人への目線がいかに弱いかです。個人的に
ビジネスとして考える気はありませんが、カラダに良い食材やバランスを考えた
料理などなどといったレベルで収めず、ベビーフーズと同様に用途(病状)に応じた
「美味しい病中食」 を開発して、一食ずつのレトルトや冷食として市販されても
良いのではないかと真剣に感じました。( 何を食べればよいのか悩みました )
【 例:胃腸障害と微熱で食欲のない方向けの 「新発売!美味しい○○○」 】
今後は、
自分の体力や内臓を過信せず、歳相応に “摂生(節制)” したいと思います。
また、ストレスを溜めず前向きに考え行動するように頭も改善したいと思います。
そして、
心配して頂いた皆様にこの場を借りて、一度区切りとしてお礼申し上げます。
“心配をお掛けして申し訳ありません。ありがとうございました!”









