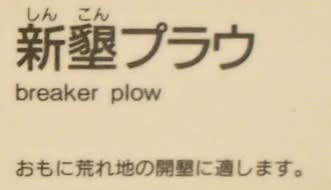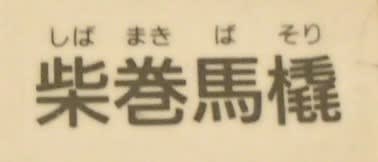帯広百年記念館。帯広市字緑ヶ丘。
2022年6月11日(土)。
帯広百年記念館のある緑ヶ丘公園は十勝監獄(帯広刑務所)の跡地である。
十勝監獄。
1893年(明治26年)3月 : 北海道集治監釧路分監帯広外役所として開設。
1895年(明治28年)4月 : 北海道集治監十勝分監として開庁。
1903年(明治36年)4月 : 十勝監獄として独立。
1922年(大正11年)10月 : 十勝刑務所へ改称。
1924年(大正13年)4月 : 釧路刑務所に統合し、釧路刑務所帯広支所となる。
1936年(昭和11年)4月 : 網走刑務所の所管となり、網走刑務所帯広刑務支所となる。
1939年(昭和14年)11月 : 帯広少年刑務所として再び独立。
1943年(昭和18年)8月 : 官制改正により帯広刑務所へ改称。再び成人受刑者の収容施設となる。
1951年(昭和26年)3月 : 士幌農場開設。
1976年(昭和51年)10月 : 帯広市緑ケ丘三番地から帯広市別府町南13-33へ移転。
1977年(昭和52年)4月 : 収容区分の改正により、B級収容施設となる。
1981年(昭和56年)6月 : 別府農場開設。
1994年(平成6年)11月 : 士幌農場廃止。
2007年(平成19年)4月1日 : 釧路刑務支所(旧・釧路刑務所)の所管を開始。

帯広市は開拓使による開拓・開墾ではなかった。帯広には、農業開拓の先駆としてすでに晩成社が入植していたが、パツタの異常発生などにより大打撃を受けていた。これを再興、拡大することが、北海道集治監十勝分監の使命であった。
帯広市街の形成には十勝分監の果たした役割が大きい。分監開庁二年前に、戸数一四、人口九一であった下帯広村が、開庁二年後には、戸数四三二、人口一、九二六になる〉ことからも、確かめられる。ただし、図7にみるように、分監と市街は連担しなかった。理由は、晩成社の入植後、市街地区画と諸官庁の設置がなされ、分監建設がそののちになったためである。
交通に関しては旧十勝監獄の受刑者が大通を整備し、今の市街地を形成したと評価されている。

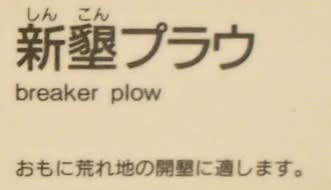
新墾プラウは、最も大型の撥土板プラウで、もっぱら荒地の開墾に用いた。先端には鋭利ななた(犂刀)を備え、土の反転を良くするため撥土板も大きく、曲面を呈していて、普通2頭または3頭の馬で曳く。プラウは、洋犂とも書き、日本古来の和犂にかわって明治期に北海道に普及した畜力耕具である。
十勝の開拓と馬。
十勝の開拓の歴史は、馬の歴史と言っても過言ではない。いわゆる「ドサンコ」と称される馬は、主に開拓の際、抜根などの厳しい作業に使われた。また、ドサンコは駄載力に優れていたので、荷物の運搬にも大きく貢献した。入植当時の住居は、土間をはさんで馬小屋と寝室が一緒になっており、文字どおり人馬一体の生活であった。
その後、開拓が進みプラウ、ハロー、カルチベータが導入されるようになると、駄載力より農具を曳く輓曳力(ばんえいりょく)が必要とされ、農耕馬の大型化が要求されるようになり、トロッター種とペルシュロン種による交配が積極的に進められた。この交雑種は「農トロ」と称され、十勝の開拓に大いに共用されました。
明治43年、音更村に開設された十勝種馬牧場は、フランスからペルシュロン種の種馬「イレネー号」を導入した。昭和3年に亡くなるまでの間、1074頭に種付けするという旺盛な繁殖力を発揮し、その功績を称えて建造された銅像が、帯広競馬場内に鎮座している。
十勝の馬の飼養頭数は、農耕馬だけでなく軍馬の生産振興も加わり、十勝国産牛馬組合が誕生した明治39年には13232頭であったたが、その後も増加の一途をたどり、大正3年には3万頭を超えた。
第二次世界大戦で軍用に徴用されたため一時減少したが、戦後は復興に向けた農耕の主力として活躍し、ピークの昭和31年には65070頭に達し、多くの農家で2~3頭の馬が飼育されていた。
その後、トラクターの普及に伴い急速に減少し、ばんえい競馬や肉用、乗用など、平成13(2001)年時点で3361頭となっている(平成14以降統計はとられていない)。
明治の終わり頃になると、馬の価値や力くらべのため、競争が行われるようになった。明治44年11月、十勝国産馬組合は競馬場を建設し、十勝競馬を開催し、ばんえい競馬が始まった。

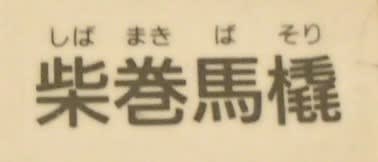

柴巻馬橇(しばまきばそり)。
馬橇とは馬などのうしろにそりをつけ、人や荷物を運搬する交通の手段である。
明治初期、北海道開拓使は札幌に全国でも初めてロシアから馬橇の製作技術を導入した。これは主な産業技術をアメリカから導入していた当時としては異例であり、ウラジオストクやサハリンのコルサコフを視察して冬の交通・運搬手段として馬橇が便利なことを知った開拓長官黒田清隆の考えによるものだった。
ロシア型馬橇の製作技術の特色は、太い角材や若木(細い丸太)を蒸籠(せいろう)で蒸して曲げる技術にある。曲物(まげもの)のような薄い板や細い木を曲げる技術は日本にもあったが、馬橇のような太い木材を曲げる技術はなく、ロシア人の直接指導により初めて修得した。
ロシア型馬橇を基本型に、その後札幌・青森・函館3型式の馬橇が誕生した。特にロシア型馬橇の直系といわれる札幌型の馬橇(柴巻馬橇)は、初期のロシア型に比べると台木(だいぎ)が太く、先端の曲げもより大きく見栄えがいいのが特徴で、橇も全体に大きく、丈夫になった。
柴巻馬橇(札幌型、石狩型ともいう)は、明治20年代(1880年代末頃)に、馬橇の製造技術を習得した職人が独立し、北海道の各地で馬車や馬橇の製造業を営むようになって製造された。ロシア型を改良し、細い丸太状の木材である柴木を加工して巻き、橇を補強した。柴巻馬橇は開拓地の拡大にともなって全道に普及し、北海道の多くの場所では単に「馬橇」と言った場合は柴巻馬橇を示し、柴巻馬橇は北海道的な風物とされる。



農耕馬用器具。再墾プラウ。装輪プラウ。
プラウ(英: plough、plow)は、種まきや苗の植え付けに備えて最初に土壌を耕起する農具である。大正期にドイツから輸入した双耕プラウを、深耕用ワンボトムに改良したものが装輪プラウである。畜力1頭曳き、車輪により舵(かじ)を取る労力が軽減され、根菜栽培の増加で普及した。耕深・耕幅や車輪高調整のレバーが付く。

農耕馬用器具。方形ハロー。
ハロー(馬鍬まぐわ、英: harrow)は、牛・馬などの家畜やトラクターの力を使い「土の破砕、ならし(代掻き)」を行う農具である。明治初期にプラウなどと共に輸入され普及した代表的畜力農具。プラウ耕起の後に砕土と整地するのに使う。方形木枠に4角形の釘をネジで固定、方形ハローまたは爪ハローと言う。

農耕馬用器具。三畦カルチベーター。
カルチベーター(畦立機・中耕除草機、英:cultivator)は、作物の種をまいたあとに表土を砕いてやわらかくするもので、家畜の力を使った「中耕作業機」であるが、同時に除草の効果もあるので「中耕除草機」ともよばれる。
中耕爪(づめ)、除草・培土刃を雑草の程度にあわせて調整し、爪刃の引き抜き作用、切断作用、埋没作用の組合せによって条間の除草を行う。
畜力用1条5本爪カルチベーターが1870年(明治3)プラウとともにアメリカから輸入され、北海道の畑作地帯で利用されていたが、昭和20年代に急速に普及した府県では、畑作物の中耕除草以外に、中耕爪と除草刃の調整によって、ムギの簡易整地や土入れ、ムギの踏圧(とうあつ)といも(ジャガイモ)の掘り取りなど広範囲に使用されてきた。
爪の種類を変えると、土を寄せる「培土機(ばいどき)」としても利用されるなど非常に重宝な農機具であった。
【カルチベータ物語】第2回 畜力3畦カルチベータ
農業ビジネス 2003年05月01日 農学博士 村井信仁。
3畦カルチベータは、大正12年(1923年)に十勝川西村(現在の帯広市)の農家である中田耕平が考案し、これを父親の玉一郎が実用化したのが始まりとされている。
大正12年と言うと、第一次大戦の豆景気で農家が潤い、自立を始めていた時期である。十勝には甜菜製糖企業が進出し、2工場が操業を開始して、大規模畑作農業の基盤を整備し始めていた。ドイツやデンマークから招聘した模範農家も実績を挙げつつあり、ここから実質的な洋式農業が始まった。規模が拡大していたことから、農家は高能率機械を要望し、一方、開墾から時を経て畑は熟畑化しており、大型機械が抵抗なく使える時代を迎えていた。
3畦カルチベータは爆発的な売れ行きで全道に広がり、やがて特例を除いて1畦用カルチベータは姿を消した。早くも開発から5年後の昭和3年(1928年)には、北海道農業試験場が比較審査を行い、その成績書を発表している。中田式、川崎式、黒田式が審査されたが、これを機に改良は一段と進み、高水準化したと言われている。
畜力の場合、作業速度を調節することができないので、除草効果を高めるためには爪の数を多くする、あるいは爪の種類を多くして条件別に対応しなければならないなど、現在のカルチベータより多彩な内容であった。
爪の数は、一般的には5本が原則であった。畦幅の広い作物に稀に6本、あるいは7本装着されることもあったが、これは例外と考えてよいであろう。あまり爪の数を多くすると土塊や残稈が爪の間に詰まって正常な作業を妨げるので、好ましいものではなかったと思われる。
代表的な爪の種類を作用で分類すると、中耕爪、除草爪、護葉爪、培土板であった。それぞれ用途によってさらに何種類かに分化するが、最も多く使われた中耕爪は俗に細刃と言われる幅の狭いものであった。上下に刃が付いており、刃先が摩耗すると上下を付け換えた。
畦幅が広い、あるいは、土の動きを大きくする必要がある場合は、若干幅の広いものを用いた。猫足刃と呼ばれる小さな三角状の刃の付いたものも中耕爪として用いられたが、これは粘質土で比較的土壌が硬い圃場用のものであった。先が鋭く尖っており、緩い角度が付けられているので刺さりがよく、抵抗が少ないのが特長であった。
除草爪は表層を浅く削る形態のもので、三角刃、あるいは、魚のかすべ(エイ)状を呈していることからかすべ刃とも呼ばれた。幅広く削り根を切断するところから、機体の中央に装着するのが通例であった。
護葉爪は株際を施工するもので、削った土が作物にかからないように畦間に土を寄せる形態になっていた。木の葉の形に似ているので、木の葉刃とも呼ばれ、左ひねり、右ひねりの左右対であった。普通は作物があまり生育していない時期に使用されたが、作物が大きくなって小培土が必要になった場合は、取付けを逆にして土を作物の根際に寄せ、小培土を行った。培土による覆土も除草技術の一つであり、培土をしても差し支えない作物には有力な株間除草の手法であった。
培土板は、バレイショなどに使われる大培土用と、最終除草作業時に畦の中央を開溝するように左右に土を寄せて雑草を制圧し、畦間の排水を良好にする小培土用の2種類があった。
いずれにしても、畜力の場合はトラクタのようなけん引力はないので、各種の爪を組み合わせ、工程を多くして対応せざるを得なかった。このため技術力を必要とし、農家間に大きな能力差が認められた。
開発の背景
3畦カルチベータが開発された大正12年頃になると、北海道と言えども鋼材が入手しやすくなっていた。機械工作技術も発達し、刃物鍛冶屋が機械鍛冶屋としての体裁を整え、著名なプラウメーカーが続出した。
カルチベータも木台から鉄製へと改造され、爪の貫入角調節が自在に行えるようになっていた。定規車の高さ調節も任意に調節できるようになり、高水準化した。機体の軽量化にも成功すれば、次は当然のこととして多畦化を図り、高能率化を狙った。
3畦カルチベータを考案した中田耕平は、約25haの農地を耕作する大規模農家であった。1戸あたりの標準経営面積が5haと言われていた時代に、その5戸分の農地を所有している大規模農家は、当時としても珍しかった。
その頃は2戸分、つまり10ha所有すれば、家族労働力だけで対応するのは困難であり、農耕シーズンになると東北地方から労働力を求め、住み込ませたと言われる。大正後期から甜菜を作付けできるようになったが、主体は豆類とコーン類であった。除草に多大の労働力を必要としたので、その省力化には大規模農家である程腐心したであろう。
1畦用カルチベータが鉄製になりコンパクトになれば、これを3つ揃えてけん引できないかと考えるのは当然の成り行きであったと言える。また、大正時代には耕馬の改良が進んでいたので、けん引力に不足はなく、1畦用カルチベータけん引の調教も充分に行われていた。こうしたことから、耕平は1畦用カルチベータを横桁で3台括り付けることを思い付いたようである。
何度か手直しをしたと伝えられているが、ついに3畦除草に成功し、これが周辺の農家に注目された。これを見た父親の玉一郎が、3畦除草器の名称で1925年に実用新案登録を行い、この製造販売に取り組むようになった。これを機に川崎式、黒田式も開発され、3畦カルチベータ時代を迎えた。
3畦カルチベータの功績
当時の農家は除草のために「朝暗き内より起き出でて、夕べは星を抱いて帰る」という状態が連日続いていた。男衆が1畦用カルチベータを操作し、女衆はホーによる手取り除草である。猫の手も借りたいとは、まさにこのことであった。
1畦用カルチベータの作業能率は、慣れた人でも時間当たり15a程度であったと言われる。これが3畦カルチベータになると、枕地4行のロスタイムがなくなった分、53aと一気に約3.5倍の能率に達した。しかも、1畦ずつ処理するのとは異なり、3畦同時作業であるので機体の振れが少なくなり、作業精度が向上した。その分手取り除草の手間が省け、女衆にも好評であったと言われる。こうなると、もう言うことなしである。
大正時代に入って経営規模が拡大すると、除草の労働負担が重荷になり、その省力化が大きな課題となった。それに伴い、ようやくカルチベータ本来の仕事が注目されるようになった。鋼材が不足し、木台で構成されていたカルチベータも、遅れ馳せながら鉄製になり、同時に爪はもちろんのこと各部に改良が加えられ、機械らしい体裁を整えた。
北海道の開拓農家は、第一次大戦による豆景気、バレイショ澱粉景気で潤い、力を付けていた。これを機に、甜菜製糖工場をはじめとする農産加工も活発になった。
その勢いに乗じ、日本風の3畦カルチベータが開発されたのである。わが国はどちらかと言えば、農耕民族で工業技術力には欠けていると言われるが、そうとは限らない。日本刀に代表されるように、刃物鍛冶的な技術には長けている。それが機械鍛冶に昇華して、欧米を凌ぐ3畦カルチベータに形を整えたことは称賛に値しよう。
この3畦カルチベータの功績は、単に除草を省力化したことに留まらなかった。精密中耕除草が作物の生育、収量に関係して高位生産をもたらしたのである。同時期に製糖工場が欧米から新しい防除機を導入し普及に努めていたので、その相乗作用とも言えるが、いずれにしろ3畦カルチベータが高位生産の先駆的役割を果たしたことは疑いようがない。
大正末期から昭和初期にかけては、欧米から導入された技術をようやく掌中にした時期と言えよう。心土耕プラウも開発され、自立した畜力機械化時代の幕開けとなった。
この3畦カルチベータの技術は、第二次大戦後の動力化時代にも引き継がれた。日本風のホイールトラクタ用のカルチベータが開発されたのは、昭和35年(1960年)頃からである。それまでは専ら畜力用の3畦カルチベータをティラ(tiller,耕耘機)に取り付け、これが大いに活躍していた。
ティラは耕馬に比較すると、肩を振ることなく真っ直ぐ走行できるので、株際まで爪を寄せて作業ができる。その分、手取りの株間除草を容易にすることができ、動力化に弾みをつけた。また、ティラは作業速度をある程度任意に変えることができ、条件別に作業速度を変えることで、より除草効果が高まった。
ティラを大型にし、けん引力を増大させると、中耕爪を深く入れることが可能であり、冷害=湿害を回避する技術としても注目された。こうした日本らしいきめ細かい技術が、やがてトラクタ用へと引き継がれた。