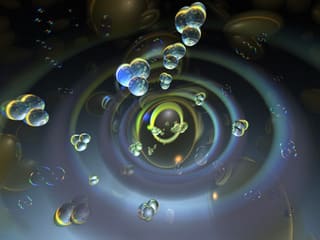クォーク(quark)とは、ハドロンを構成する素粒子である。実験によるとそれ以上の内部構造があることを示唆する有意な結果が無いため、現在、クォークは素粒子であるとされている。
クォークという名称は、モデルの提唱者の一人マレー・ゲルマンにより、ジェイムズ・ジョイスの小説『フィネガンズ・ウェイク』中の鳥の鳴き声「quark」から取って付けられた。
我々が生活する通常の温度・密度ではハドロンの中にクォークは閉じ込められており、単独で取り出すことは不可能であるとされる。NASAの発表によると、天体が超新星爆発を起こした後に、クォークが裸の状態で存在する「クォーク星」と呼ぶべきものが発見されたとのことである。
クォークは、1対ずつ3つの階層に分類され、それぞれ「アップ、ダウン」、「チャーム、ストレンジ」、「トップ、ボトム」と名付けられている。また、「色荷(カラー)」と呼ばれる量子数を持ち、他の粒子同様逆の電荷を持つ反クォークが存在する。
クォークという名称は、モデルの提唱者の一人マレー・ゲルマンにより、ジェイムズ・ジョイスの小説『フィネガンズ・ウェイク』中の鳥の鳴き声「quark」から取って付けられた。
我々が生活する通常の温度・密度ではハドロンの中にクォークは閉じ込められており、単独で取り出すことは不可能であるとされる。NASAの発表によると、天体が超新星爆発を起こした後に、クォークが裸の状態で存在する「クォーク星」と呼ぶべきものが発見されたとのことである。
クォークは、1対ずつ3つの階層に分類され、それぞれ「アップ、ダウン」、「チャーム、ストレンジ」、「トップ、ボトム」と名付けられている。また、「色荷(カラー)」と呼ばれる量子数を持ち、他の粒子同様逆の電荷を持つ反クォークが存在する。