徳川四天王 井伊兵部少輔直政
赤備えの新参譜代
白石一郎【作家】
苦難の生い立ち
地味な人物である。名声のわりにきらびやかな逸話に乏しい。戦功や実績にも特にこれといった華々しさがない。それでいて徳川家創業期の四天王の一人と呼ばれ、譜代筆頭の高禄を喰み、徳川全軍の先鋒役をつとめたのが、井伊直政である。華々しい実績やきらびやかな逸話を史上に残さず、しかも現実に栄達をとげた人物は、後世の者にとってイメージを描きにくい。物語の主役にはなれず、副人物として登場させると、それなりのリアリティを発揮する。場合によっては意外な精彩を放つこともある。 井伊直政とは、そんな人物である。酒井忠次・本多忠勝・榊原康政の三人に直政を加えて四天王と呼ばれたのだが、四人のなかでは最も個性の輝きに欠ける。それでいて最高の栄達を遂げたところに、直政という人物の個性があったのであろう。
主の家康はかつて息子秀忠の夫人に手紙を与え、その文中で直政を評し、
「平常は言葉少なく、気重く見えるが、腹が決まったらすぐ実行に移す。もしわしが何か考えちがいをし、評議ちがいをして、それがまずい結果になると判断すると、他人のいないところで意見してくれる。それゆえ何事もまず彼に内相談するようになった」
と、告げているそうだ
(『物語藩史・彦根藩』西田集平氏に拠る)。
このへんに、井伊直政の栄達の秘密が要約されていると考えてよかろう。
もっとも四天王のなかで、直政の家柄は群を抜いていた。筋目の正しさでは主家徳川家より上であったろう。井伊家は名門藤原氏に出ている。藤原良門の流れをひき、一条天皇のころ遠江守に任じられた藤原共資の子共保を始祖としている。井伊直政はその共保から二十四代目に当たった。永禄四年(一五六一)先祖代々の領地である井伊谷に生まれている。幼名は虎榜。
曾祖父のころから井伊家は今川氏の勢力に呑まれて臣従し、直政の祖父は桶狭間の合戦で討死にし、父の直親は徳川家に内通した疑いで今川氏真のために謀殺された。このとき直政も殺されようとしたが、今川家の臣新野左馬前の助命嘆願で、ようやく命だけほとりとめたという。幼い直政は、しばらく恩人の左馬助の家で養われたらしい。それでもまだ命を狙われ、左馬助の叔父である浄土寺の僧に預けられて、出家したという。今川家没落のあとは三河のさる寺へ逃れ、それから遠州浜松へ移り、のち生母の再嫁した松下家に養われて、いちじは松下姓を名乗っていた……。
以上は『寛政重修諸家譜』『野史』などに見られる井伊直政の幼年期であるが、これによると、たいへんな苦難の生い立ちである。早く父を失い、所領を奪われ生家を離れて他家に養われた点では、主人の徳川家康と共通した幼年期といえる。家康の直政に対する好適は、よく似た体験への同情もあったのではないかと思えるのである。
井伊の赤備え
直政と家康との出会いは天正三年(一五七五)二月十五日のことで、家康はそのとき浜松の城下で鷹狩りをしていた。路傍で十五歳の直政を見出したというが、おそらく誰かがそのように仕組んだのであろう。家康は直哉の素姓を聞くと、「汝はわがために命を落せしものの子なり。われ報いずんばあるべからず」 と言い、さっそく召し抱えて、父祖伝来の地遠江の井伊谷を与えたという。直政の父直親が徳川家に内通した疑いで、今川氏のために殺された事情を、家康はよく知っていたのである。内通の疑いは、ある程度事実であったのかもしれない。
徳川家に仕えてからの直政は、とんとん拍子といってよい出頭ぶりである。四天王のうち、他の三人は本来の三河譜代で、それぞれ豪勇を謳われた武将だが、直哉は新参譜代であるにもかかわらず、いつの間にか三人に伍し、肩を並べる存在となった。四天王の中では最も若い。最年長の酒井忠次とは三十四歳のひらきがある。本多忠勝・榊原康政の二人とも、十三歳の年齢のひらきがあった。戦功についてはとくにこれといって際立った話もない。
天正四年の武田勝頼との対陣が直政の初陣である。同九年の高天神城攻めにも参加している。どちらも、……軍功あり。といったところで、特に華々しい逸話はない。それでも着々と禄を増し、その存在は注目されてゆく。虎松と称した直政はこの間に万千代と改名し、さらに元服して直政と名乗っていた。家康の甲斐攻略の過程で直政の存在は、着々とクローズアップされてゆくのである。
甲斐攻略の成ったあと、直政には武田家旧臣のうち一条衆・山縣衆・土屋衆など七十四名と関東武者四十三人、合計して百十七人が頂けられ、所領も四万石相当の大身となった。しかも、家康は武田二十四将の一人として武名も高い山県昌景の、『赤備え』を直政に継承させている。これは鎧具足から旗・差物・鞍・鐙・鞭に至るまで、すべてを赤一色に染めたもので、戦場で目立つことはこの上もない。武田軍中で山県昌景がこれを常用し、その一隊は武田軍の先鋒をつとめていた。これを直政に許すことによって、井伊家の徳川軍に於ける先鋒役が決まったようなものである。
……井伊の赤備え……
と後世に喧伝される端緒がこのときであった。ちなみに井伊家では、これを末代までの名誉とし、新参の奉公人があれば武具奉行が命じて鎧具足を赤色にさせ、具足櫃に百石につき金二十両を納めて城中の庫に保管したので、同家ではいざというとき、武具が欠けることはなかったという。またこのとき、直政は兵部少輔に昇り、徳川家の重臣にふさわしい名誉を与えられている。こうした家康の直政に対する破格の好適は、とうぜん多少の嫉妬をも家中に呼んだであろう。宮腹と直故の間に衆道の関係を類推するむきもないではないが、やはりここでは井伊家の家柄が高く評価されたと考えてよかろう。
この当時の直政について、ちょっとおもしろい逸話がある。武田の旧臣たちから諌言される話である。
若い直政が鋭気に満ち、あまりに血気さかんなので、家来たちが連署で次のように書面で注意したという。
『人には必ず向ふざすと申すことを思い設けたるが然るべく候。 臣らが前の主君の事を申すもいかがなれども、
信玄は若きときより一ツとして心より善事はなき人にて候えども、
常に越後の謙信を以て向ふざすとして
謙信にまさるべしとつとめはげまれ候ひき。されば信玄一生の間、
手をおろしたる大事の合戦五度に及び候へども、
大なる敗北はせられず候。殿にも本多中務大輔忠勝を以て、
向ふざすとして勉めて劣らじとはげみ給ひ候へかし。
いにしへより進まず退かざる良将と申すは
中書(ちゅうしょ)相かなひて覚えたりと書たりけり。
(『常山紀談』)
ちょっと長い引用になったが、当時の直政のようすがしのばれておもしろい。右の文中の「向ふざす」というのは現代風に解釈すれば「ライヴァル」といった意味であろうか。そのライヴァルに本多忠勝を擬せとすすめているのも、肯ける話である。
忠勝は家康の旗本先手侍大将で、三河武士の代表と目され、
「家康に過ぎたるものは二つあり、唐の頭に本多平八」
と、もてはやされた勇将であった。当時の代表と目され、直政には恰好の目標となったであろう。
旗本先鋒役
徳川家の軍団は三股編成だった。いわゆる三備の軍制といわれるものである。
家老(組頭)二人がそれぞれ東西の軍団を掌握して両翼となり、家康が直属の旗本団を率いて中心を占める。この旗本団の先鋒役をつとめたのが、直政である。
徳川家の戦法は「突き掛り」といい、敵陣に向かってがむしゃらに突進し、相手の陣形を混乱させて勝機をつかむという方法だった。その突き掛りの先頭に立ったのが直政の一隊である。これは井伊家の家襲となり、江戸時代にも引きつがれ、何ごとによらず譜代大名の先頭に立つのが慣例となった。江戸城内の式典でも井伊家が先頭に立ち、ために譜代大名の筆頭と目されるようになるのである。
この先鋒役の件に関しては、直政にひとつの逸話がある。小牧・長久手のいくさをへて、家康が秀吉と和睦し、天正十八年二月、小田原城攻めに参加したときのこと。
家康は榊原康政に先鋒を命じ、井伊直政を手もとにとどめた。いつもなら先鋒を望む直政であるのに、この時はおとなしく命令に従い、不服もいわない。ところが小田原の陣中で、直政は秀吉の周辺に人数の少ない折を見すかし、家康に向かって、
・・・唯今取り囲みて討取るべき時に候・・・
と、さかんに秀吉討取りを進言した。家康は笑って取り合わない。すると直政は、
・・・さらば先陣たらん・・・
それならば先鋒に戻してくれと言い張った、というのである。これを直政の一種のゼスチュアと見るかどうかは別として、主家思い、家康思いの一徹さは、直政の生涯を貫いている。
たとえば、これよりさきの天正十四年、秀吉と家康の間に和睦がととのい、家康上洛の条件として、秀吉が母の大政所を人質として岡崎へ送ってきたことがある。井伊直政は大政所の警護役を命じられた。家康の命にかかわる大切な人質である。上洛した家康は秀吉から、
「わが母の奉行に誰を選ばれたか」と訊ねられ、「井伊兵部少輔直政と申す者でござる」 と答えたところ、秀吉はうなずいて、「聞いた名の武士じゃ。一昨年長久手合戦のとき、われらの陣中で赤鬼と呼んでいた男であろう。いったい年齢はいくつぞ」「当年二十六歳に相なります」「二十六?」と秀吉はおどろき、「家康どのは名誉のお人である。このたびわが母を預けたのは貴殿の命の代償である。いわば自分の命の番人に二十六歳の莟(つぼみ)花のような侍大将をつけられたとは、よき侍を幾人も持たものよ」といい、さっそく飛脚をつかわして、岡崎から直政に同道を命じて、母の大政所を呼び寄せた。上洛した直裁は秀吉に謁して侍従に任ぜられ、一日、召されて秀吉の饗応を受けた。その席に石川数正が同席していた。
かつて徳川家の組頭をつとめながら、天正十三年出奔して秀吉の竃下に参じた男である。直政は席上、石川数正から面をそむけて物もいわない。秀吉が自ら茶を点じて振舞ったとき、直政はたまりかねたように傍の人に向かい、秀吉に聞えよがしに、
「ここに同席した石川数正は、譜代相伝の主君にそむき、殿下に従った大臆病の男でござる。拙者はこの男と肩を並べ、膝を組むことはごめんこうむりたい」 と言ってのけ、同席の人々を驚かした、というのである。こんな逸話に家康思いの直政の一徹さがにじみ出ている。
さらにこのとき、大政所が秀吉のもとへ戻って、苦情を言ったらしい。 「あの井伊直政という者は、まことに憎い男です。私の居る所ではいつも四方に萱を積み重ね、すわといえば放火して私を焼き殺す支度をしておりました。思いだしても腹が立ちます」
聞いた秀吉はかえって感心し、
「あっぱれ徳川殿はよい人を持ったものかな。直哉の致し方は真の忠臣である」
と褒称したそうだ。
『名将言行録』『責両者草』などの伝える話だが、これらの話からは、一途に家康のために尽くそうとする直政の態度をしのぶことができる。
赤鬼の覇気
家康が秀吉の命令で関東へ転封したのは、天正十八年八月一日。六力国と飛び地を合わせて二百五十万石という大領主となった。
このとき井伊直政は上野国箕輪で十二万石を家康から与えられ、文字通り譜代直臣のトップに躍り出ている。
本多忠勝が上総で十万石、榊原康政は上野国館林で十万石、すでに隠居した酒井忠次の場合は、その子に三万石が与えられたにすぎなかった。この頃では四天王と呼ぶ言葉はすたれ、忠次をのぞいた直政・忠勝・庶政を称して、『三人衆』 と世間は呼ぶようになっていた。井伊直政はその三人衆の中で筆頭の位置を占めたわけである。この三人が徳川家の軍制、民制の中心となったことはもちろんである。
本多正信などのいわゆる「能吏」も指頭してくるが、世はまだ武勇が何よりも尊ばれる戦国であった。
井伊直政には特にきわ立った武功譚がないとはいえ、それは恵勝や庶政に比較しての話で、この人物も戦国の猛将であったことに変わりはない。単なる家柄のよさや家康の寵愛だけで譜代筆頭に擬せられるような時代ではなかった。個人的な功名噺は別としても、直政の猛勇をしのばせる逸話なら、各種の記録に散見している。
ここでは慶長五年の関ケ原役のうちから、直政の逸話をいくつか拾ってみよう。
家康が会津の上杉景勝を討つべく七月半ばに江戸を発ち、二十五日に下野の小山に着いたところで、石田三成の挙兵の報に接した。さっそく諸臣を集めて協議したところ、本多正信が、
「諸大名はこのたびの東征に従ってきたものの、妻子はすべて大坂に置いています。このさい遠慮しないわけにはゆかないでしょう。まず早く軍を止め、諸大名に暇をつかわし、それぞれの所領を安堵せしめ、箱根の嶮を境として譜代直臣を集めて守らせるほかにないと思います」
と、進言した。それを聞いた直政が大いに反対して、
「天の与うるを取らざれば、反ってその災いを受くと申すなり。いま、時すでに至れり。早く大兵を起し、旗を畿内に進め、天下を一に定めらるべし。今の時にあたり、天下誰か我に敵する者あらん。且つ正信の策に従われなば、北条氏と同じく社稜を亡ぼし給うに至らん」
と言い、席を蹴って退座したので、家康もその議に従ったという。これが実話であるかどうかは別として、能吏慎重型の本多正信と武断蔵突進型の直政の処世の違いを、中々うまく表現した挿話であろう。
実戦に際しても、いかにもベテランらしいと思わせる直政の逸話がある。
関ケ原決戦の朝は霧が深くて、敵味方の所在がしかとは判らなかった。鉄砲弾だけがしきりに飛んでくる。黒田長政の家来で大沼寺孫九郎という者が物見のために走り出て、しきりに敵の方角を見ていたところ、同じ所に赤具足の騎馬武者が一人でやってきた。
その武者は悠然とした態度で、手綱をゆらりと握り、いかにも物静かに敵陣を眺めていたが、「これはすぐにも決戦となろう」 と独り言をつぶやいた。孫九郎が武者の側に寄ってその理由を聞くと、「敵と申す者は間近になるほど足軽どもがうろたえ、玉を筒の中へよく入れぬものじゃ。だから撃つ玉に勢いがなく、味方の足もとへころころ落ちてくる。こんなときは決戦が間近いと知れ」 と教えて走り去った。あとで間けば、この武者が井伊直政その人であったというのだ。
これなどは何となくリアリティを感じさせる挿話である。いかにも歴戦の勇士という印象がつよい。
この関ケ原では直政は家康の四男松平下野守忠吉を同道していた。まだ若い忠吉を家康から預けられていたのだろう。
いざ合戦となった時、若い忠吉は気がはやるのか、真っ先に飛び出そうとして局囲の家来たちの制止をきかない。馬の口をとらえて皆で放さなかったが、あまりに忠吉がせき立てるので、家来が直政のところへ相談にきた。そのときの直政の答えがおもしろい。
「武士の子をさように用心して何の役にか立つべき。放してもし討死ならば、その分のことよ」。
と言い放ったというのだ。おそらく訓練のために預った主君の子である。討死にすればそれまでのことだと放言するには、直政にもそれなりの覚悟があったのであろう。戦場に於ける直政の面目をしのばせてくれる、好い話である。
この戦場で直政と忠吉の一隊は、先鋒と定められた福島正則の軍勢を出し抜いて、一番駈けをしている。正則の家臣可児才蔵が自軍に先駈けしようとする直政を見とがめて、誰何したところ、直政はそしらぬふりで「斥候の者なり」
と答え、そのまま駈け披けて敵陣へ飛び込んでしまったという。
このとき、直政も忠吉も負傷した。二人ともに家康の本陣に伺候したが、家康は息子の忠吉には、さほどのいたわりも見せず、直政には手ずから薬を取って与えたらしい。
本陣には先鋒の福島正則も顔を出していた。そこで直敢は正則に向かい、
「今朝は私がいくさをはじめたこと、おのおのがたを出し抜いたように思われるかもしれませんが、他意はありませぬ。いくさをはじめる塩合いがちょうどよかったので、はじめただけであります」
と告げたところ、正則はうなずき、
「御念の入ったご挨拶です。野合わせのいくさはすべて誰の手ということはなく、敵に早く取付いたものが思うようにはじめてよいものです」
と、挨拶を返した。直政は喜んで座を立ち、そのまま一間ばかり歩いたが、何を思ったのか引き返してきて、立ったままで再び正則に向かい、
「左候はば、今日のI番合戦はわれらにて候。さよう御心得賜われ」。
と言って立ち去ったという。何となく子供じみた態度のようだが、これには理由があった。徳川と豊臣が覇権を争う天下分け目の合戦である。直政としては、何としても譜代直臣の中から、一番合戦を勝取りたかったのだ。
さいわい自分がそれを果したので、家康はじめ諸大名の前で、そのことを公言しておいたのである。多少の稚気はあったにせよ、それを上回る政治的配慮もあったことであろう。
佐和山城
関ヶ原の戦いの後、伊直故は石田三成の居城であった佐和山城をもらい、近江のうち十八万石を与えられた。翌年正月には従四位下に昇り、直故は佐和山へ赴いた。
この転封に際し、直故や本多忠勝が加増の少さに不満を抱き、仲々折紙を受けなかったという話が『武野燭談』に見えるが、どうだろう。直政の日頃の行動から察して信じられないように思えるのである。外様大名に大領土を与え、譜代直臣に小禄を与えた徳川家の内情は、直故ならとうぜん知っていたはずで
ある。譜代直臣の当時の不満を、その筆頭たる直政に託した話なのかもしれない。
但しこの頃から家康の周辺も変化してくる。大久保忠隣、本多正信など文官派能吏が抬頭し、三人衆のかげが薄れてゆくのは確かであった。
直政のもらった佐和山城は、ひどく粗末な城だったらしい。城内はすべて荒壁で、上塗りしたところはなく、室内も多くは板張りのままで、庭にも樹など植えたようすもなく、手水鉢なども粗末な石を据えてあったという。
すべての財を関ケ原の一戦に投じた三成の心意気がしのばれる話だ。
井伊直敢はこの城に入った翌年、慶長七年二月一日、まだ四十二歳の若さで死んでいる。関ケ原役で、逃走する島津の軍勢を迫ったさい、直政は銃弾をあびた。
「いずくより打ちしか鉄砲玉きたって直政の乗りし鞍に一度、
また冑の吹返しに一度あたりたれど、事ともせずにかお馳せ行く所に、
玉また飛びきたって今度右の肩を打ちぬかれ持ちたる槍を落すやいな、
馬よりどうと落ける故、あとより馳せくる騎馬武者直ちに飛びおり、
直政を馬に乗せ、回りを打ち囲み引き返しける(『明良洪範』)。
とある右肩の傷が悪化し、それが原因で若死したといわれる。三人衆のうち榊原康政は慶長十一年、本多忠勝は同十五年の死亡だから、最年少の直政がいちばん早く世を去ったわけである。
直政の死後は、嫡男直継が井伊家をついだが、この嫡男は病弱を理由に退き、かわって次男直孝が当主となった。
直政の内室は徳川家康の養女花である。松平康親の娘であった。
家康の養女を妻としたために、直政は内室にずいぶん気をつかったらしい。
次男の直孝は内室の侍女が生んだ子であった。直政は内室に遠慮して女を外へ出し、生まれた直孝を引取ったのは慶長六年、直孝が十二歳となった年であるという。
『物語藩史・彦根藩』の著者西田集平氏によると、直孝が六歳のときにその母が直致を訪ねてきた。直孝を引取れという願いのためである。そのさい直政は直孝を引取る条件として、母親の死を要求し、じっさいにその母は直政の家来に斬られて死んだという。そこまで直政は、家康の養女である内室に遠慮していたのであろうか。
しかし、井伊家をついだ直孝は父直政に劣らぬ器量人だった。直孝の武勇や智略を物語る逸話は、父の直政を遥かにしのぐほど多く、まだきわ立っている。
彦根藩井伊家の不動の地位は、直政の創業と直孝の献身によってかちとられたものといってよい。
井伊家はその後加増を重ねて、三十万石、公称三十五万石となり、徳川三百年の間に閣老もしくは大老職を七代も出すという家格を誇った。
直政の法名は清涼院安安祥寿院。彦根の清涼寺に葬られた。 (了)













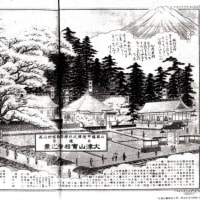
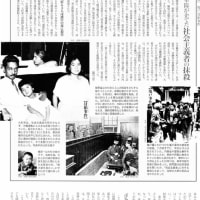
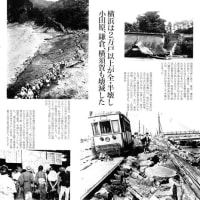










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます