芭蕉雑談 正岡子規
引用資料『甲府だより』 伊藤良氏著
《筆註》
伊藤先生のことについては何の知識もないので、『甲府だより』の序文を引用させていただくことにする。
新宿駅西口のデパ-トの古書市で見つけて手に入れた。山本周五郎の刊行本が一冊500円で並んでいた横に並んでいた。「高い」でも「欲しい」、財布の金も少なく、心配だったが思い切って手に入れた。大変だったのはその後である。電車に乗る金額が足りない。あわてて高速バスに飛び乗って帰ってきた。でも帰りのバスの中で今回紹介する、正岡子規の「芭蕉雑談」を読んでいるうちに、英断(?)を下した自分を褒めたくなる内容であった。
驚いたことがもう一つ、本の表装が高野山成慶院の重文で真贋を廻って論争を醸し出した「信玄像」であったことでした。(別項あり)
序文
敬愛する伊藤良博上は、昭和五九年以来、『能登だより』、『敦賀だより』、『上州だより』、および『琵琶湖だより』と相次いで四冊の本を出版されてきたが、この度『甲府だより』を上梓されることになった。年一冊の割合で刊行されておられ、しかもそれらがかなりの大部であり、多忙な診療の合間での執筆活動であることから、驚異の目を見張らざるを得ない。
今回の『甲府だより』は、著者が現在の山梨大学教育学部附属小学校に入学し、折にふれ武田神社に通った思い出の地、甲府に関する記述から始まる。巻頭の武田流軍学のバイプル『甲陽軍鑑』からの抜粋は、現在にそのまま通じる処世訓が選ばれている。統いて、甲州、信濃、北越、佐渡の紀行文と詩歌集、それらの地に関係した文云作品と著者の評価などがある。紀行文はその上地と関連のある古典の集約で、歴史物は読むだけでその風景が眼前に浮かび、読者を遠い育に引き一反すような華麗な筆致で綴られている。
これらの著書の基には、膨大な資料が必要であろうし、それらをまとめて名文を著すことは、努力と才能の然らしめるところであろう。
自分の専門分野についてならとにかく、専門外の分野について本を著すのは容易なごとではない。著者はご尊父の仕事の関係からか、学校をいろいろな上地で過こされ、大学卒業後も基礎医学から臨床医学へ、大学の研究者から病院勤務医、閉業医と豊かな人生経験を持たれ、それがこういった幅広い執筆活動に結びついているに連いない。
著者が甲府から千葉を経て東京に来られ、本郷の誠之小字校で、今は亡き畏友小林守博士と同級であられたようで、その関係でお近付きになり、また弱視斜学会を通じてのご縁で、今回序文を書かせて頂く光栄に浴した。
伊藤良博上のますまのご発展をお祈り中し上げたい。
昭和六二年五月二九日
丸尾敏夫(帝京大学教授)
目次
甲府だより 甲州紀行文持歌集 山部赤入者 将門記 水瀞伝と八大伝 芭蕉雑談
信濃紀行文・ 詩歌集 菩光寺縁起 苅菅道心行状記
北越紀行文・ 詩歌集 北越中自譜 良寛持歌集
佐渡紀行文・持歌集 承久の乱考 大平記阿新殿
世阿弥考考 佐渡日記 島根のすさみ
芭蕉雑談 本文 年齢
古今の歴史を視(ミ)、世間の実際を察するに人の名誉は多く共の年齢に比例せるがごとし。
蓋し文学者、技術家に在りて殊に熟練を要する者なれば、黄口の少年、青面の書生には成し難き筋もあるべく、或は長寿の間には多数の結果(詩文または美術品)を生じ得るが為に漸次に世の称賛を受くる事も多きことわりなるばく、はた年若き者は一般に世の軽蔑と嫉妬とによりて其の生前には到底名を成し難き所あるならんとぞ思わる。
我が邦古米の文学者美術家を見るに、名を一世に揚げ誉れを万載に垂るる者、多くは長寿の人なりけり。歌聖と称せられたる柿本人麿の如き其の年齢を詳かにせずと難も、数朝に歴仕せりといえば長々を保ちたる疑いなし。
その外年齢の詳かなる者に就いて見れば、
九○歳以上
土佐光信 俊成 北斉
八○歳以上
信実 鳥羽僧正 季吟 雪舟 肖栢 宗長 宗鑑 元信 梅宝 貞徳 宗祇 也有 蒼虬 馬琴 定家 兼良 蓼太 兆殿司
七○歳以上
紹巴 蘆庵 杏坪 宗因 野坡 雅望 秋成 常信 文晁 守武 南海 光起 千代 京樹 一蝶 真淵 鵬齎 探幽 巣林 宜良 千蔭 心敬 基債
六○歳以上
一九 抱一 通村 支考 蕪村 美成 出雲 春海 一茶 貞室 貫之 契沖 笛浦 許六 種彦
五○歳以上
半二 竹田 お通 昭乗 其角 凌岱 京伝 光則 光琳 嵐雪 大雅 白雄 山陽 西鶴 芭蕉
四○歳以上
浜臣 崋山 三馬 李由 蘆雪 丈艸 甚五郎
三○歳以上
波化 重恭
二○歳以上
実朝 保吉
最も有名なるのみにて此(カク)の如し。外邦にても格別の差異あるまじ。
華山の如き三馬の如き丈岬の如きは世甚だ稀なり。
バーンズの如きバイロンの如き実朝の如きは史に稀なりと謂うべし。
是に由って之を一観れば人生五○を超えずんば名を成す事難く、而して六○、七○に至れば名を成す事甚だ易きを知る。然れども千古の大名を成す者を見るに、常に後世に在らずして上世にあり。蓋し人文未開の世に在って特に一頭地を出だす者は衆人の尊敬を受け易く、又千歳の古人は時代という要素を得て嫉妬を受くる事少なきなめり。獨り,彼の松尾芭蕉に至りては今より僅々二百余牛以前に生まれて其の一門は六○余州に広まり、弟子数百人の多きに及べり。而して其の齢を問えば即ち五○有一のみ。
古来多数の茶托者を得たる者は宗教の開祖に如くはなし。釈迦、耶蘇、マホメットは言うを須(モチ)いず、達磨の如き弘法の如き、日蓮の如き、共の威霊の灼々たる実に驚くベきものあり。
老子、孔子の所説は宗教に遠しと雌も、一たび死後の信仰を得て後は宗教と同じ愛情を惹起せるを見る。
然れども是皆上世に起りたる者なり。日蓮の如き紀元後二、○○○年に生まれて一宗を開く、その困難察すべし。況んや其の後三○○年を経て宋教以外の一閑地に立ち、以て多数の崇拝者を得たる芭蕉に於ておや。人皆芭蕉を呼んで翁(オキナ)となし芭蕉を書くに白髪白鬚六、七○の相貌を以てして毫(すこし)も怪しまず。而して共の年齢を問えば即ち五○有一のみ。
平民的文学
多数の信仰を得る者は必ず平民的のものならざるべからず。
宗教は多く平民的の者にして、僧侶が布教するも、説教するも、常に其の目的を下等社会に置きたるを以て、仏教の如きは特に方便品さえ設け共の隆盛を極めたるなり。
芭蕉の俳諧に於ける勢力を見るに、宛然宗教家の宗教に於ける勢力と其の趣きを同じうせり。
その多数の信仰者はあながちに芭蕉の性行を知りてそを慕うというにあらず、
芭蕉の俳句を誦してそを感ずというにもあらず、
唯々芭蕉という名の自ら尊くもなつかしくも思われて、
かりそめの談話にも芭蕉と呼びすつる者はこれ無く、
或は翁と呼び或は芭蕉翁と呼び或は芭蕉様と呼ぶこと、
恰も宗教信者の大師様、お祖師様などと称えうるに異ならず。
甚しきは神とあがめて廟を建て本尊と称して堂を立つること、
是れ決して一文学者として芭蕉を観るに非ずして、一宗の開祖として芭蕉を敬う者なり。
和歌に於ける人丸を除きては外に例のなき事にて、
しかも堂宇の盛んなる、芭蕉塚の甚だしき夐(ハル)かに人丸の上に出でたり。
菅原の道真の天神として祭らるゝはその文学の力に非ずして、
主として其の人の位置と境遇とに出でたるものなれば、人丸、芭蕉と同例に論ずべからず。
されば芭蕉の大名を得たる所以の者は主として俳諸の著作共の物にあらずして俳諧の性質が平民的なるによれり。
平民的とは
第一、俗語を嫌わざる事、
第二、句の短簡なる事をいうなり。
近時これに附するに平民文学の称を以てするもまた偶然にあらず。然れども元禄時代(芭蕉時代)の俳諧は決して天保以後の俳諧の如く平民ならざりしは、多少の俳書を繙きたる者の盡く承認する所なり。
元禄に於ける其角、嵐雪、去来等の俳句は或は古宇を引き成語を用い、或は文辞を碗曲ならしめ格調を古雅ならしむる杯(ナド)、普通の学者と難も解すべからざる所あり、況んや眼に一丁字なき俗人輩に於てをや。天保に於ける蒼虹、梅室、鳳朗に至りては一語の解せざる無く、一句の註釈を要する事なく、児童走卒と雛も好んで之を誦し、車夫馬丁と雌も争うて之を摸す。正に是れ俳諧が最も平民的に流れたるの時にして、即ち最も広く大下に行われたるの時なり。此の間に在って芭蕉はその威霊を失わざるのみならず、却って名誉の高きこと前代よりも一層二層と歩を進め来り、その作る所の俳論は完全無欠にして神聖犯すべからざる者となりしと同時に、芭蕉の俳諧は殆ど之を解する者なきに至れり。個々共の意義を解する者あるも之を批評する者は全くその跡を断ちたり。その様恰も宗教の信者が経文の意義を解せず、理不理を窮めず、単に有難し勿体なしと思えるが如し。













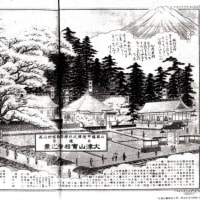
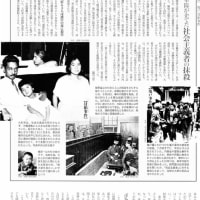
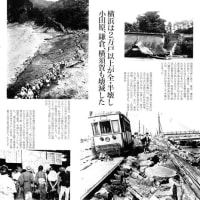









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます