一億人の証言 ガソリンの雨
燃える空と地の間で
私の空襲体験記 宍戸 かつみ
『一億人の昭和史』4 空襲・敗戦・引揚げ 昭和20年
毎日新聞社 1975-9
(当時・東京都江東区亀戸町在住)
昭和二十年三月十日。史上空前ともいうべき東京下町一帯の大空襲に江東区亀戸町で被災し、幸いにも五人家族全員生き残り、当時、小石川西丸町にあった叔父の家(母の実弟)を頼って、やっと落着くことが出来ました。
が、それも束の間、あの呪わしい日からわずか一カ月ばかりの四月十三日夜半、ふたたび大空襲に見舞われました。
ちょうど叔父は会社の仕事で地方に出張中、家族は京都に疎開しており、私どもは居候兼留守をあずかっておりました。
私は当時、女学校四年生(17歳)で、学徒動員で本所にあったD機械工場で働いていましたが、学校も工場も焼けてしまいました。祖母は三月十日の空襲にこりて福島県の山の中に疎開させ、兄は海軍省の上役の方のお宅に下宿させてもらっており、一家離散の有様でした。
後は娘の私と薬剤師である父、当時心臓病で弱かった母と三人のわび住いの毎日でした。
四月十三日の晩は風もなくおだやかで、妙に不気味なほど静まりかえった夜でした。あれはちょうど10時過ぎだったと思います。警報が出て、毎度のことながら身化度をして、父母と様子を見ておりま
した。間もなくB29の爆音と味方の高射砲のお腹にひびくような、ズシンズシンと、にぶい音が入り乱れて、だんだん近づいて来た様子です。その時なにかがピカッと光り、突如家の中がパァッーと真昼のごとく明るくなったので、とっさに外にとび出してみると、左手の上富士前の方角に照明弾がキラキラと落下して行くのが目に入りました。理研の建物がある場所あたりです。それと同時に空襲警報のサイレンが、けたたましく鳴りひびき、親子三入防空壕へすべり込んで、父と私だけ入口から首を出して空を見上げておりました。
敵機の爆音からして、今夜はどうも大編隊でやって来たらしく、地鳴りや轟音がいつもと違うようで、イヤな予感がするなと思った瞬間です。
突然、頭上でガラガラッ、ザァーッザァーッと耳をつんざく音とともに、ドスンドスンと、二、三度身体に猛烈なショックを受けて、頭をどこかへぶつけました。壕がユサユサゆれ動き、天井から土砂が降って来ます。
「やられたナ」と思ったとき、父が「ここにいたらあぶないっ、外に出ろ」と、母と私の手を引っぱって壕の外に出ました。前の路地に出ると、お向いのタンス屋さんの家に直撃弾が落ちたのです。ゴーツとものすごい音をたてて、あっという間に紅蓮の炎が吹き上げ、もう二階が崩れ落ちてないのです。無我夢中で走り、四つ角まで来ますと、もう大勢の人達がひしめき合っていました。
大塚、巣鴨、六義園方面は空も地も見渡す限り火の海で、わずかに南の後楽園(春日町方角)方面だけがほの暗いだけ、人々は完全に猛火の円の中に立たされてしまったのです。いつもは沈着冷静な父も顔色を変えて、
「こっちへ移って来てまだ日が浅く、地理がよくわからない。運を天にまかすしかないから、覚悟だけはしておけよ」といい渡すのです。
逃げまどう人々の流れに押され、突きとばされ、雨のように落下する焼夷弾の洗礼を死物狂いでよけながら、同じような場所を行ったり来たりしていたらしいのです。気がつくと市電氷川下停留所の所に立っていた私達でした。すぐ近くに、当時の鈴木賃太郎首相の邸があるのです。そのとき警防団員の人が途方にくれている私達に、「皆さん早く徳川邸に避難して下さい」と、大声で呼んでくれたのです。大きな門を入ってみると、もうたくさんの人々が避難
しておりました。雑草の生えた池のほとりに、やっと坐る場所を見つけ、いざとなったら水中にとび込む覚悟でいました。
やがて邸の回りの樹木に火が燃えうつり、パチパチと音を立て始めました。劫火が風を呼び、煙と熱風が激しく吹きつけます。敵機は未だ頭上を悪魔のように乱舞しています。そのときポトリとなにか顔に当たりました。雨かなと、手でさわってみると、プーンとガソリンの臭いがするではありませんか。敵機はガソリンをまいて焼夷弾の直撃をかけてきたのです。はらわたの煮えくり返る思いですが、どうすることも出来ません。隣に母と並んで坐っていたどこかの上品な老婦人は、さきほどからずっとお念仏を唱えどおしです。私も他の人達と力を合わせ、防空頭巾を池の水に浸しては吹雪のように降りかかる火の粉を夢中ではらいのけていました。
どのくらいの時間が過ぎたのか、ふとあたりが次第に静かになって来たのに、皆われに返りました。いつの間にか敵機も去り、東の空か白みはじめ、長い夜が明けたのです。
親子三人、しばらくは放心状態で口もきけませんでした。私達はふたたび九死に一生を得て助かったのです。一晩、生死を共にした老婦人が、「助かって本当によかったですね。火の粉をはらって下さってありがとう。おかげさまで駄目だと思っていた家が焼け残っていました」
といって、自宅からわざわざおにぎりを持って来て下さったのです。異臭の立ちこめる焦土の中で、いただいたあのおにぎりの味は、その人の温情と共に、一生忘れることが出来ないでしょう。昼すぎ親類の者が、私たちを探しにやって来ました。
学校や心あたりを探したが見つからず、百パーセントあきらめていたとのことでした。
母をリヤカーに乗せ、徳川邸を後に余煌くすぶる市電通りを黙々と歩いて行きました。途中、静かな谷中の通りにさしかかったとき、まぶしいほどの陽光に照り映えて桜の花だけは、あでやかに咲き誇っておりました。
水田に座り込んで 小林正子 (当時・芦屋市茶屋之町在住)
昭和二十年六月から終戦にかけて、阪神間もご多間にもれずB29の来襲をたびたび受けた。
そのつど交通は遮断され、二十二歳の私は勤め先の勧業銀行神戸支店から、阪神電車の線路づたいに芦屋まで家路をいそぐ。三宮あたりの阪急高架下には、その日の爆死者が百体、二百体と、整然と縦に一列に並べられていた。
死者はすべて焼夷弾のために蒸し焼きになり炭化している。人間は焼けるとそのままの形で縮むのか、ちょうど五、六歳の幼児のような大きさで、黒い人形そっくりだ。そして申し合わせたように胸を地につけ、そり返っているので、遺体はすべてうつぶせである。身元のわかった遺体には花やムシロがかけられているが大部分はそのままだ。
春日野道あたりで馬が倒れていた。これは機銃掃射によるもので、遺体は損われていない。ひっぱっていた車など散乱していないところをみると、馬方さんは助かったのかも知れない。その横を人が行き交う。人間は緊張の極限にきたとき、不思議に静かに行動する。矛盾を感じるのは爆撃をうけた地区と無傷の地域、昨日のままの平和な街並を通る時はどれがほんとうの今日なのか、一瞬ためらう。
芦屋は幸い今日の爆撃には無事だった。
翌日、ふたたび三時間の道のりを自分の足で勤め先に向かうとき、昨日倒れていた馬は半分になっていた。夜の間に馬肉として盗まれたのだ。私だって近くに住めば家族のためにそうしただろう、ここに一切れの馬肉があれば……。
この日、たどりついた銀行は、昨夜の焼夷弾攻撃をうけてくずれていた。銀行は海岸通りによく見られる赤レンガ造りなので、まず瓦礫の取りのぞき作業が今日の仕事始め。幸い金庫や地下室は無事だったが、外観は焼けただれており、すぐに開けるのは危険なので、近くの他銀行からお金を借りて開店する。それでも二人、三人とお客さん。
昼、瓦哩に腰をおろしてお弁当を開く。紙に炒り豆を包んできた人、大根ご飯(細かくきざんだ大根七分に米三分)など、仲間が集まってつまんだりつままれたり。
目の前の市電道(栄町二丁目)を越して、焼けくずれた南京町から元町通り一帯が、スポンとひらけていた。南京町は文字通り中国人の市場だった。くずれた防空壕から遺体が掘り出されていたが、中国人の遺体は必ずアグラを組んでいるので識別しやすいと、作業中の軍人さん(陸軍)が教えてくれた。
帰途、阪急高架下の三宮劇場はまだ猛煙と炎を吹き上げている。ここはその後一ヵ月あまりも異臭を放っていた。多くの人が焼夷弾の直撃をのがれて高架下に逃げこみ、ここで焼死したと聞く。
そしてついに、芦屋も初めての焼夷弾、爆弾の集中攻撃をうけ市内の三分の一が灰になった。正確には昭和二十年八月六日午前零時、広島原爆の八時間前である。
寝入りばなに空襲警報が鳴って敵機の来襲を告げたので、いつものように身仕度をして家族全員(父母に私、女学生の妹。悪いことに母の里に疎開させていた幼い弟妹二人も国民学校の夏休みを利用して昨日から帰っていた)庭先の防空壕に飛びこんだ。壕は父の手づくりで一畳あまり、頑丈にできている。一時間ぐらいで警戒警報に変わったので壕から這い出し、夏のことなので外していた蚊帳を釣って床にもぐりこんだ。そのとたんに焼夷弾の集中攻撃が始まったのだ。(B29、200機の波状攻撃ということを後で知った)あわてた私たちは、裸足のまま壕に飛ぴこんだ。無気味な照明弾がゆらりゆらりと空中にとどまり、あたりは真昼のような明るさだ。これは駄目だと思って我に返った時には壕の中が蒸し暑くなっていた。幼い弟がしきりに喉のかわきを父に訴える。父は壕をぬけ出し台所へ走って柄杓に一杯の水を運んできた。バケツを下げて走るという正常な神経はすでに麻蝉していたのだろう。
さらに暑くなったとき、このままでは蒸し焼きになるという恐怖が私たちをおそってきた。「町内会の壕へ逃げよう」と父がいった。阪神の線路を越すと水田だ。田には水がある。再び道を引き返し土手を攀じ登って三メートルあまりの高さを向こう側に飛び降りた。線路の枕木も燃えている。水田の泥に足をとられながら火の粉の降りかかるのが比較的少ない田んぼのまん中で、泥水を体にかけ合いながら私たちはへたりこんだ。家族六人、とにかく生命さえあれば……と肩をよせ合っていると「やア、きれいやナア」と無邪気な弟の声。火の粉をふりまきながら、一条の線光となってシュルシュルと落下する無数の焼夷弾は、なるほどこの世のものならぬ美しさだった。













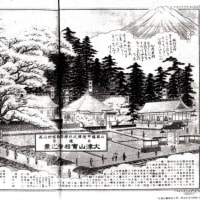
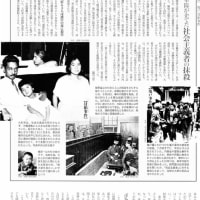
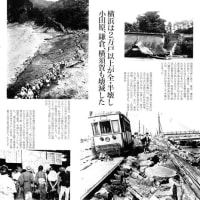










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます