素堂と蕉門俳論
1、芭蕉と素堂の俳論
芭蕉の俳論と素堂のそれとは、付かず離れずの関係であったことは、これまで述べて来たところであるが、芭蕉には自ら著した『俳論』は無い。何れも門人たちの「芭蕉翁聞き書き」(蕉翁語録で、芭蕉自身での俳論にふれているのは手紙の中だけである。従って前にも記した通り、多くの研究論文が成されているから個々では一々掲出せず、素堂との対比に比重を置いて述べたい。
芭蕉の正風(蕉風)俳諧から発句へ
芭蕉の正風(蕉風)と云う新風を、確実に出して来るのは元禄時代に入ってからで、それまでは模索の時代であろう。確かに天和年以降になると、後年の蕉風らしさが出て来るが、芭蕉の本質は発句(俳句)にあり、門弟たちを嘆かせるほど、延宝・天和期の句が変貌する。つまり発表・未発表の句にかゝわらず、推敲が上で蕉風として出て来るからで、これを看過すると、芭蕉自体の蕉風確立への形態が見えて来ない。芭蕉は俳諧から発句主体の、今日で云う俳句へと主眼を変えたのである。
延宝八年初夏「桃青の園には一流探し」(嵐蘭歌仙挙句)の自賛句もある「桃青門弟独吟二十歌仙』に続き仲秋目付けで嵐亭治助(嵐雪)序の『桃翁、羽々斎にゐまして、為に俳諧無儘経を説く。東坡が風情、杜子がしゃれ、で知られる其角の二十番自句合「田舎の句合」など、宗因流(談林風)の付句法によるものだが、芭蕉も句作法の模索の時期であった。この様な時に素堂序の「誹枕」が板行され、素堂が序文で「漢詩も和歌・連歌・俳諧も、その文芸性は根底では一つ、旅により受けるこの道の情と生き方は風雅」に触発されたものであろう、翌九年七月「俳諧次韻」をして、新風追求への意欲を示した。
これより前の五月十五日付け(翌年との鋭もある)で高山伝右衛門(麋塒・ビジ)宛てで
(前文略)
京大坂江戸共に俳諧の外古く成り候ひて、皆同じ事のみに成り候折りふし、
所々思ひ入れ替り候を、宗匠たる者もいまだ三四年已然の俳諧になづみ、
大かたは古めきたるやうに御坐候へば、学者猶俳諧にまよひ、
爰元にても多くは風情あしき作者共見え申し候。(中略)
玉句の内三四句も加筆仕り候。句作のいきやうあらまし、此の如くに御坐候。
一、 一句前句に全体はまる事、古風中興とも申すべき哉。
一、 俗語の遣ひやう、風流なくて又古風にまぎれ候事。
一、 一句細工に仕立て候事、不用に候事。
一、 古人の名を取り出でて、何々の白雲などと云ひ捨つる事、第一古風にて候事。
- 二文字あまり、三四字、五七字あまり候ひても、句のひびき能候へばよろしく、
一字にても口にたまり候を、御吟味有るべき事。(以下略)
芭蕉は俳風の変革期に処して、最新の風だと自負する、句作の狙いと付句の例を示している。
解説の必要はなかろう。
延宝八年の七月二十五日付け木因宛の手紙では
(前略)
昨日終日御草臥なさるべく候、
されど玉句殊の外出来候ひて、拙者に於いて大慶に存じ候。
それに就き「香箸」の五文字、
いかにも御尤もに存ぜられ候間「かれ枝」と御直し成さるべく候。
愚句も「鳥の句」「猿の句」皆しそこなひ、残念に存じ候。
「寝に行く蝿の鳥つるらん」といふ句にて御重有るべきを、
急なる席故矢ごろをはやくはなち、面目もなき仕合はせにて御坐候。以下略
この後は素堂訪問の打ち合わせなどである。また日付は欠けているが素堂訪問後の手紙で
今朝は御意を得珍重、今少々に罷り成り、汲々御残り多く存じ奉り候。
且つ文、第三致し候、河豚ノ子とありて秋めかしく候故、秋季□□置き候。
むつかしく思召し候はば御かへし菅成さる可く候。
五文字〔上五のこと〕蛤ともこちのこにも□候へ共、
清書之致様あしく候はゞ、是又可被仰聞候。(以下略)
素堂亭での三物をしたが、清書して木因に与える際のもので、第三の芭蕉の句は
河豚ノ子は酒乞ひ蟹は月を見て
とあったものを手直しした事が判る。木因添状によると
木因大雅のおとづれを得て
秋とはゞよ詞はなくて江戸の隠 素堂
鯔鈎の賦に筆を棹(サヲサス) 木因
鯒鴻の子は酒乞ヒ蟹は月を見て 芭蕉
と清書した事が記されている。翌天和二年三月二十日付木因宛で、大垣俳人の後見指導すゝめ、木因の句の評をしている。
(前文略)
且つ貴翁御発句感心仕候。猫を釣夜〔柳ざれてあらしに猪ヲ釣ル夜哉(「虚栗」所載)
其気色眼前に覚候。土筆をしぞ〔不明〕是猶妙、御作意次第改るに被覚珍重、
兎角日々月々に改る心之れ無く候らはでは、
聞く人もあぐみ作者も泥付く事に御坐候へば、随分御心ヲ被賭留められ、
人々〔大垣俳人〕御いさめ可被候。
天和二年暮の大火で焼け出され、翌三年五月に流寓先から江戸に戻った芭蕉は、其角撰の「虚栗」に鼓舞書を著した事は前出の通りである。こゝで素堂の「誹枕序」を自分成りに消化した芭蕉は、李・杜・白氏・西行らの風流を追う新風を宣示し、貞享元年(天和四年)「甲子吟行」(野ざらし紀行)の旅に上ったのである。この旅の途中、名古屋で「尾張五歌仙」を行い『冬の日』として板行し、天和の漢詩文詞を脱して蕉風樹立を示し、翌二年正月廿八日付半残宛で
- 江戸句帳等、なまぎたへなる句、或は云たらぬ句共多見え申候ヲ、
若し手本と思し召し御句作成され候らはゞ、聊かちがいも御坐有る可く候。
みなし栗(虚栗)なども、さたのかぎりなる句共多く見え申候。
唯李・杜・定家・西行等の御作等、御手本と御心得成さる可く候。
先此度之御句以下略
と、虚栗鼓舞書の新風をすゝめている。
貞享四年秋、素望との蓑虫贈答で素堂の「蓑虫記」に跋文を書いたが、素堂は「みのむし記」で芭蕉の才気ばしることを戒めているが、その冬十月廿五日帰郷の旅びと「卯辰紀行」(笈の小文)に出発した。その直後の十一月、素堂の序文を得た其角撰「続虚栗」が板行された。芭蕉が素堂の序文をつぶさに見ていることは「笈の小文」にある。
見る処花にあらずといふ事なし。おもふ所月にあらずといふ事なし。
像花にあらざる時は戎狄にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類ス。
夷狄を出、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり。
これが後に「不易流行論」に発展するのである。また芭蕉の俳諧思想と云う「虚実論」もこの辺りから盛んにされる。尚、虚実の初出は「常盤屋句合」(延宝八年)中の芭蕉の句評で、
勝ち句 だいだいを蜜柑と金柑の笑て曰
「橙を蜜柑金柑の論は、作のうちに作者て、虚の中に実をふくめり。
数句の中の秀逸、此句に於て荘周が心凍らむ。尤玩味すべし云々」とある。
貞享四年十一月け四日付寂照(知足)宛で
風俗そろそろ改り候はゞ、猶露命しばらくの形見共思召被下候。云々
つまり、現実を仮象と見る無常観によった語だが、「虚に居て実を行う、実に居て虚を行うには非ず」である。言わば「虚に入りて実に至り、虚に居て実に遊ぶ」と云うことである。
素堂は『続虚栗』序で「漆園の書いふものはものはしらずと、我しらざるによ巧いふならく」と皮肉っているのである。
芭蕉の俳諧感を見ると、修辞上の滑稽は造化の秘を発く事によって帰趣とした。従ってその詠は人事よりも自然が多かった。つまり、現実の生活を肯定して、その中で風雅の世界を求めることで、生活そのものには立ち入らずに、現実と永遠、いわゆる虚と実の中に道を求める処世の態度を維持する。また古人の心をもとめて幽玄体を追求する、よって逃避的な物の哀れに走ると云う。つまり、道に対して継承すべき伝統の発見と自覚により、幽玄・清淡・風雅を生じる。〔風雅の誠を勧め、心身を苦しめて絶す〕新しい表現をしようとする態度だと云うのである。
物の辞典には蕉風(正風)について
松尾芭蕉の始めた俳諧の作風。その精神は寂(サビ)侘(シヲリ)細みを重んじ、連句の付様に、うつり・ひびき・匂・位を重んじ云々と云う。
連句の付様は、貞徳期の物付では前の句の意味を取り、新しい事柄を加えて行くのであるが、宗因の談林風は心付で、前の句の意味を取り、新しい事柄を加えて行くと云う斬新奇抜な俳諧を興し、蕉風では心付を土台にして、前の句にある余情を汲んで付ける匂付とした。つまり貞門俳諧の流れを汲んで、匂・響き・俤・移り・位の各付を勧め、発句の美的理念に、さび・しをり・ほそみを重視したのである。
蕉風の理念が確立する経過
さて、蕉風の理念が確立するには、如何なる過程を経ているいるのであろうか、素堂と芭蕉の親密関係の成立に関しての一例として、『俳諧芭蕉談・乾之巻』に
素堂云、
我翁にはじめて対面せし時、
俳諧と連歌と心得いかゞすべきと問しに、
翁云、連歌はやさしく歌の上下を分てり、
一句一句にこととゝのひたるをもつて、百韻千句も心をつらぬるなり。
故に聯の字義なり。
俳諧は俚言たはむれて、たゞに今日世俗の上なり。
とあり、続いて後年の素堂の芭蕉感を述べている。〔恐らく貞享年間のこと〕
此一言にて我、翁の俳諧を思ふに、
翁の俳諧は心を用ゆる所、さらにひとしからず。
是を以一家の躰とす。格はともにひとし。連歌をかろめて去嫌やすくす。
其心連歌は前句を放たずその理にこたへ、そのものにこたへてさらに離れず。
はせをの俳諧は、前句の心を知てねばりを放つ、一句の物に感合す。
ものゝ情をさぐり知て附ければ、これを魂ともいわんか。
芭蕉は季吟門であるから、季吟との応答は判るが、素堂が季吟門でないことは、季吟撰の「続連珠」(延宝四年)に入集が無い事から証明できるが、唯し、潮春が「信章興行に」(『二十回集』)の詞書で附句をしているから、延宝二年の『廿全集』興行以外季吟七の関係は判らない。
しかし、前掲書に古今・万葉にふれて
古今集の序に六義を説く、季吟俳諧に六義を分つ、其義あたれる事にや。
翁云、
凡六義は詩の事なるを、和歌の義にしたるは、詩歌一徹の道理なれば尤なれども、
いまだ六義経緯の説にあたらず。我、季吟に此事を問いしに、
季吟云、
道を述べるための儲けなりと。
去々年の頃、素堂に季吟の答えを語りしに、
素堂云、
儲けなり、凡そ六義を皆格別なりとおのへり。風雅の頌の内に(中略)
わきて風雅のたつは、歌にては得分がたかるべし。
素堂云、
今の人歌よむに、万葉躰て詰屈なる事をよむ人あり。
万葉は詩の三百編ごとし。後世の体裁自ら別なり。
詩に古今の躰り、詩経の體又作る事も有べし。
…中略…
時世の風俗をしらずとやいはん。
古今集は、今躰に比すれば盛唐の風ありといへり。
此躰ぞ本とすべき、万葉は其材を取る所なり。
其体裁のごときは、尽く習ふべきにあらずといはん。
はせを曰く、
乱きはまって治に入の諺ならんと。予、此一言を感心す。
古学庵仏兮・幻窓湖中共編の「俳諧一葉某集」に
季吟云、
或時挑青申せれけるは、万葉集を周覧せしに、
全篇、諸兄卿のえらび給ひたるものとは見えず。
多くは其人々の家の集を、後によせ集めたるものと見ゆと也。
此こと予が見識の及ぶ処にあらず。桃青の云ことを聞てより、
大に利をえたりと。季吟物がたり、素堂より伝ふ。
恐らく延宝年代のものであろう。以上掲出した条から見ると、素堂は芭蕉をはさんで季吟と、かなり親しく会っている事が判る。













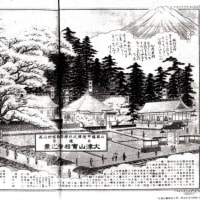
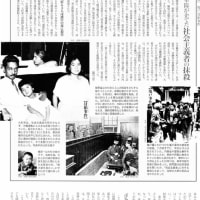
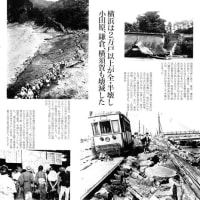










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます