伊藤生更の歌碑 甲府の夢見山中腹にある
<著者 奥山正典氏 >
北の方より駒 鳳凰 農島と我が目を移す雪の高山 生更
この歌碑は昭和三十八年六月十六日、甲府の夢見山の中腹に建立され、同日除幕式が行われた。裏面に「歌誌美知思波発刊三十周年と山梨県文化功労者伊藤生更生誕八十年を慶び門流一同これを建つ。
英知思波短歌会。昭和三十八年六月」とある。
除幕式は雨のため、甲府市立春日小学校講堂に移され、「美知思波」会員のほか、来賓として、知事代理田中県開発部長、中村星湖、許山茂隆氏等が見えられ、中村星湖氏は手づくりの杖に
「手づくりのあららぎの杖ささけまつる 八十瀬を越ゆるうた人君に」
の一首をそえて先更翁に贈られ、しみじみとした場面もあった。 「万」は「かた」と読む。
さて、先更翁は、昭和元年短歌結社「アララギ」に入会、斎藤茂吉が昭和二十八年に亡くなるまで、茂吉を絶対の師と仰ぎ、万葉を宗とする。真実一路の作歌道に終始した。昭和十年、組歌話「美知恵波」を主宰創刊し、その詠風は、荘重・枯淡・純素、県内外の六百五十名に及ぶ後進の育成に努められ、今日、全国の短歌誌でも十七、八位の会員を擁する結社の基礎づくりをしたのである。
この一首は、生更翁が散策のコースとして、こよなく愛した夢見山から、甲府盆地の北西にそびゆる駒ヶ岳、鳳凰山、農鳥岳を眺望しての自然詠で、見たまま、感じたままを、平明率直に詠じて、雪の高山の荘重、峻厳美を表出し、作者の心の姿勢までもうかがえる。生史前は生前「我が目を移すとした所に現実感があるのだ」と申され、その著「茂吉秀歌の鑑賞」「作歌道」などで、「客観は主観に即(つ)く」という歌論、芸術論を唱道されたが、これらを裏づける作品といえる。翁は歌集「草谷」「柴山」「山雲」「甲斐の国」を残し、昭和四十七年七月二十七日、八十八歳で他界される。













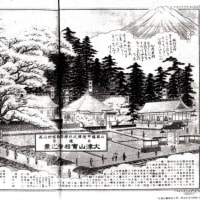
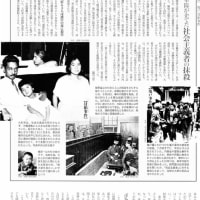
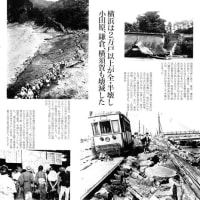










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます