今年の大河ドラマ『八重の桜』は、ほんとうに色々と考えさせられたし、胸に迫るシーンがたくさんあって、私の中では、もう単なるドラマの枠を超えていた。
もともと、大河の主流である幕末ものや戦国時代に、個人的には興味が無いというか、あまり好きじゃないので、私自身、こんなに魅入られるとは思ってもいなかった。
大好きな福山さんの『龍馬伝』すら後半は、残虐シーンがつらくて見るのやめてしまったし・・・。
幕末モノは、誰に焦点を当てるかで、時代の見方ががらっと変わってしまうものだ。今回の『八重の桜』を見ながら誰が正しくて誰が間違っていたかなどと、一言ではとても言えないのだと、教えられた気がした。
逆賊の汚名を着せられた会津藩が、とても誇り高くまっすぐに生きてきたことを知った。ドラマの前半はそれで十分満足だったけれど、負けたあとの後半にこそ、このドラマのテーマがあったのだと思った。
何をしても人一倍の能力を見せてくれる八重さん。だけでなく、会津出身者では、京都府政の礎を作った兄の山本覚馬はじめ、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と同僚になったという秋月悌次郎、山川浩・健次郎・捨松の山川家の兄弟姉妹など、明治になっても活躍した人々が多く、文武両道、教育がゆきとどき、教養豊かな人々を作った会津という国の懐の大きさを感じた。もし、戦争なんかしないで、死なずにすんだ会津の人材が新しい国造りに参加していたら、また違った日本の姿ができていたかもしれないしね。
人を殺すことに正義などなく、誰かを打ち負かすことが、喜びではなくて、次の憎しみを生んでしまう。
維新の誰もが、不完全で未熟だった、しかし歴史を動かしたそれぞれが、一生懸命に良かれと思ったことをしていたのだ、というメッセージは伝わってきた。
ドラマ後半は、戦いのあとの喪失感や心の葛藤に悩みながら、新島襄というかけがえのないパートナーに出逢い、心を救われて再生していった八重さんの姿。
それらを通して、番組の本当のテーマは、人生は勝ち負けではなく、愛をもって支えあうこと、戦うことの虚しさを知り、相手を許し、憎しみを乗り越えてゆくこと、・・・だったんじゃないかと、ひしひしと感じて、知らずに涙が出てくる場面が多くて・・・参ったよー。

今現在、明治維新の時代に戻したいような安倍政権が復活したおかげで、現在に通じるメッセージがタイムリーに伝わってくるのは、偶然だったのか。
新聞社を立ち上げた徳富蘇峰は、同志社大学の前身である同志社英学校の出身で、新島襄や八重さんの教え子に当たる人なのだけれど、日清戦争の記事を書くにしても、勇ましいことばかりを書いていた。
八重さんが創立したばかりの日赤の看護婦として働いていた広島の従軍病院を訪ねてきて、戦況を病人にまで取材する姿。思わずたしなめる八重さん。
だが、彼は、「今は士気を鼓舞する記事を優先する時だ、読者もそれを望んでいる」と言い放ち、聞く耳を持たなかった。
その上、自由党の板垣退助のところにまで出向いて、「講和会議には、強い態度で臨め、国民はそれを望んでいる」と、強硬外交を唱える。
戊辰戦争を戦い、たくさんの悲劇を目の当たりに見てきた板垣は、「おぬし若いの」と一喝するが、彼の耳には、何も届かない。
当時のすべての新聞社は、皆こういう論調であったという。
京都の八重さんの茶室で、八重さんと蘇峰の会話は、とても印象的だ。
八重さんのたてたお茶を飲み干した蘇峰は、急いで東京に戻ろうとする。それをとめる八重さん。
「もう一服してゆきなんしょ」
「急いで東京にもどらんといかん。時局が切迫している時ですけん」
「徳富さんの国民新聞、近頃は、政府の機関誌のようですね」
「軍備増強ば、あおっちょるということでしょうか」
「・・はい」
「国家のためです。私は国を愛するものです」
「襄も愛国者でした。
でも、襄が愛した国というのは、そこに暮らす人間、一人ひとりのことです」
「・・・・」
「同志社にきた頃、徳富さんは自分の目で世の中の本当を書きたいと言っていた」
「言論が人を動かす時代がきたっです」
「その力を何に使うのですか」
「え?」
「人を動かす大きな力を」
「・・・・」

「
力は、未来を切り開くために、使わねばなんねえよ」
「・・・・」
「昔、私が生まれた会津という国は、大ぎな力に飲みこまれた。
わたしは、銃を持って戦った。最後の1発を撃ち尽くすまで。
ひとりでも多くの敵を倒すために
だけんじょ・・・もしも今、わたしが最後の1発の銃弾を撃つとしたら・・・」
会話はそこで終わる。
しかし、映像は続く。スペンサー銃を持ってお城に立てこもった若き日の八重の姿。
彼女は、最後の弾を、高く空に向けて撃った。
それは、人を動かし、戦をしむける「大きな力」に向かって撃ったのだろうか。
そして、もう、他者に向けて銃弾を撃たないという決意、戦さをしないという決意の表れであったかもしれない。

史実とはいえ、ドラマだから脚色はあるだろうけれど、このような良質の物語を書いてくださった脚本家の山本むつみさんには、心から拍手を送りたい。
八重さんの願いもむなしく、この後、時代は、日露戦争へと進み、そして、日本を含めた世界は、世界大戦に向けて突き進んでいった。
1945年、日本の国土にふたつの原爆が投下され、一瞬にして数十万人もの普通の人々の命が奪われた。
日本は、2度と戦争をしないと憲法で誓った。
たくさんの人々の命の代償、血と涙の結晶が、今の日本国憲法だ。それを忘れてはなんねえよ。
(ところで、八重さんが徳富蘇峰に「近頃は政府の機関誌のようですね」と言ったのを聞いて、思わず、読売と産経を思い出したのは、私だけではありますまいて。)

















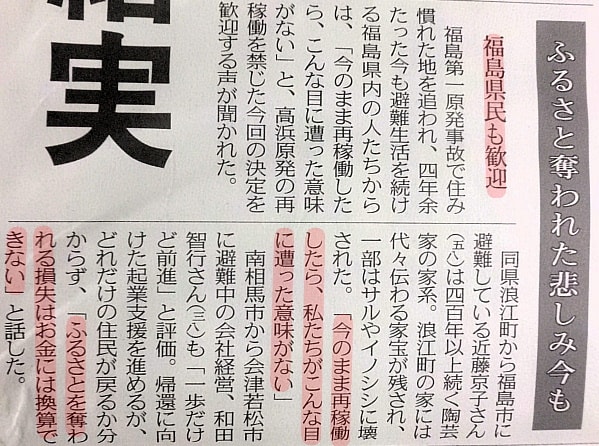


 今年はこの記事で終わります。
今年はこの記事で終わります。





















