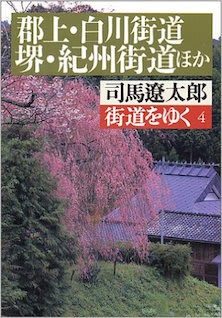

電話をかけた相手から、突然怒鳴られ「馬鹿野郎」と罵倒され、受話器を投げ出すように切られたことが三度ほどある。相手に対して特に失礼は思い当たらず、また非常識な物言いをしたわけでもない。
もう三十年前後も昔のことである。その方々とは作家の開高健氏であり、元横綱朝潮の先々代の高砂親方である。そしてもう一人は司馬遼太郎氏であった。いずれもすでに鬼籍に入られているので、何の差し障りもない。
電話はイベントの企画で打診したのだった。よほどに虫の居所が悪かったか、二人の作家は執筆に詰まって苦吟していたか、あるいは乗りに乗って筆が進んでいるときに、突然電話のベルでその思考と作業を断ち切られたかであったろう。またイベント屋など実に怪しげな輩だと思われたに相違ない。
司馬遼太郎氏への用向きはこうであった。当時、ある有名女性誌の発刊十周年だったかの記念イベントの企画を頼まれた。その女性誌はスター、ファッション、ゴシップ、グルメ、映画、旅の情報で構成されていた。私が考えたのが「司馬遼太郎とゆく京都・青春群像の旅」という、読者参加の旅行イベントであった。
そもそも作家への打診は、怪しげなイベント屋より出版社がすべきなのである。もしこのときの企画が実現していたら、近年流行の若い女性たちの「歴女」ブームは、もっと早くに起こっていたかも知れない。また私は、怒鳴られ取りつく島もなく電話を切られたにも関わらず、その後も彼の良き読者であり続けた。ちなみに私は開高健氏の無礼な電話以後、「ロマネ・コンティ」とかいう退屈な本を一冊読んだきりで、決して良き読者ではない。
司馬遼太郎は膨大な著作を遺した。私はその著作のほとんどを読んでいる。その中で何度も読み返している著作がある。小説の「竜馬がゆく」「燃えよ剣」「峠」「坂の上の雲」「花神」「菜の花の沖」などではない。シリーズ全四十三冊の「街道をゆく」である。全冊もう四、五回は読み返しているだろう。
「街道をゆく」は実に楽しい紀行の本である。固い歴史学術論文ではない。全く 肩肘の張らない随筆である。読者は随意に、どの街道に立ち至ってもよい。
風土と歴史を考察しながら、次から次へと想像を飛ばし、ときにその街道から大きく逸れる。佇むその地や時代から大きく外れる。彼の連想は七世紀から明治に飛び、また戦国から元禄へと、人を語り、時代を遊ぶ。宗教を語り、思想を簡便に解説し、築城や石積みの技術を語り、運河の掘削の思想や稲作の伝播に想いを馳せる。まさに人と風土と歴史の蘊蓄紀行である。
登場人物も楽しい。彼の旅のほとんどに同行した挿絵の須田剋太画伯は実に愛らしく、画伯の思想(道元への固執)や自らの身体への思い込み、そのぎこちのない挙措は微笑ましい。また時々旅に同行する作家の金達寿(キムダルス)氏などや、編集部の人たちの素描も素晴らしい。
ときに「街道をゆく」の本道から大きく外れて、野芹咲く田畑の畦をゆくかのごとき、どうでもよいような逸話に遊ぶ。その中には不思議な猫の話や、愛らしい犬や、どうにも悲しい犬の話なども出てくるのである。
その猫の話は「街道をゆく4」の「郡上・白川街道 堺・紀州街道ほか」の巻にある。その「ほか」に当たる「丹波篠山街道」である。この旅の途中から須田画伯とは別行動となり、編集部のH氏とC社の編集部のI女史が同行した。Iさんは東京住まいだが、もともと京都の女性である。
篠山の古さびた宿に入り夕食となり、彼等の話題がよく出没する猿や猪の話となった。食事の世話をする女中さんはよほど動物好きらしく、愛情を込めて猿や猪の観察談を物語った。H氏が山陰線の亀岡あたりで、汽車の窓から山を走る猪を見たという話をした。冬場の畑には荒らすべき食物もなく、猪は悲壮な感じで地響きを立てるように走っていたという。その「悲壮」という言葉から連想の灯がともったらしく、I女史が言った。以下やや長いが引用したい。
「私は猫が涙を流して泣いているのを見たことがあります」
と言い出して、話が丹波から京都の巷へ外れてしまった。Iさんの母堂は飼い猫のしつけにやかましく、このためその猫はいやしくもお膳の上のものに手をのばすということがなく、堪えに堪えているようなふぜいで、人間たちが食事をするのを待っているというのが彼女の日常であった。
ある日、母堂が親戚の家へゆかれると、そこの猫は実に放縦で、お膳の上のものを嗅いだり、手でひきよせたり、包み紙に首をつっこんだりして、母堂はそのために神経がくたくたになって帰宅した。
「そこへゆくと、ほんまに、お前はおとなしゅうて、ええ子やな」
と、母堂は夕食のとき、猫をふりかえって、ほめてやった。そのとき猫が無言で泣きだしたというのである。大きな目にみるみる涙があふれて、その滴ってゆく涙がひげを濡らしたというから、とても何かの見違えとはちがいます、私もびっくりしましたし、母も息をのんで見つめていました、とIさんはいった。その猫にすれば某さんの家の猫こそ猫らしい猫で、自分は御当家の御躾に堪え忍んでいるだけなのです、と言いたかったのであろう。
「なるほどな」
動物好きの女中さんはその話によほど感動したらしく、何度もうなずき、しかし猫よりもーーといった。亀岡の山を走っていた猪のほうがもっと可哀そうやな、という。猫はなんといっても食物を人からもらって暮らすのだが、猪の境涯ともなればそうはいかないのである。
猫がぽろぽろと涙を流して泣く……「街道をゆく」全記述の中で、いささか異質に過ぎるこの逸話が、なぜか私の心に留まり忘れがたい。
また「街道をゆく38 オホーツク街道」には、印象的な犬が二頭出てくる。女満別の遺跡の発掘現場である。
犬が一頭、いそがしげだった。
現場のあちこちを歩き、坑と坑の細い道に立って作業現場ぜんたいを見まわしたかと思うと、一挙に区画のすみまで行ってその角度からひとびとの動きを見、また身をひるがえして、区分ごとのふちを歩いている。
雑種の日本犬で、シッポの巻きあげが、威勢いい。
「自分も働いているつもりなんですね」
私は感心して、編集部の村井重俊氏にいうと、この人は童話のなかの人のまなざしになった。
司馬らが発掘現場のプレハブ小屋で出土品を見たり、その説明を受けているあいだ、この犬は立ち上がって窓ガラスいっぱいに張りついて、中の様子をのぞいていたらしい。
もう一頭の犬の話は、紋別西郊の、雪原と化した海辺の砂丘上の喫茶店で食事を摂っていたときである。その犬は雪原側の出入り口近くにいて、ワゴン車から降りてくる人々を見ると、すがるように寄っていく。そんな動作を繰り返しているのだ。その店の犬でもなく、野良犬でもないという。北海道犬の雑種らしく見える。軽食堂の女主人によれば「けさ、車できた人に捨てられたんです」とのことである。だから、もしや飼い主ではないかと、犬は車がとまるたびに飛んでゆくのである。まだ自分が野良犬になったとは、認めていないのに違いない。その犬の様子を覗っていると胸が痛む。むごい話になった。
しかし「街道をゆく」は楽しい蘊蓄紀行である。だからこの犬の話も北海道犬とアイヌ犬の話として展開し、東北地方のマタギが猟に使っている犬とアイヌ犬は同系統であるらしいとか、マタギはアイヌ語の「狩猟者(マタンギトノ)」と無関係ではあるまいとか、読んでいて興味は尽きない。まるで芳醇な雪中梅を馳走されたような、あるいは立ち寄った農家の縁側で深蒸し茶とうまいお新香を出されたような、気分の良い時間が過ぎていくのだ。
司馬遼太郎「街道をゆく4 郡上・白川街道 堺・紀州街道ほか」
「街道をゆく38 オホーツク街道」(朝日文庫)









