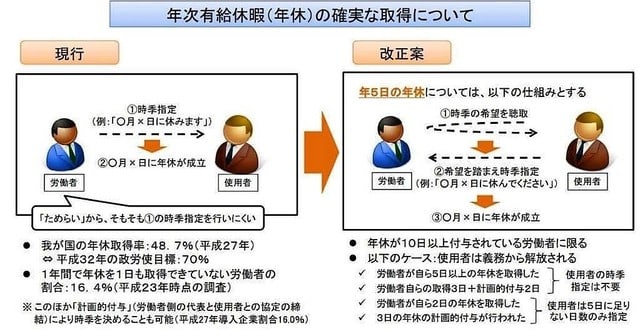昨日は京成電鉄労組の「委員講座」で、社会保障について90分間講演させてもらったが、その際にも触れた、1月8日の第144回労働政策審議会職業安定分科会で出された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の内容。
縦書きで読みにくいから横書きにして、特にうちらとこに関係の深いところをマーカーして作って、今日の会議で報告した。
そのついでに、こちらのブログにも掲載しておこう。
第一 雇用保険法の一部改正
一 目的の改正【施行期日 令和2年4月1日】
労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを雇用保険の目的として追加するものとすること。
二
育児休業給付の新しい給付の体系への位置付け【施行期日 令和2年4月1日】
1 育児休業給付金について、失業等給付の雇用継続給付から削除するとともに、失業等給付とは別の章として育児休業給付の章を新設するものとすること。
2 現行の育児休業給付金に係る規定を削除するとともに、1で新設する章に同内容を規定するものとすること。
3 失業等給付で措置されている未支給の失業等給付、返還命令等、受給権の保護及び公課の禁止の規定について、育児休業給付金について準用するものとすること。
4 国庫は、育児休業給付について、当該育児休業給付に要する費用の八分の一を負担するものとすること。
5 一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとすること。
三
高年齢被保険者の特例【施行期日 令和4年1月1日】
1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるものとすること。
(一)一の事業主における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
(二)二以上の事業主の適用事業に雇用される六十五歳以上の者であること。
(三)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(注1)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
(注1)五時間とする予定〔省令〕。
2 事業主は、労働者が1の申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
四
被保険者期間の計算方法の改正【施行期日 令和2年8月1日】
被保険者期間が十二箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては六箇月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が十一日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間が八十時間以上であるものを一箇月として計算するものとすること。
五
高年齢雇用継続給付の改正【施行期日 令和7年4月1日】
1
高年齢雇用継続基本給付金の改正
高年齢雇用継続基本給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に百分の十(当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の
百分の六十四に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とするものとすること。
2 高年齢再就職給付金の改正
高年齢再就職給付金の額は、1と同様の方法により算定して得た額とするものとすること。
六 雇用安定事業の改正【施行期日 令和3年4月1日】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく高年齢者就業確保措置の導入等により高年齢者の雇用を延長する事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことについて、雇用安定事業として行うことができるものとすること。
七 会計法の特例【施行期日 令和2年4月1日】
年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が自動変更対象額、控除額又は支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付又は育児休業給付があるときは、これらに係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受ける権利については、会計法第三十一条第一項の規定を適用しないものとすること。
八 報告徴収及び立入検査の対象の追加【施行期日 令和2年4月1日】
報告徴収及び立入検査の対象に、被保険者と認められる者を雇用し、又は雇用していた事業主を追加するものとすること。
九 国庫負担の改正【施行期日 令和2年4月1日】
1 令和二年度及び令和三年度の各年度における失業等給付等に要する費用に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の百分の十に相当する額とするものとすること。
2 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和四年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で雇用保険法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすること。
十 その他
その他所要の改正を行うこと。
第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
一 労災保険率の算定方法の改正【施行期日 交付の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日】
第六の二及び三に伴い、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の場合における労災保険率の算定方法について規定するものとすること。
二 雇用保険率の弾力的変更の算定方法の改正【施行期日 令和2年4月1日】
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更に係る算定において、教育訓練給付の額と雇用継続給付の額を除いて算定するとともに、算定で用いる国庫の負担額から育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額を除き、算定で用いる徴収保険料額から一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額を新たに除くものとすること。
三 二事業率の弾力的変更の範囲の改正【施行期日 令和3年4月1日】
労働保険特別会計の雇用勘定の雇用安定資金の状況による雇用保険率の変更が行われた場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、雇用保険率を当該変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更できるものとすること。
四
雇用保険率の改正【施行期日 令和2年4月1日】
令和二年度及び令和三年度の各年度における雇用保険率については、千分の十三・五(うち失業等給付に係る率千分の六(注2))(農林水産業及び清酒製造業については千分の十五・五(同千分の八)、建設業については千分の十六・五(同千分の八))とするものとすること。
(注2)
令和二年度における失業等給付に係る雇用保険率については弾力条項の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項)に基づき、千分の二とする予定〔告示〕。
五 その他
その他所要の改正を行うこと。
第三 特別会計に関する法律の一部改正【施行期日 令和2年4月1日】
一 育児休業給付資金の創設
1 雇用勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び3による組入金をもってこれに充てるものとすること。
2 1の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとすること。
3 雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとすること。
4 雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとすること。
5 育児休業給付資金は、育児休業給付費及び特別会計に関する法律第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができるものとすること。
6 育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとすること。
二 繰替使用の改正
雇用勘定においては、同勘定の積立金、育児休業給付資金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができるものとすること。
三 その他
その他所要の改正を行うこと。
第四
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正【施行期日 令和3年4月1日】
一
高年齢者就業確保措置
1
定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下同じ。)の定めをしている事業主等は、次に掲げる措置のいずれかを講ずることにより、現に雇用している高年齢者等の六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないものとすること。ただし、当該事業主が、創業支援等措置を講ずることにより、当該高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した就業の機会を確保する場合にはこの限りでないものとすること。
(一)当該定年の引上げ
(二)六十五歳以上継続雇用制度(現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等に引き続いて雇用する制度をいう。3及び4において同じ。)の導入
(三)当該定年の定めの廃止
2
1に規定する創業支援等措置は、次に掲げる制度であって労働者の過半数を代表する者等の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た上で導入されるものをいうものとすること。
(一)現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者が定年後等に引き続いて
新たに事業を開始する場合等に、事業主が、当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約に基づき当該事業主が当該高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結する制度
(二)現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等が定年後等に引き続いて次に掲げる事業(当該事業を実施する者と当該高年齢者が、当該事業に係る
委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結するものに限る。)であって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものに係る業務に従事できる制度。ただし、ロ又はハの事業に係る業務に従事できる制度については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該者が、当該高年齢者が当該業務に従事する機会を提供する契約を締結するものに限る。
イ 事業主が実施する事業
ロ 事業主が団体に委託する事業
ハ 事業主が事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行う団体が実施する当該事業
3 六十五歳以上継続雇用制度には、事業主が他の事業主との間で、当該事業主が現に雇用している高年齢者等であって定年後等に雇用されることを希望するものを、定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとすること。
4 厚生労働大臣は、1に掲げる措置及び創業支援等措置(5において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針を定めるものとすること。
5 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるとき等に、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすること並びに高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告すること等ができることとすること。
6 事業主による厚生労働大臣への報告事項に、創業支援等措置等に関する状況を加えるものとすること。
二 その他
その他所要の改正を行うこと。
第五
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正【施行期日 令和3年4月1日】
一 国の施策
国が総合的に取り組まなければならない事項として、次に掲げるものを規定するものとすること。
1 労働者の職業選択に資するよう、職場に関する事項又は職業に関する事項の情報の提供のために必要な施策を充実すること。
2 高年齢者の職業の安定を図るため、高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施の促進のために必要な施策を充実すること。
二
中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等
1 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければならないものとすること。
2 国は、1の割合その他の中途採用に関する情報の自主的な公表が促進されるよう、必要な支援を講ずるものとすること。
三 その他
その他所要の改正を行うこと。
第六
労働者災害補償保険法の一部改正
一 目的の改正【施行期日 交付の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日】
複数事業労働者の複数事業の業務を要因とする事由に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とする事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを、労働者災害補償保険の目的として追加することとすること。
二
複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設【施行期日 交付の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日】
業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付と並び、
複数事業労働者の複数事業の業務を要因とした負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設するものとすること。
三
給付基礎日額の算定方法の特例【施行期日 交付の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日】
複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とした事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により保険給付を行う場合は、当該
複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とするものとすること。
四 会計法の特例
年度の平均給与額等が修正されたことにより、厚生労働大臣が労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率、同法第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率等を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法第三十一条第一項の規定を適用しないものとすること。
五 その他
その他所要の改正を行うこと。
第七 施行期日等
一 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。
1 第一の四令和二年八月一日
2 第二の一及び第六の一から三まで公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
3 第一の六、第二の三、第四及び第五 令和三年四月一日
4 第一の三 令和四年一月一日
5 第一の五 令和七年四月一日
二 検討
政府は、第一の三の施行後五年を目途として、第一の三の1に基づく適用の状況、これにより高年齢被保険者となった者に対する雇用保険法に基づく給付の支給状況等を勘案し、二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する同法の適用等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
三 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこと。















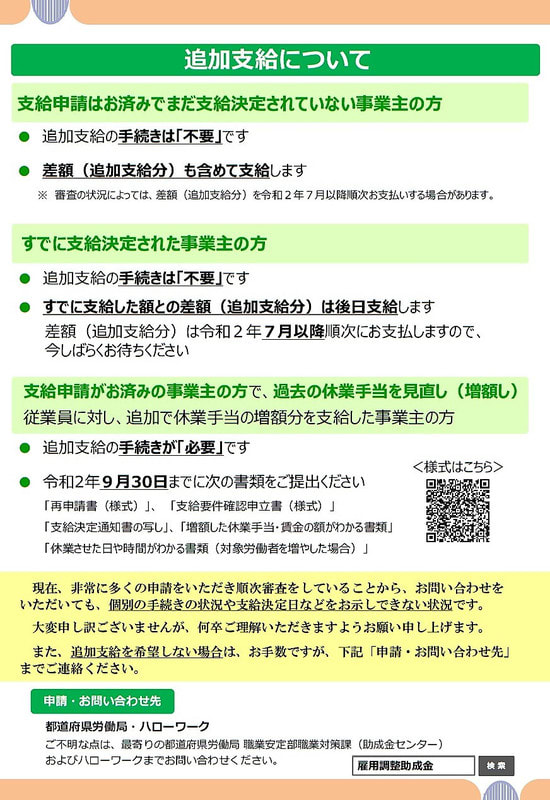






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1adbbbe8.43df8136.1adbbbe9.c39647a8/?me_id=1332214&item_id=10000056&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaei-trading%2Fcabinet%2F05248292%2Fmask%2Fkaeimask50.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaei-trading%2Fcabinet%2F05248292%2Fmask%2Fkaeimask50.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac16cee.4a94eac4.1ac16cef.7f68e60a/?me_id=1265863&item_id=10000018&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoneymother%2Fcabinet%2F06634963%2F06740946%2Fnew_umf10-250-trial2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoneymother%2Fcabinet%2F06634963%2F06740946%2Fnew_umf10-250-trial2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)