「中国の医学書の人体図」と「解体新書の人体図」を同時に提示する。
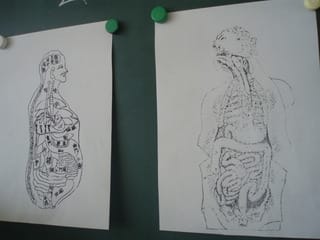
子どもたちは、こういう「気持ち悪い(?)」絵が大好き。
盛り上がる。
どちらも医学書であることを説明した後
=======================
もし自分が手術をしてもらう場合、
どちらの医学書を使って手術してもらいたいか
=======================
と発問した。
子どもたちは、「解体新書」を選択した。
このように、江戸時代後半、「医学」が進歩してきたことを確認し、
その他にも様々な学問が発達していったことを伝える。
子どもたちは自然に学習課題を設定する。
■■■■■■■■■■■■■■■
新しい学問は、世の中に
どのような影響を与えたのか
■■■■■■■■■■■■■■■

杉田玄白を紹介し、オランダの医学書を翻訳していった苦労を調べる。
「フルヘッヘンド」(←ターヘルアナトミアには、なかったという説もある)から、
「盛り上がる」=「鼻・胸」=「落ち葉の集まり」
などの説明で、当時の苦労を読み取る。
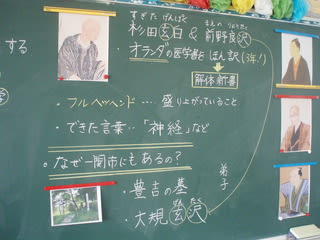
そして、解剖の見学の図から、日本で初めて「腑分け」をしたことについて調べる。
すると、子どもたちが
==================
先生、(春に行った)市の博物館で
解体新書が展示されてましたよね
==================
と言ってきた。
そこで、なぜ、一関市と解体新書がつながっているのかを
説明した。
一つは「豊吉の墓」

市内にあり、「腑分け」をされた罪人の墓だ。
日本の歴史の中でもかなり早い段階で腑分けを行った場所であり、
そんな場所が身近にあったことを子どもたちは驚いていた。
もう一つは「大槻玄沢」
一関市の有名人、大槻三賢人。

医者である玄沢は、師匠の杉田玄白、前野良沢の字を一字ずつもらって
「玄沢」と名乗っている。
その辺りは「地域教材」の良さ。
子どもたちの食いつきも良かった。
その後
医学の他にどんな学問が広がったかを調べ学習。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
・本居宣長=国学(古事記伝)
・高野長英=蘭学(幕府の政策を批判)
・伊能忠敬=天文学(測量で日本地図を作製)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
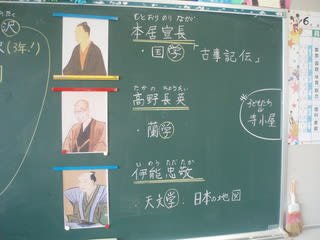
ただ、調べるだけでは定着しないので、
エピソードとともに説明。
・高野長英が奥州市出身で、液体で顔を焼いて整形したこと
・伊能忠敬は50歳を過ぎてから勉強を始め、海岸線をひたすら歩いたこと
などは、子どもたちは興味津々で聞いていた。
エピソード記憶で、しっかり定着を図りたいと思った。
準備や教材研究が若干足りない1時間だったが、なんとか流れて、良かった。

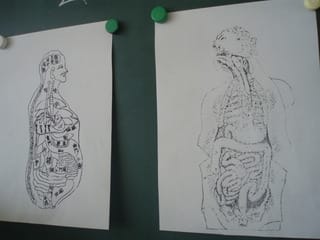
子どもたちは、こういう「気持ち悪い(?)」絵が大好き。
盛り上がる。
どちらも医学書であることを説明した後
=======================
もし自分が手術をしてもらう場合、
どちらの医学書を使って手術してもらいたいか
=======================
と発問した。
子どもたちは、「解体新書」を選択した。
このように、江戸時代後半、「医学」が進歩してきたことを確認し、
その他にも様々な学問が発達していったことを伝える。
子どもたちは自然に学習課題を設定する。
■■■■■■■■■■■■■■■
新しい学問は、世の中に
どのような影響を与えたのか
■■■■■■■■■■■■■■■

杉田玄白を紹介し、オランダの医学書を翻訳していった苦労を調べる。
「フルヘッヘンド」(←ターヘルアナトミアには、なかったという説もある)から、
「盛り上がる」=「鼻・胸」=「落ち葉の集まり」
などの説明で、当時の苦労を読み取る。
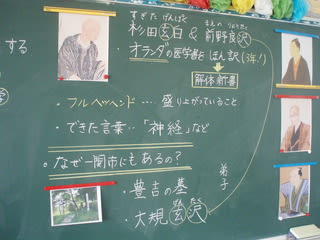
そして、解剖の見学の図から、日本で初めて「腑分け」をしたことについて調べる。
すると、子どもたちが
==================
先生、(春に行った)市の博物館で
解体新書が展示されてましたよね
==================
と言ってきた。
そこで、なぜ、一関市と解体新書がつながっているのかを
説明した。
一つは「豊吉の墓」

市内にあり、「腑分け」をされた罪人の墓だ。
日本の歴史の中でもかなり早い段階で腑分けを行った場所であり、
そんな場所が身近にあったことを子どもたちは驚いていた。
もう一つは「大槻玄沢」
一関市の有名人、大槻三賢人。

医者である玄沢は、師匠の杉田玄白、前野良沢の字を一字ずつもらって
「玄沢」と名乗っている。
その辺りは「地域教材」の良さ。
子どもたちの食いつきも良かった。
その後
医学の他にどんな学問が広がったかを調べ学習。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
・本居宣長=国学(古事記伝)
・高野長英=蘭学(幕府の政策を批判)
・伊能忠敬=天文学(測量で日本地図を作製)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
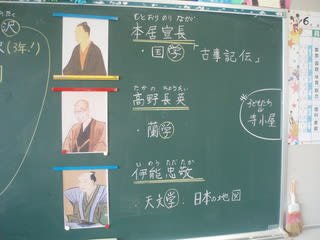
ただ、調べるだけでは定着しないので、
エピソードとともに説明。
・高野長英が奥州市出身で、液体で顔を焼いて整形したこと
・伊能忠敬は50歳を過ぎてから勉強を始め、海岸線をひたすら歩いたこと
などは、子どもたちは興味津々で聞いていた。
エピソード記憶で、しっかり定着を図りたいと思った。
準備や教材研究が若干足りない1時間だったが、なんとか流れて、良かった。










