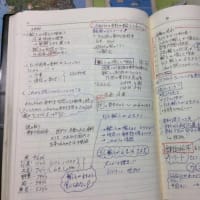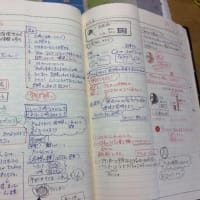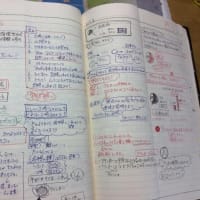豊臣秀吉の学習。
豊臣秀吉の生い立ちについてエピソードを紹介し、
興味を持たせたところで、課題提示。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
秀吉は、どのような国づくりを
行ったのだろう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ひととおり、予想させた後、追究の時間。
まずは、検地尺の実物大模型を提示。

これがなんだか分かれば、秀吉の国づくりの目的がわかるよ
と煽る。
そして、一体何をする道具なのかを予想させる。
子どもたちはいろいろな意見を出すが、
どうやら「定規じゃないか」という考えに収束する。
============================
では、この定規が使われていることがわかる資料を
教科書から探しましょう
============================
子どもたちは、検地の様子(想像図)の資料を探し当てる。
そこから、資料の読み取り。
=========================
田んぼの大きさが違う
定規を使って測っている
役人がいる
農民が土下座している
ひもで何かを測ってい
==========================
など、とにかく沢山の情報を読み取る。
そこから、秀吉の検地について
・どんなものだったのか?
・なぜこんなことをしたのか
ということをメインに調べさせる。
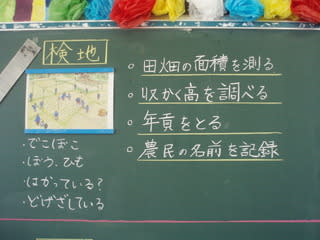
=========================
・全国に家来を派遣して村ごとに検地を行ったこと
・田畑の面積を測ったこと
・土地の善し悪しや収穫高を調べたこと
・耕している農民の名前を記録したこと
=========================
を子どもたちはまとめた。
次に「刀狩」の想像図を提示。

このイラストから、どんなことを行っているのかを想像させ、
そして調べ学習。
内容とその目的を中心に調べさせた。
====================
・農民が田畑を捨てることを禁じたこと
・農民が一揆を企てることを禁じたこと
・農民が武士や町民になることを禁じたこと
=====================
などを子どもたちはまとめる。
なおかつ、メインの
「刀や鉄砲をとりあげた」
ということに関しては、実物を提示。

模造刀の切っ先や、火縄銃の銃口を子どもたちに向けると、やはり教室に緊張感が走る。
この武器を農民たちや寺社が当然のように持っていたことを説明。
(この詳しい話は、昨年度センターで同僚の先生から教えていただいた。)
秀吉が刀狩を行った必然性についても理解をさせる。
最後に、秀吉の朝鮮出兵について触れ、学習のまとめへ。
課題は
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
秀吉は、どのような国づくりを
行ったのだろう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
だった。
そこで、まとめとして秀吉の目指した国づくりを
~~な国
ということでまとめさせた。

前時の信長で調べた
・戦争
・しくみ
・外国
の観点で、子どもたちは自分の言葉でまとめていた。
ここで45分が終了。
※
いろいろと途中で迷いがあったが、子どもたちの反応から見ても
今回はしっかり流れた授業であったと思う。
本当はいろいろと言いたいこと(思ったこと)がある。
この場面は昨年度、研究の対象として授業をした場面だった。
メインのところをガラッとかえて授業をした。
(分かる方は本当に分かると思う)
その点で、様々なことを考えた。
一言で言えば、
「自分の力不足を改めて痛感した」ということである。

豊臣秀吉の生い立ちについてエピソードを紹介し、
興味を持たせたところで、課題提示。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
秀吉は、どのような国づくりを
行ったのだろう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ひととおり、予想させた後、追究の時間。
まずは、検地尺の実物大模型を提示。

これがなんだか分かれば、秀吉の国づくりの目的がわかるよ
と煽る。
そして、一体何をする道具なのかを予想させる。
子どもたちはいろいろな意見を出すが、
どうやら「定規じゃないか」という考えに収束する。
============================
では、この定規が使われていることがわかる資料を
教科書から探しましょう
============================
子どもたちは、検地の様子(想像図)の資料を探し当てる。
そこから、資料の読み取り。
=========================
田んぼの大きさが違う
定規を使って測っている
役人がいる
農民が土下座している
ひもで何かを測ってい
==========================
など、とにかく沢山の情報を読み取る。
そこから、秀吉の検地について
・どんなものだったのか?
・なぜこんなことをしたのか
ということをメインに調べさせる。
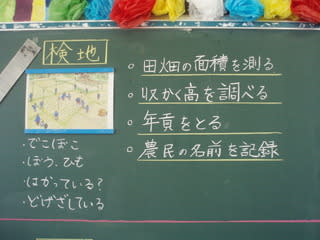
=========================
・全国に家来を派遣して村ごとに検地を行ったこと
・田畑の面積を測ったこと
・土地の善し悪しや収穫高を調べたこと
・耕している農民の名前を記録したこと
=========================
を子どもたちはまとめた。
次に「刀狩」の想像図を提示。

このイラストから、どんなことを行っているのかを想像させ、
そして調べ学習。
内容とその目的を中心に調べさせた。
====================
・農民が田畑を捨てることを禁じたこと
・農民が一揆を企てることを禁じたこと
・農民が武士や町民になることを禁じたこと
=====================
などを子どもたちはまとめる。
なおかつ、メインの
「刀や鉄砲をとりあげた」
ということに関しては、実物を提示。

模造刀の切っ先や、火縄銃の銃口を子どもたちに向けると、やはり教室に緊張感が走る。
この武器を農民たちや寺社が当然のように持っていたことを説明。
(この詳しい話は、昨年度センターで同僚の先生から教えていただいた。)
秀吉が刀狩を行った必然性についても理解をさせる。
最後に、秀吉の朝鮮出兵について触れ、学習のまとめへ。
課題は
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
秀吉は、どのような国づくりを
行ったのだろう
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
だった。
そこで、まとめとして秀吉の目指した国づくりを
~~な国
ということでまとめさせた。

前時の信長で調べた
・戦争
・しくみ
・外国
の観点で、子どもたちは自分の言葉でまとめていた。
ここで45分が終了。
※
いろいろと途中で迷いがあったが、子どもたちの反応から見ても
今回はしっかり流れた授業であったと思う。
本当はいろいろと言いたいこと(思ったこと)がある。
この場面は昨年度、研究の対象として授業をした場面だった。
メインのところをガラッとかえて授業をした。
(分かる方は本当に分かると思う)
その点で、様々なことを考えた。
一言で言えば、
「自分の力不足を改めて痛感した」ということである。