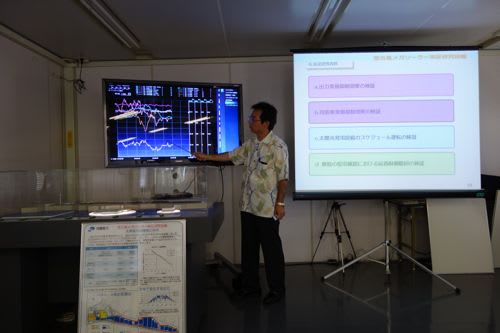いよいよ、宮古島視察も三日目、最終日を迎えました。
今日の視察は、宮古島メガソーラー実証研究設備がメイン。それと共に、宮古島市が取り組んでいる環境モデル都市、「エコアイランド宮古島」の推進についてもお話を伺い、私たちが今、取り組みを進めているスマートグリッドの今後の展開に向けた参考にさせていただこうという趣旨です。
宮古島市長表敬
この日、まずは宮古島市役所を訪問し、下地市長にご挨拶。今回の視察訪問の目的と内容をご説明した上で、昨日の下地中学校訪問の成果についてご報告。さらに、今後の再生可能エネルギーの拡大に向けて、宮古島市の取り組み成果が大変重要な意義を持つことお話しながら、意見交換をさせていただきました。その中で、私から特に、今後、改正沖縄振興特措法に基づく10年間の沖縄振興計画の実行にあたり、離島を含めた「均衡のとれた発展」を実現することが大変重要であることや、そのために情報通信基盤やサービス網の整備を確保して、行政、医療、教育、環境・エネルギーといった分野で利活用を促進しながら、島民の生活や産業、子どもたちの豊かな教育を支えていく必要があることをお話しました。
 (市長室で、下地宮古島市長と一緒に)
(市長室で、下地宮古島市長と一緒に)
ちなみに、 市長さんとの写真で、私の後ろに写っているポスター、何のポスターか分かりますか? これ、10月1日から始まるNHKの連続テレビ小説「純と愛」のポスターなんですが、舞台が宮古島なんです! すでにNHKのサイトには、あらすじや動画も含めてたくさんのコンテンツが載せられています。ぜひご覧いただいて、宮古島の魅力を堪能して下さい!
エコアイランド宮古島
さて、市長さんとの会談に続いて、市の企画政策部・エコアイランド推進課の皆さんから宮古島市の取り組みについてご説明をいただきました。離島県・沖縄のさらに離島に位置する宮古島では「地産地消」による資源循環を確立することが必要であって、さらに自然環境への負荷低減や、地場産業の育成による雇用の創出にも取り組まなければいけないということで、これらの実現を目的とした「エコアイランド宮古島」宣言を2008年3月に行ったということです。2009年1月には、全国で13の自治体が指定されている「環境モデル都市」の一つに選定され、行動計画を策定してCO2の削減にも取り組んでいます。
そして、具体的な取り組み事例をお聞きして、そのメニューの豊富さに驚きました。詳細にはこちらをご覧いただきたいと思いますが、例えば:
- 「さとうきび等による自給自足のエネルギー供給」・・・サトウキビの精糖残渣を原料とするバイオエタノール燃料製造プロジェクト。併せて資料や液肥の製造も。
- 「クリーンエネルギーによるCO2フリー化」・・・沖縄電力との連携による離島マイクログリッド実証事業。
- 「21世紀環境共生型住宅(エコハウス)の整備事業」・・・宮古島の伝統的住宅に自然エネルギー技術を組み合わせたエコハウスを整備する。
- 「宮古島市全島エネルギーマネジメントシステム(EMS)実証事業」・・・再生可能エネルギーの導入量や導入効果の拡大を確実にするため、沖縄県とも連携して全島のエネルギーを最適制御するシステムの実証を行う。
- 「来間島再生可能エネルギー100%自活実証事業」・・・来間島で、全世帯の消費電力に相当する規模の太陽光発電や(みなし)風力発電および蓄電池を設置して、全島をカバーする来間EMSを基盤に再生可能エネルギー比率100%の達成をめざす。
などなど。すごいでしょう? まだまだ時間はかかるでしょうし、課題も多いと思いますが、これらの目標が達成されてくると、これが沖縄県の他の離島や、全国各地の離島および小規模自治体にも波及していく効果ががあるのではないかと思います。
 (宮古島市・エコアイランド推進課の皆さん。とても熱心に内容をご説明いただきました)
(宮古島市・エコアイランド推進課の皆さん。とても熱心に内容をご説明いただきました)
離島マイクログリッド実証事業
さて、上記の宮古島市の具体的取り組み事業の中にある「沖縄電力との連携による離島マイクログリッド実証事業」を視察するのが、この日のメインの目的です。市役所を離れて、車で宮古島の南東の端の方に向かっていくこと約20分。到着したのが、沖縄電力の「宮古島メガソーラー実証研究設備」です。全体像はこんな感じ(写真:沖縄電力ホームページより):

到着後、まずは沖縄電力の担当の方から、宮古島の発電設備の現況や、実証研究の内容についてご説明をいただきました。
現在、宮古島には、宮古発電所(ディーゼル=19,000kW)、宮古第二発電所(ディーゼル=40,000kW、ガスタービン=15,000kW)、宮古風力6号機(風力=600kW)、狩俣風力1・2号機(風力=900kW×2基)、サデフネ風力1・2号機(900kW×2基)があります。
系統規模が約50,000kWと小さいので、再生可能エネルギーの出力変動の影響を受けやすく、これをどのように安定化させるかが重要なポイントになるわけですね。そこで、この実証設備では、太陽光発電設備4,000kWに、同規模の蓄電設備(NAS電池)を加えて、太陽光発電を大量に導入しようとした場合の系統への影響を把握し、太陽光発電と蓄電池の運用データを収集・解析しながら、系統安定化を図るための研究を実施しているわけです。実証実験のより具体的な説明は、こちらをご覧いただきたいとおもいますが、施設内には、一般家庭100軒、学校等4軒が接続する配電系統を模擬できるシステムが導入されていて、これによってデータが得られるようになっていました。
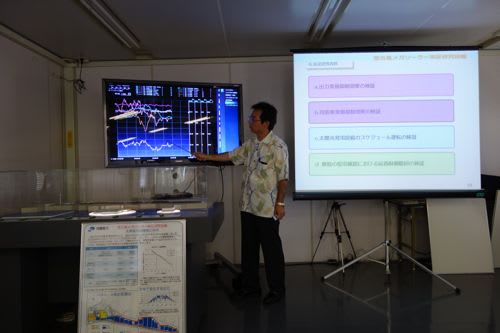
これが風車(二基)と太陽光パネルです。太陽光パネルは、三つのメーカーの特性の違うパネルが設置されていて、総計は21,716枚になるそうです。「台風は大丈夫なの?」とお伺いすると、最大瞬間風速80メートルぐらいでも大丈夫だとか。約10年前の大型台風では、風力発電の支柱がぽっきり折れてしまったそうですが、これは停電によって向きの制御が効かなくなり、かぜをもろに受けてしまったからだったとか。今では、バックアップ電源が準備されているので、強風にも耐えられるのだということです。



この実証研究で得られた成果は、経済産業省を通じて他の事業者等にも公表され、利用可能になるということです。これだけ大規模の実証実験を行っている施設もなかなかないので、今後の全国的な再生可能エネルギーの大量導入に向けて、ぜひ成果を出して広く公表していっていただきたいと思います。
最後に、本日ご案内いただいた沖縄電力の担当者の皆さんと記念写真をパチリ。皆さん、大変お世話になりました!