 浅堀木城西遠景
浅堀木城西遠景
 丘陵の東裾にある堀跡
丘陵の東裾にある堀跡
 南から西に向かって伸びる空堀
南から西に向かって伸びる空堀
 西端当りの土塁
西端当りの土塁
 同空堀
同空堀
 丘頂は自然地形に近い
丘頂は自然地形に近い
 浅堀木城南遠景
浅堀木城南遠景
| 城名 |
| 浅堀木城 |
| 読み |
| あさほりきじょう |
| 住所 |
| 松阪市上川町浅堀木 |
| 築城年・築城者・城主 |
| 不明 |
| 形式 |
| 平山城 |
| 遺構 |
| 空堀(丘陵の東裾から南西裾まで約170m程の空堀跡がある)土塁、曲輪 |
| 規模 |
| 空堀の位置と地形から東西200m×南北180m程か。 |
| 標高 42m 比高 26m |
| 歴史 |
| 敵が攻めてくるので朝までに堀を造ったといわれこの名が付いたといわれている。 |
| 書籍 |
| 三重の中世城館 |
| 環境 |
| 櫛田川下流域の平野部を直近にする場所である。 |
| 現地 |
| 北に開けた平野部から見ると他の丘陵で隠されるように少し奥まったいい位置にある。 |
| 東麓にほぼ直線で幅4m、深さ1m弱の堀が見られる。南から西側に向かって続く。 |
| 北側は現在道となっている所が堀であったともいわれている。 |
| 丘頂は自然地形に近く、あまり平坦ではない。 |
| 開墾地には弥生土器片が散布している。 |
| 考察 |
| 神山城の支城という考え方は疑問が残る。城の造りが神山城のそれとあまりに違うこと、また神山城から出て立利縄手や大口付近で戦ったという記録は残るが浅堀木の名前は出てこない。 |
| 感想 |
| 伊勢平野の中勢部の一角を治める荘園領主の詰め城であった、というのが一番分かりやすい。 |
| 名前の由来となっている「敵が攻めてくるというので、、、」の敵とはどういう敵であったのだろうか。 |
| 空堀の造成は間に合ったのだろうか。敵は来て、戦いはあったのだろうか。結果はどうだったのだろうか。詳しいことは分かっていない。ただ空堀が残っているだけである。 |
|
地図 |










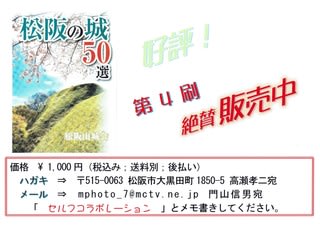

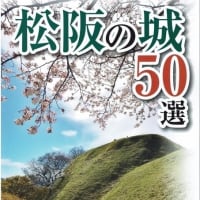

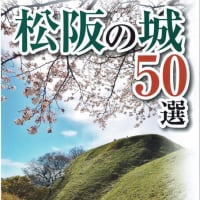
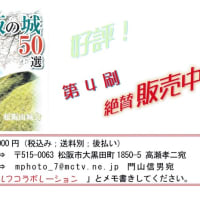




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます