達磨城
| 城名 | 達磨城 |
| 住所 |
三重県松阪市東黒部町
|
| 築城年 | 北畠具房の命令で神戸・西黒部の検断職を安堵された時代 永禄十一年(1568)十二月か |
| 築城者 | 佐波九郎左エ門=澤氏(奈良宇陀郡澤村領主) |
| 形式 | 平城 |
| 遺構 | 無し |
| 規模 | 遺跡の範囲;南北150m × 東西525m |
| 城主 | 初代=佐波兵部大輔房満 |
| 二代=佐波九郎左衛門之廣 | |
| 三代=佐波九郎左衛門之道 | |
| 標高 | 0m |
| 歴史 | 北畠具房の命で沢(後に佐波)兵部大輔房満に神戸・西黒部の検断職を安堵された。このとき達磨山に館を構え城主となる。 |
| 永禄12年(1569)8月27日織田信長、国司北畠をせめる、このとき、九郎左エ門数代後の佐波一族は佐波洲に陣を取り、織田勢を防いだ。 | |
| 経緯 | 天正五年(1577)北畠滅亡後、信長より旧領の安堵を受け隠居して大和に帰る。折柄筒井氏大和を統一するに際し摩下となる。 |
| 子、之廣は秀吉に仕え蒲生氏郷の戸木城攻めに参加している。その子之道は藤堂家に仕え一志郡で千石を与えられたが大坂の陣で討死したという。 | |
| 佐波の館跡は数軒の屋敷となり、約三反歩の地が認められる。尚、付近には郎党の屋敷跡が伺えるが、定かではない。 | |
| 書籍 | 黒部史(ベルネットフレンドより) |
| 現地 | 西に櫛田川、北に大口港やがら崎と海からの防御に備えた城。現在は松阪市の発掘調査により「永山遺跡」として登録されている。 |
| 考察 | 現在の遺跡を見ると周辺の田より一段高く台地状になっているが造成されたものと思われ遺構らしきものはない。平面での遺跡の形は歪でありこれらも当時を偲ばせるものでは無いと思われる。 |
| 感想 | この地に達磨城という城があり、一時の歴史の中で北畠氏を支え武士たちが闊歩し多くの人たちの歴史を紡いだと想像するにとどまる。できればもう少し裏付けを取りたいものである。 |
| 参照 | 伊勢 松名瀬の佐和氏 http://blog.goo.ne.jp/sawa-001_001/c/4ec032e7cb9d0cf3bf19a8b8a05890d6/1 |
| 武将家一覧 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/uda_sawa.html |
地図;










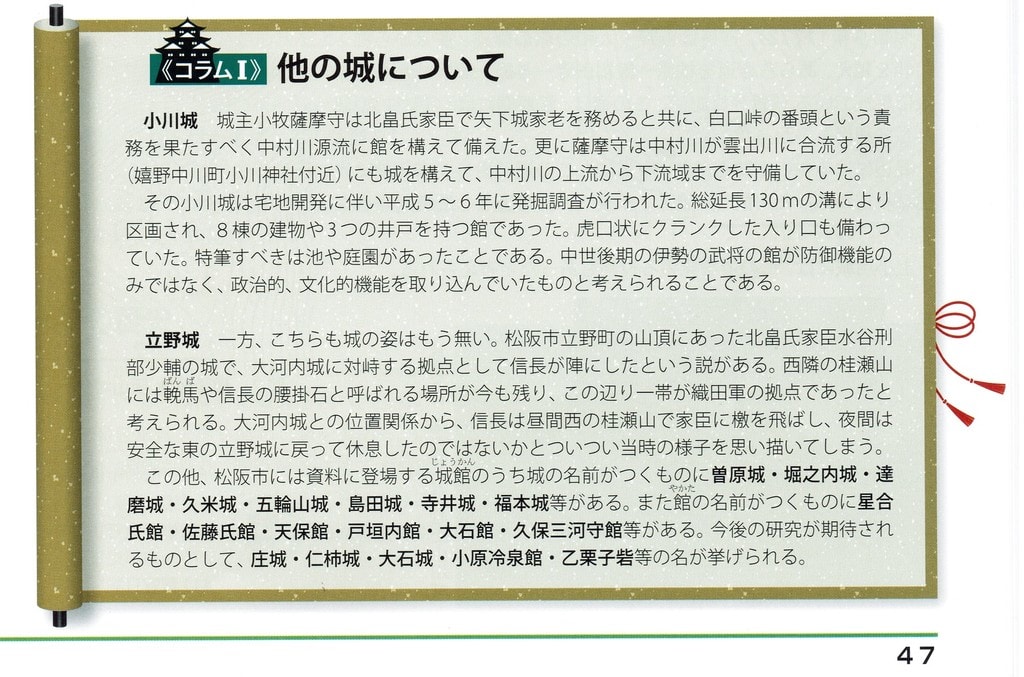

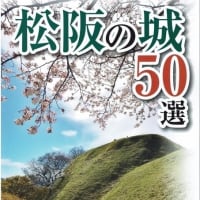

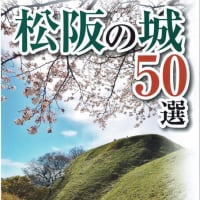
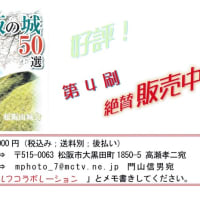




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます