|
城名 |
| 岩内城 |
| 住所 |
| 松阪市岩内町 |
| 築城年 |
| 室町時代 |
| 形式 |
| 山城 |
| 遺構 |
| 曲輪、堀切、帯郭、竪堀 |
| 規模 |
| 東西100m×南北80m 兵の数約500人 |
| 城主 |
| 岩内主膳正光安(北畠13人衆の一人) |
| 標高 |
| 180m |
| 比高 |
| 80m |
| 歴史 |
| 北畠は迎撃態勢の一環として岩内城には岩内御所一族(岩内主膳正光安)兵500を置き、信長の侵攻に対抗しようとした。信長は近隣の岩内城と阿坂城に降伏勧告(和睦案)を出した。岩内氏は国司の一族であるため回答を保留。「大河内城の考え次第である」とした。(追記;中世城館と北畠氏の動向より)信長公記に「滝川左近人数入れ置き是よりわきわきの小城へはお手遣いもなく直ちに奥へ、、とある。小城というのは岩内城、伊勢寺城、奥野城、岡ノ谷城、白山城辺りを言っているのでしょう。つまり北畠側から抵抗が無かったので、そこへ軍勢を遣ることもなく、まっすぐ大河内城へ向かったということです。(8月27日) |
| 経緯 |
| 岩内城は多気郡明和町にあったが大河内城の出城として松阪市の天ケ峰に移された。岩内光安の子息が2歳の時、北畠具親の養子となり北畠に改称 |
| 書籍 |
| 三重の中世城館の不明城館ページ |
| 一族 |
| 岩内御所 |
| 岩内氏の系譜は不明。顕豊-政治と続いた後、政治の戦死により一時廃絶。永正9年に再興される。 |
| 岩内鎮慶(?) 父は北畠材親か?母は不明。岩内家を再興。木造俊茂から白粉代官職を奪った、岩内某と推定される。久我家木造庄の年貢未納に対し大御所具教とともに対応。 |
| 岩内国茂(?) 父は岩内鎮慶、母は不明。 |
| 岩内具俊(?) 父は岩内国茂、母は不明。 |
| 岩内光安の子息が2歳の時、北畠具親の養子となり北畠に改称した。 |
| 後、具親敗走の時に光安は田丸城で殺され家は断絶した。 |
| 光安の子息「玉千代」は北畠具親に養われ、成人し北畠荘門光吉と名乗り、北畠の遺臣に守られて伊勢山田に住まいした。 |
| 現地 |
| 瑞巌寺跡と墓地の中間位に西登城口がある。金毘羅宮入口のの看板がある。突然、急坂となるが尾根にたどり着くまでの距離は少ない。 |
| 尾根にたどり着くと石垣で造成された金毘羅宮がある。この辺りから城域と思われる。 |
| 堀切ではなさそうな鞍部を超えてしばらくで頂部に着く。その尾根は細く大勢の人数は留まれない。 |
| しかし、曲輪は主郭、帯郭とそれぞれ明確である。主郭は狭いながらも2段に分けている。 |
| 北側に尾根として続く主郭の切岸は当時の様子を物語っている。帯郭と竪堀がそこを守っている。 |
| 尾根の先は堀切が大小2連ありどちらも明確である。上部の堀切は岩や石垣で造られている。 |
| この二つの堀切より北へ標高をたどるが城としての構造物は無いと判断した。一部道のようなものと未完成な削平地のようなものはあるがこれは後世の山仕事に関係するものと思う。 |
| 主郭の南側を下るとこの城で一番大きい堀切がある。こちらは山の麓からの敵を防御する位置にある。 |
| その先には見張台とも思える小さな削平地がある。城の範囲はここまでと思われる。 |
| その下に大きな削平地があるが他の削平地よりキレイに残っているので後世のものと考えた。大日さんとして今も祀られている。 |
| 松阪遺跡地図にも三重の中世城館にも著わされていない山城の発見である。これは松阪山城会の松本会長が種々の情報を元に自ら足を運んで確定されたものである。 |
| 感想 |
| 岩内町にはもう一つの山城がある。ここより南東1Kmの山上にある天ヶ城である。過去に多数の学者の方々が岩内城ではないかと考えられた所だ。 |
| 両城に関して記事が重複するのはそのためである。現状では岩内城と天ヶ城に分類整理することは困難である。 |
| この二つの山城は造られた時期が異なるのであろう。天ヶ城が古く、岩内城が新しいものと考える。 |
| このような発見はおそらくこれからもあるのだろう。なんと山城の興味は尽きないものだ。 |
|
地図 |











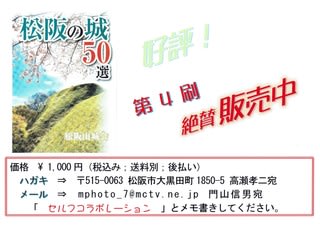

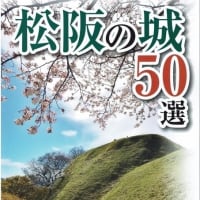

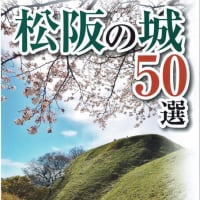
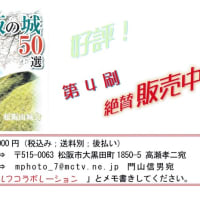




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます