| 城名 |
| 野呂氏館 |
| 住所 |
| 津市芸濃町椋本 |
| 築城年 |
| 時期は、出土した常滑焼大甕の特徴によって16世紀後半のものと考えられる。 |
| 築城者 |
| 野呂氏 |
| 形式 |
| 居館 |
| 遺構 |
| 郭、土塁、空堀 |
| 蒸風呂の燃焼部と考えられる炉遺構は県内でも初めての発見。 |
| 規模 |
| 東西80m× 南北90mほどの方形(三重の中世城館) |
| 東西300m×南北200m(日本城郭体系) |
| 城主 |
| 野呂民部少輔 |
| 一族 |
| 雲林院出羽守の家臣 |
| 標高 80m 比高 15m |
| 歴史 |
| 雲林院氏を亡ぼすために織田信包が謀って、天正8年(1580)に雲林院氏によって野呂氏は滅ぼされた。 |
| 経緯 |
| 雲林院氏の家臣であった野呂氏の居館とされるが、詳しいことは不明 |
| 書籍 |
| 三重の中世城館 日本城郭体系 |
| 環境 |
| 椋本の河岸段丘の縁に築かれた。南に安濃川と安濃の平野部を望み、西に城主、雲林院氏の居城を望む。 |
| 開発前の様子(三重の中世城館より) |
| 館は低い台地にあって、深い堀を廻りにめぐらし、更に内堀を巡らしている。現在は、西に巾3mの堀があり、東は巾6m、深さ5mの空堀となっており、北側にも空堀がある。北西部は宅地化され、館跡は高さ2mの土塁にかこまれ、その部分の面積は360坪で、畑となっている。 |
| 開発前の様子(日本城郭体系より) |
| この館は最西部の郭には巾10m、深さ5m近い外堀を伴い、また、中央部の郭には見張台状のものもあって、丘城としての構えを見せていて交通の要衝を押える室町時代の土豪の居館にふさわしい規模のものである。 |
| 現地 |
| 前出の開発前の様子より開発が進み、北側の土塁は削られ堀も埋められ見張台状のものは削られ、記述の様子は現地で確認することが困難である。 |
| 開発が行われている西側地域より、東方向の藪の中に潜む郭、空堀、土塁などが現在でも確認することができるが、これらも野呂氏館に関係する遺構であると考えられ観察するに値する。 |
| 考察 |
| 三重県で初めての蒸し風呂の発掘は、当時の有様を知ることになり中世武士の日常を窺う上で指標になるといえる。 |
| 感想 |
| 「調査対象外の館跡中心部まで開発が進んでいったことで、堀や土塁の痕跡がほとんど残っていない状況となった。」こうやって、遺構はどんどん無くなっていく。 |
| 地図 |
<!-- 野呂氏館 -->












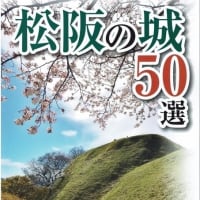

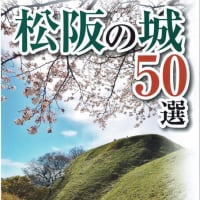
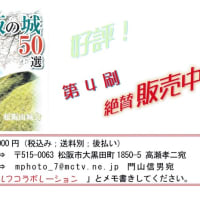




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます