







| 城名 |
| 南鮠川城 |
| 読み |
| みなみはいかわじょう |
| 住所 |
| 度会郡度会町鮠川662/富津 |
| 形式 |
| 丘城 |
| 遺構 |
| 土塁の一部 |
| 規模 |
| 内城田村史によると当時、東西30間、南北20間とあり、54×36m位ほ平地があったようだ。 |
| 城主 |
| 不明 |
| 標高 29m 川面からの比高 10m |
| 書籍 |
| 三重の中世城館 |
| 環境 |
| 宮川に面する河岸段丘の断崖にある。支流鮠川(はいかわ)が東側の急崖を創り出したようだ。まるで岬の突端の様相を現している。 |
| 「内城田村誌」によると「南鮠川の城、字浦の上なる渡船場の断崖上。東西30間。南北20間の平地にあり。 |
| 郷人これを城(じょう)と称す。蓋し(注1)砦跡ならん」とある。 |
| 昭和47年2月、城跡を縦断するように鮠川大橋が完成した。いまは土塁状のものがわずか数メートル残っている。 |
| 現地 |
| 宮川右岸の河岸段丘の縁に城はある。城から宮川へは行き来ができる。船着き場の様子が垣間みられる。 |
| ここで戦いをうんぬんという気配ではない。現地に来てそれが分かった。現在は土塁の片割れが残るのみであるがロケーションは当時の雰囲気を残していると思える。 |
| 考察 |
| 山城ではなく、居館でもない。渡船場で物資や通行人を抑える関所という位置付けが一番近いと思われる。 |
| ここより3km下流の宮川左岸に牧戸城があるが、河岸段丘の縁に造られる城砦の2例となる。 |
| 感想 |
| 鮠川大橋記念碑に長年の渡し舟、、、という行があるように結構川幅のある宮川のこの場所では渡し舟の運航は大変であったと想像できる。 |
| 宮川を渡る関料をとったり人や物の検査をしたり舟自体を守る役目があったりという気がする。 |
| 注1 |
| 蓋し:(けだし) 物事を確信をもって推定する意を表す。まさしく。たしかに。思うに。 |
| 地図 |










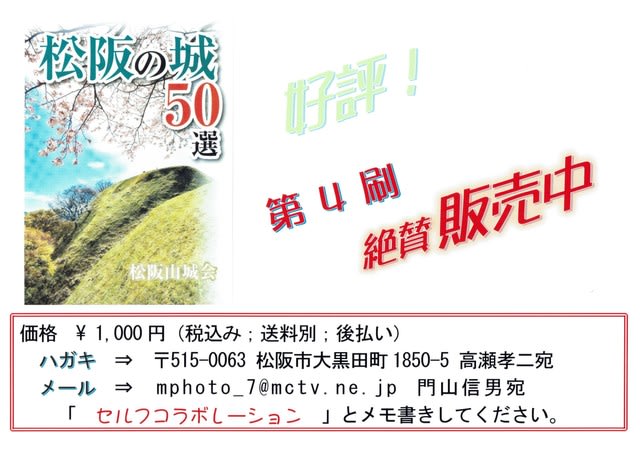

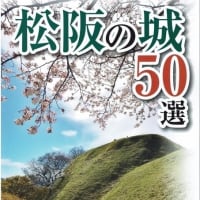

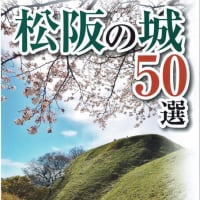
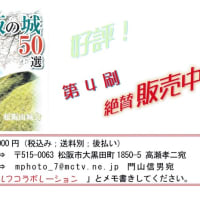




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます