すでに四条通には祇園祭の山鉾が並び立ち、鉾の曳き初めも終わってるが、
先日、四条烏丸へ行って「鉾建て」を見て来た。
雨が降るかと思っていたが曇り空だったので行く気になった。
雨だと傘を差しながら写真を撮るのがとても難しい。
だから雨が降らないと判断して行くことにしたのだ。

去年は足の甲を骨折していたため自由に歩けず、
祇園祭も行かなかったが、
今年こそ現地へ行って少しは山鉾を見ておきたい。
腰の痛みはますます酷いが(>_<)、それでも見たい。
すぐ近くで(地下鉄で一駅)鉾が建っているのだもの。
そんなわけで地下鉄で四条烏丸まで行き、山鉾町へ向った。

行ったのは四条烏丸の西側、
まず四条烏丸の西北側にすぐ見える函谷鉾。
四条通に飾られている提灯に祇園祭のムードが高まっていた。

行った時はすでに函谷鉾は建ち上がっていて、四条通に聳え立っていた。
木材がむき出しのままで飾り付けられていない鉾の様子は、
鉾建ての時ならでは。
この時しか見られない。
もちろん飾り付けられて完成した山鉾が本来の山鉾であることは言うまでもないが、
まだ飾られていない、骨組みがむき出しの、
木の質感がそのまま見られる鉾も好きなのだ。
塗りを施されていない白木のようなものと言えば良いのか。


鉾をまさに組み立てている最中に行けば、
作事方の仕事が間近に見られる。
意外と若いお兄さんたちが真剣に、何ごとか合図をしあったり、
時間を気にせずにただ黙々と仕事をしている。
巨大な鉾の屋根に上りつつ組み立てている職人たちの迫力には
圧倒されるばかりだった。
間近で見ると、改めて圧倒されてしまった。
それだから鉾建てが好きなのだった。
四条通を室町通りまで歩き、菊水鉾へ行く。
ここはまだ鉾が横倒しになっていて鉾上げはまだだった。


鉾は横倒しのまま土台に真木を差し込み、飾り付けてゆく。
そうして真木(しんぎ)の飾り付けが済むと鉾を起こして立ち上がらせる。
骨組みだけの鉾を見るのも面白いのだ。
菊水鉾の鉾頭(ほこがしら)も間近で見られる。
菊水だから文字通り菊の形の鉾頭である。


釘を使わず、縄だけで組み上げてゆく「縄がらみ」を見られるのも、
鉾建ての時のみだ。
完成すれば懸装品に隠れてしまうからだ。
縄がらみの美しさは例えようもないと思っている。
作事方の職人の技が込められているし、
鉾建ての最中に行けば、その技が間近で見ることが出来る。

四条通に戻ったら、月鉾の立ち上げの真っ最中だった。
というか、ほぼ立ち上がっている時だった。
通りの反対側から見たので、遠くからになってしまった。
立ち上げは近くで最初から見たかったが、立ち上げは待ってくれない。
途中からでもいいや、と思い、
必死にシャッターを押した。

音頭取りの人がエンヤラヤーと言いながら扇子を振りながら指図していた。
もう少し早く来ていれば始めから見られたのに、と後悔したが、
立ち上げはタイミングで、いつ、どの鉾が何時に立ち上るかは予想できない。
現場へ行ってみないことには分からないのだ。
毎年行っていると大体この鉾は何時ころ立ち上がるか、は分かるのかもしれない。
まだまだ修行が足りない(>_<)。

月鉾が完全に立ち上がると、周囲のあちこちのギャラリーから拍手が自然と起こる。
自分もスマホを持ちながら一生懸命拍手した。
月鉾の鉾頭までの高さは隣に聳えるビルよりまだ高い。( ゚Д゚)
鉾建ても一種の見世物というか、祇園祭の見どころの一つなので、
こうして周囲で見ているみんなで鉾建てを見守るのもまた、楽しい。

新町通まで行くと、すでに雑貨店では山鉾のミニチュアや団扇を売っていた。
祇園祭ムードがすでに盛り上がってた。

新町通に建つのは放下鉾。
私の凄く好きな鉾のひとつである。
ここはまだ骨組みの縄がらみも完成しておらず、途中だった。
新町通はいつも鉾建ても曳き初めも四条通の鉾より一日遅い。
放下鉾の会所は古い会所の形を残していて
京都市の指定有形文化財に指定されているほど、価値のある町家だ。
会所の前には案内の看板も出ている。

宵山へ行けるかどうか分からないが、行けたならまた入りたい会所だ。
2階は母屋から祇園祭時期のみ奥の蔵(土蔵)へ渡り廊下が渡される。
その光景が素晴らしく、毎年訪れたいと思ってしまうのだ。
今年は放下鉾は宵山では一般拝観者は搭乗出来ないことになったと
新聞に出ていた。
部材が江戸時代の200年くらい前のものをそのまま使っていたため、
古くなりすぎ、劣化していて搭乗に耐えられない可能性があるため、という。
(順次、新しい部材に取り換え中)
放下鉾は男性しか搭乗出来ないので自分はもとから入れないが、
そんなに古い部材をずっと使い続けていたとは、
改めて驚くばかりである。
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
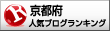 京都府ランキング
京都府ランキング
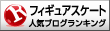 フィギュアスケートランキング
フィギュアスケートランキング
↓ブログ村もよろしくお願いします!
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
先日、四条烏丸へ行って「鉾建て」を見て来た。
雨が降るかと思っていたが曇り空だったので行く気になった。
雨だと傘を差しながら写真を撮るのがとても難しい。
だから雨が降らないと判断して行くことにしたのだ。

去年は足の甲を骨折していたため自由に歩けず、
祇園祭も行かなかったが、
今年こそ現地へ行って少しは山鉾を見ておきたい。
腰の痛みはますます酷いが(>_<)、それでも見たい。
すぐ近くで(地下鉄で一駅)鉾が建っているのだもの。
そんなわけで地下鉄で四条烏丸まで行き、山鉾町へ向った。

行ったのは四条烏丸の西側、
まず四条烏丸の西北側にすぐ見える函谷鉾。
四条通に飾られている提灯に祇園祭のムードが高まっていた。

行った時はすでに函谷鉾は建ち上がっていて、四条通に聳え立っていた。
木材がむき出しのままで飾り付けられていない鉾の様子は、
鉾建ての時ならでは。
この時しか見られない。
もちろん飾り付けられて完成した山鉾が本来の山鉾であることは言うまでもないが、
まだ飾られていない、骨組みがむき出しの、
木の質感がそのまま見られる鉾も好きなのだ。
塗りを施されていない白木のようなものと言えば良いのか。


鉾をまさに組み立てている最中に行けば、
作事方の仕事が間近に見られる。
意外と若いお兄さんたちが真剣に、何ごとか合図をしあったり、
時間を気にせずにただ黙々と仕事をしている。
巨大な鉾の屋根に上りつつ組み立てている職人たちの迫力には
圧倒されるばかりだった。
間近で見ると、改めて圧倒されてしまった。
それだから鉾建てが好きなのだった。
四条通を室町通りまで歩き、菊水鉾へ行く。
ここはまだ鉾が横倒しになっていて鉾上げはまだだった。


鉾は横倒しのまま土台に真木を差し込み、飾り付けてゆく。
そうして真木(しんぎ)の飾り付けが済むと鉾を起こして立ち上がらせる。
骨組みだけの鉾を見るのも面白いのだ。
菊水鉾の鉾頭(ほこがしら)も間近で見られる。
菊水だから文字通り菊の形の鉾頭である。


釘を使わず、縄だけで組み上げてゆく「縄がらみ」を見られるのも、
鉾建ての時のみだ。
完成すれば懸装品に隠れてしまうからだ。
縄がらみの美しさは例えようもないと思っている。
作事方の職人の技が込められているし、
鉾建ての最中に行けば、その技が間近で見ることが出来る。

四条通に戻ったら、月鉾の立ち上げの真っ最中だった。
というか、ほぼ立ち上がっている時だった。
通りの反対側から見たので、遠くからになってしまった。
立ち上げは近くで最初から見たかったが、立ち上げは待ってくれない。
途中からでもいいや、と思い、
必死にシャッターを押した。

音頭取りの人がエンヤラヤーと言いながら扇子を振りながら指図していた。
もう少し早く来ていれば始めから見られたのに、と後悔したが、
立ち上げはタイミングで、いつ、どの鉾が何時に立ち上るかは予想できない。
現場へ行ってみないことには分からないのだ。
毎年行っていると大体この鉾は何時ころ立ち上がるか、は分かるのかもしれない。
まだまだ修行が足りない(>_<)。

月鉾が完全に立ち上がると、周囲のあちこちのギャラリーから拍手が自然と起こる。
自分もスマホを持ちながら一生懸命拍手した。
月鉾の鉾頭までの高さは隣に聳えるビルよりまだ高い。( ゚Д゚)
鉾建ても一種の見世物というか、祇園祭の見どころの一つなので、
こうして周囲で見ているみんなで鉾建てを見守るのもまた、楽しい。

新町通まで行くと、すでに雑貨店では山鉾のミニチュアや団扇を売っていた。
祇園祭ムードがすでに盛り上がってた。

新町通に建つのは放下鉾。
私の凄く好きな鉾のひとつである。
ここはまだ骨組みの縄がらみも完成しておらず、途中だった。
新町通はいつも鉾建ても曳き初めも四条通の鉾より一日遅い。
放下鉾の会所は古い会所の形を残していて
京都市の指定有形文化財に指定されているほど、価値のある町家だ。
会所の前には案内の看板も出ている。

宵山へ行けるかどうか分からないが、行けたならまた入りたい会所だ。
2階は母屋から祇園祭時期のみ奥の蔵(土蔵)へ渡り廊下が渡される。
その光景が素晴らしく、毎年訪れたいと思ってしまうのだ。
今年は放下鉾は宵山では一般拝観者は搭乗出来ないことになったと
新聞に出ていた。
部材が江戸時代の200年くらい前のものをそのまま使っていたため、
古くなりすぎ、劣化していて搭乗に耐えられない可能性があるため、という。
(順次、新しい部材に取り換え中)
放下鉾は男性しか搭乗出来ないので自分はもとから入れないが、
そんなに古い部材をずっと使い続けていたとは、
改めて驚くばかりである。
↓ブログ村もよろしくお願いします!










