JARLのAWARDへの取組みは『ハムライフを長続きさせる』と感じます。DXばかりやっている方から見れば『JARLのアワードなんか・・・』という声をいただくこともあります。しかし、実際のところは『コツがわからなくて、QSLリスト作成がめんどくさい』のではないでしょうか。日頃の運用から、チェックリストを作成しておき、それを『そのままQSLリストに転用できるような設計』をしておけば、何にも面倒くささも感じないのですが。

【写真:WASA-HF(GLスクエア)のチェックリスト。そのまま申請に使用】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆FT8を漠然と運用していても、飽きるリーチが短くなるだけです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いかに、長続きさせるか・・・を、真剣に考えましょう。
特に『再開組』の方に、強くお伝えしたいのです。
なぜならば、数十年のブランクがあって再開したという既成事実があります。
ムセンに飽きたり、ムセンより楽しい遊びを見つけたり、
あるいは、学業、就職、結婚等々、さまざまな理由で、
アマチュア無線から遠のいていた『前科』があるわけです。
要は『ここの店は、長続きしない』という『潰れる店のジンクス』みたいなもん。
・ハムログ
・チェックリスト
日頃の運用から、この2つを連携させておく必要があります。

▲GLスクエアなどは、HFハイバンドを運用したら、必ず増えてくる
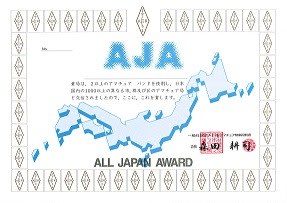
▲AJAも、市郡区すべてがカウントできるので、周波数別に管理
私がFT8/FT4を始めてまる3年、
現在10,000交信で得たJARLのAWARDは、次のとおりです。
AJD
JCC-100~600
WAJA(1,200)
AJA(1,700)
WASA-HF
ADXA-Half
ADXA などなど。
・7MHzでFT8を運用すれば、概ね10か月でJCC-500のWkdができました。
・ところが、JCC-600のWkdは1年半かかりました。
・そして、JCC-600のCfmは、2年ちょいかかりました。
・JCC-600からは、なかなか伸びない・・・。
多くのJA局がでている7.041MHzですら、こんな感じです。
ハイバンドに出ている局の中には、ハイバンドがNGになってくると、
7・10・14MHzに集中しますね。
ハイバンドがNGだから、自分の『居場所に戻ってくる局が多い』です。
運用局が多い≒コンディションがいい、というのは早計です。
単に『安定したバンドに戻ってくる』ということです。
そもそも、14MHz以下は太陽活動の影響を『さほど受けないバンド』です。
この『ミドルバンド』を駆使すれば、
DXがわんさかいるはずですから、DXCCを伸ばすにはもってこいだと思います。
早合点してもらっては困るのですが、
運用局が多い≒コンディションがいいのではなく、
ハイバンドより、空中状態が安定しているということです。
DXCCは伸びると思いますが、200~250エンティティで頭打ちでしょう。
340エンティティしかない上に、アマチュア無線をやっている人がいない島も。
グローバル運用も楽しいですが、
せっかくJARL会員ならば『JARLのAWARD』も並行して楽しめば、
面白味は倍増すると思います。
グローバル(DX)+ローカル(国内)=グローカル運用

▲DXCC入りより、難易度が高く感じた、JAを含むアジア30エンティティ。
ADXAも『特記』を付けて、
複数バンドでチャレンジすれば、運用への取組み方も変わってくるでしょう。
WASA-HFも『GLスクエアの管理やチェック』が不可欠ですし、
DXCCとは比較にならない数のスクエアを伸ばしていくのが楽しいです。
海上移動局も、GLスクエアが確認できれば『有効』です。
雑魚扱いしている『BY、YB』も『GLスクエアの宝庫』です。
私は、意図的に『北米狙い』を外しています。
USAは、世界トップのアマチュア無線家人口を誇っている『超雑魚』です。
しかし、人口密度が低いことから『北米と数局交信』すれば、
交信数と同数のGLスクエアが稼げることが多いです。
現在の生活パターンで北米を狙うのは、7MHzくらいです。
ハイバンドでの運用は『2024~2025年の楽しみ』に残しています。
ちょっとの工夫で、おカネをかけずに楽しむことも大事だと思います。
FT8・7.074MHzで『50W+HF40CLというモビホ運用』で、
WAC(六大陸州)ができたときは仰天しました。
LoTWでCfmできていますので、
JARLの代行申請を利用しようと、
申請書を作成中です。
AWARDは公的な認定証でもあります。
ハムログの上でWkd&Cfmを眺めていても仕方がないものです。
また、ARRLのページでDXとのCfm状況を眺めているだけというのも、
案外『むなしいものだな』と感じます。
やはり、公的機関の認定証を手にしたときの喜びはひとしおです。
JARLの決算書(JN-2023秋号・P18)を見ると、
事業収益の中の『賞典収益』という勘定科目には、
約3百万円が計上されています。
ここには代行申請も含まれていると考えられますが、
年間約3,000件弱のAWARD申請があると数字から読み取れます。
眺めているだけではなく、実際に賞状(認定証)を手にしてはいかがでしょう。
毎度おおきに。ほんじゃーね!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事は、表現と言論の自由に則ったエッセイで、
公人を除き、登場する個人・団体名は全て架空のものです。
※時事問題については、筆者個人の考えです。
※SNSなどの他サイトへリンクやリツイートはご遠慮ください。
※Twitter等、拡散性の高いSNSでのコメント合戦はお断りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright:(C)2023 Ota-Tadashi All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※下記の広告は本記事とは無関係です。














