史実としては、学者さんの説を色々調べても、これは分かりませんね。直江状についても真贋について、色々意見があるようです。
小説「関ケ原」では「連携があった」ことになっています。
それはそれとして、この「連携問題」はなにかと不可解なんですよね。
どうして三成は挙兵を急いだのでしょうか。
たとえば「連携なんかなかった」とします。そう主張する学者さんも多い。
それはそれでいいのですが、「なかったとしても、挙兵を遅らせた方が有利」でありましょう。
待っていれば、上杉と東軍の間には戦闘状態が発生します。あるいは東の伊達との間に挟まれて、上杉は滅亡するかも知れません。
でも戦いに入ってから、西軍が挙兵すれば、西軍は東軍を挟むことができます。「連携がない」のなら上杉の運命は気にする必要もありません。
「連携がない」としても、この作戦の方が有利でありましょう。「連携があった」としたら、伊達のことを上杉は「織り込み済み」ですから、さらに問題はなくなります。
待っていると西軍から大名が抜けていく、でしょうか。島津は抜けますが、宇喜多は残るし、小西も残ります。
毛利、吉川と小早川が抜けたとしても、それはそれで「スッキリ」するはずです。裏切られるよりは「まし」です。どうせ島津も毛利も関ケ原では一切動かないのですから。
それに「秀頼様警護」とすれば毛利輝元は大阪を動けないでしょう。
とにかく東軍が上杉と戦っている後ろから「突いた」ほうが有利なはずです。
つまり、東軍が上杉と戦端をひらくまで待つ。
ただ待っていると西軍の諸侯が抜けていくから、「三成挙兵のうわさ」は流しておく。流すことによって味方を大阪に引き留める。
同時に家康および東軍諸侯に「三成の挙兵はうわさに過ぎず、そのような意志のないこと」を三成は伝える。宇喜多もそのような動きがないことを伝える。
そうすれば、東軍は引き返す大義を失ってしまう。
戦端が開いたら、大老宇喜多秀家の名で「戦闘中止命令」を出す。「会津討伐は誤解であり、上杉に謀反の心がないことが分かった。即刻中止なさるべきこと」
しかし中止なんかしないでしょう。その時初めて、軍令違反ということで西軍を結成し、東軍をうつ。上杉はもう降伏しているかも知れませんが、東軍もかなり傷ついています。
そうすればかなりいい勝負に持ち込めたでしょう。
上杉があっけなく降伏してしまい、その段階で西軍(宇喜多、三成に味方する大名)がほとんど大坂城に残っていなければ、挙兵しなければいいだけのこと。
そもそも東軍は豊臣軍であり、その勝利は形式上は秀頼の勝利ですから、簡単には家康に実権は移りません。
それを早く挙兵なんかするもんだから、東軍は早々に引き返してしまいます。さらに上杉は伊達と戦闘に入って、東軍を追いません。
上杉にとっては三成挙兵は「天の助け」になっています。上杉は本能寺でも助けられましたが、三成挙兵でも、また窮地において助けられています。
連携があろうと、なかろうと、上杉と戦闘に入ってから挙兵すればいいものを。
どうも三成は戦機を知らない感じがします。島左近も名将の名は高いですが、それぐらいの「謀略」を献策できないようでは、たいした武将ではありません。
もっともかつてTBSドラマ「関ケ原」で徳川家康(森繁久彌)は最後にこう三成を評します。
「豊臣子飼いの大名の節操もない裏切りには背筋が冷たくなった。せめて三成一人がいて、泉下の太閤殿下も浮かばれるというものだ」
そうして家康は三成と太閤のために涙をながします。まああくまで「ドラマ」ですが、史実としても「あり得る」と思います。
徳川家康は若いころは律儀者で真面目な人間でした。年をとってからは狸親父、ワルというイメージが強いですが、当時としてはかなりの読書家で知識人です。
歴史主義者である家康の目から見れば、三成には勝利したものの、その行動には「讃えてもいい側面がある」と考えたはずです。
家康が尊敬する政治家は源頼朝で、その子供たちの悲惨な運命も知っていました。徳川存続のためには三成的な盲目的義心(忠義心とはちょっと違いますが)が必要と考えたはずです。
たとえ「建前としての義」であっても、「義」は必要だと思ったでしょう。その後徳川家全体が儒学を採用し、「忠」や「義」は徳目の中心となっていきます。
家康の涙は、まあ9割がた「なかった」でしょうが、1割ほどなら、三成と太閤の為に涙した可能性はあります。
小説「関ケ原」では「連携があった」ことになっています。
それはそれとして、この「連携問題」はなにかと不可解なんですよね。
どうして三成は挙兵を急いだのでしょうか。
たとえば「連携なんかなかった」とします。そう主張する学者さんも多い。
それはそれでいいのですが、「なかったとしても、挙兵を遅らせた方が有利」でありましょう。
待っていれば、上杉と東軍の間には戦闘状態が発生します。あるいは東の伊達との間に挟まれて、上杉は滅亡するかも知れません。
でも戦いに入ってから、西軍が挙兵すれば、西軍は東軍を挟むことができます。「連携がない」のなら上杉の運命は気にする必要もありません。
「連携がない」としても、この作戦の方が有利でありましょう。「連携があった」としたら、伊達のことを上杉は「織り込み済み」ですから、さらに問題はなくなります。
待っていると西軍から大名が抜けていく、でしょうか。島津は抜けますが、宇喜多は残るし、小西も残ります。
毛利、吉川と小早川が抜けたとしても、それはそれで「スッキリ」するはずです。裏切られるよりは「まし」です。どうせ島津も毛利も関ケ原では一切動かないのですから。
それに「秀頼様警護」とすれば毛利輝元は大阪を動けないでしょう。
とにかく東軍が上杉と戦っている後ろから「突いた」ほうが有利なはずです。
つまり、東軍が上杉と戦端をひらくまで待つ。
ただ待っていると西軍の諸侯が抜けていくから、「三成挙兵のうわさ」は流しておく。流すことによって味方を大阪に引き留める。
同時に家康および東軍諸侯に「三成の挙兵はうわさに過ぎず、そのような意志のないこと」を三成は伝える。宇喜多もそのような動きがないことを伝える。
そうすれば、東軍は引き返す大義を失ってしまう。
戦端が開いたら、大老宇喜多秀家の名で「戦闘中止命令」を出す。「会津討伐は誤解であり、上杉に謀反の心がないことが分かった。即刻中止なさるべきこと」
しかし中止なんかしないでしょう。その時初めて、軍令違反ということで西軍を結成し、東軍をうつ。上杉はもう降伏しているかも知れませんが、東軍もかなり傷ついています。
そうすればかなりいい勝負に持ち込めたでしょう。
上杉があっけなく降伏してしまい、その段階で西軍(宇喜多、三成に味方する大名)がほとんど大坂城に残っていなければ、挙兵しなければいいだけのこと。
そもそも東軍は豊臣軍であり、その勝利は形式上は秀頼の勝利ですから、簡単には家康に実権は移りません。
それを早く挙兵なんかするもんだから、東軍は早々に引き返してしまいます。さらに上杉は伊達と戦闘に入って、東軍を追いません。
上杉にとっては三成挙兵は「天の助け」になっています。上杉は本能寺でも助けられましたが、三成挙兵でも、また窮地において助けられています。
連携があろうと、なかろうと、上杉と戦闘に入ってから挙兵すればいいものを。
どうも三成は戦機を知らない感じがします。島左近も名将の名は高いですが、それぐらいの「謀略」を献策できないようでは、たいした武将ではありません。
もっともかつてTBSドラマ「関ケ原」で徳川家康(森繁久彌)は最後にこう三成を評します。
「豊臣子飼いの大名の節操もない裏切りには背筋が冷たくなった。せめて三成一人がいて、泉下の太閤殿下も浮かばれるというものだ」
そうして家康は三成と太閤のために涙をながします。まああくまで「ドラマ」ですが、史実としても「あり得る」と思います。
徳川家康は若いころは律儀者で真面目な人間でした。年をとってからは狸親父、ワルというイメージが強いですが、当時としてはかなりの読書家で知識人です。
歴史主義者である家康の目から見れば、三成には勝利したものの、その行動には「讃えてもいい側面がある」と考えたはずです。
家康が尊敬する政治家は源頼朝で、その子供たちの悲惨な運命も知っていました。徳川存続のためには三成的な盲目的義心(忠義心とはちょっと違いますが)が必要と考えたはずです。
たとえ「建前としての義」であっても、「義」は必要だと思ったでしょう。その後徳川家全体が儒学を採用し、「忠」や「義」は徳目の中心となっていきます。
家康の涙は、まあ9割がた「なかった」でしょうが、1割ほどなら、三成と太閤の為に涙した可能性はあります。











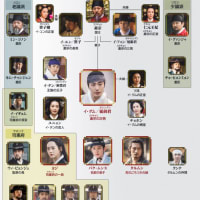




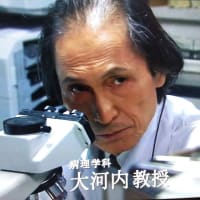



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます