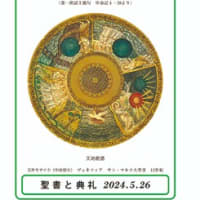こんばんは。岩瀬です。 神学講座は今日7月6日は、F・カー著『二十世紀のカトリック神学』の第7章「バーナード・ロナガン(1904-1984)に進みました。梅雨の大雨の中、しかもサッカー女子WC決勝戦の行われている時間帯そのものだったためか、参加者は20名弱でした。 ロナガンは、われわれカト研のメンバーにとっては、ジョンストン師を通してなじみのある神学者です。ジョンストン師は著書の中でも、講演の中でも、自分に影響を与えた神学者としてロナガン(とT・マートン、注1)に繰り返し言及し、引用している。思い起こされる方も多いのではないだろうか。
しかし一般的にはロナガンの名前はそれほど知られているとは思えない。公会議の文書作成に携わったわけでもなさそうだし、優秀な弟子を輩出したわけでもなさそうだ。では、一体ジョンストン師は彼のどこにひかれたのであろうか。また、著者F.カーは、なぜ、ロナガンを「カロル・ヴィイティワ(ヨハネ・パウロ二世)に並ぶ二十世紀最大の哲学者」としてピックアップしているのか。
まず、ジョンストン師側から見てみる。彼の著書『愛する』の原題は Being-in-love であることは皆さんご承知の通りです。Being-in-love は Loving(Love) とは異なること、を明らかにすることがこの本の主題でした。そしてこの言葉はロナガンの言葉なのです。『愛する』の訳者たちは、Being-in-love を 「恋する存在」と訳しており、F.カーの訳者たちは「愛のうちに存在する」と訳していて、適切な訳語の選択に苦労していることがわかる。また、ジョンストン師個人で見れば、ロナガンはイエズス会だし、その上アイリッシュ・カナダ人なので「英語」で考え、書いている(注2)。ジョンストン師は随分と身近に感じたようだ。しかも彼は名著『洞察』を書いた後、関心を霊性論に移してトマス主義神学研究から離れていくので、ジョンストン師の問題関心の変化と平行しているように思われる。
神学研究からみれば、ロナガンの『洞察』(Insight)(1957)は大きな思想的影響を与えたようだ。細井神父様は神学生時代にこの本を読まされたそうだ。まったくちんぷんかんぷんだったが、二つのことは覚えているという。ひとつは、神父様の言葉を借りると、「スコラ主義を180度ひっくり返した」哲学者(カーはロナガンを神学者というより哲学者と呼ぶべきと言っている)だと教わったという。バチカン第一公会議から二十世紀初頭まで支配していたトーマス理解(例えば、自然的秩序と超自然的秩序の機械的分離)を教会内部にとどまりながら批判し、正したという。第二は、長く続いた「恩恵論論争」(成聖の恩恵・助力の恩恵の区別をめぐるドミニコ会とイエズス会の間の論争)が実は不正確なトマス理解によるものであり、トマスの新しい解釈によれば意味の無い論争となるというロナガン説を教わったという。確かに第二バチカン公会議以降、われわれは成聖の恩恵とか助力の恩恵などという言葉を聴かなくなった。岩下壮一師の論文「成聖の神学」(1940)『信仰の遺産』(2015・岩波文庫)などを読むと、ロナガンはこういう議論を批判していたのだとわかる。)。
『洞察』で言えば、門脇佳吉師は、ジョンストン師の『愛する』への「解説」のなかで、異様と思われるほどきつい言葉でこの『愛する』を「批判」している。それはジョンストン師は「ロナガン哲学・神学を使っている」からだ、という。門脇師はローマでロナガンの講義を聴いているので、ロナガンがトマス主義者だということはよくわかっている。そのうえで、ロナガンは「トマス主義者」だから駄目だと言う(注3)。この辺は、カトリックと「禅」の関係をどう捉えるかについて、ジョンストン師・門脇師・そして井上洋治師は三者三様なのでそのまま真に受けるわけにはいかないが、私としては、何もここまで強く言わなくとも、と思う。ジョンストン師は、「禅」が持つ「力動性」、ダイナミズムを結局理解できなかった、それはネオトミズムの限界だという批判(例えば若松栄輔『霊性の哲学』)は当てはまるとは思うが、だからといってなにもそこまで言わなくともと、やはり思う。が、このテーマはまた別の機会に考えてみたい。
ロナガンは、前回取り上げたK・ラーナーと同じ年に生まれ、同じ年に亡くなっている。つまり同じ時代を生きたわけだが、「経験主義」の影響を強く受けている点では共通している。社会を「意味の世界・言語の世界」としてとらえていこうとする姿勢、共通の根源体験(referential point)を認めることで、宗教の多様性・多元性を認めようとする姿勢は、共通している。ヨハネ23世は、『洞察』を読んで、やはり公会議を開こう、と思い至ったという。この話が本当かどうかはわからないが、それほどロナガンのこの本はバチカン第二公会議を生み出す思想的背景として重要視されていたようだ。単に古いからと言ってトマス・アクイナス批判を繰り返すのではなく、トマスを読み直す、解釈し直すことによって、カトリック神学を豊かにしていくという姿勢はロナガンのレジェンドなのだろう。
第二バチカン公会議以前の神学校では、解釈学や歴史研究は御法度だったという。勝手な議論を繰り広げると収拾がつかなくなるからだという。第二公会議以降聖書研究の成果を取り入れるのは当然のこととなっている。著者カーは、「今や、聖書批評や教理史などをふくまない組織神学なるものはあり得ない」と断定している。普通に言えば、自然神学は組織神学の中に組み込まれるということだ。そういう意味では、ロナガンは第二バチカン公会議を思想的に準備した人と言えるかもしれない。カーは、それを「カトリック思想の刷新という広大なプロセス」と呼んでいる。事実ロナガン自身、「神学者たちはフランス革命まで支配的であった思想を...大転換させ、現代の後継者たちの思想・・・へと適合させていった」と述べている。
ジョンストン師からみれば、ロナガンの影響は『洞察』からのものもあっただろうけど、おもに引用されるのは『神学の方法』などロナガン後期のもの、または「霊性」論である。人間の「存在」が being-in-love になるのは、「回心」のときに無条件の愛に心を向けるときだという(『愛する』196頁)。(教会で、「改心」ではなく「回心」という言葉を使うのは、心が神の方を向くという意味を込めるため)。こういう存在論や霊性論はどうも門脇師の好みではないようだが、この第17章「愛する」はジョンストン師へのロナガンの影響がはっきり読み取れる秀作で、私の好みの論文というか、黙想のもとになっている。
(注1)トーマス・マートン師は神秘主義研究者で、特に禅とキリスト教の関係についての文献は今でも読まれるらしい。鈴木大拙、井筒俊彦、若松栄輔などによる言及がある。ジョンストン師は「感電という不慮の事故のためタイのバンコクで亡くなった」と書いているが(108頁)、交通事故死という説もあるし、また、その過激な主張のため「赤狩り」の犠牲になったという説もあるようだ。
(注2)20世紀前半のカトリック神学では前世紀のJ・ニューマンなきあと英語を使った神学者は少ないようだ。ここ10年グローバリズムのなかで英語はもはや外国語ではなく、世界語になってしまい、まるでエスペラントにとってかわったようだが、ジョンストン師の時代に英語で神学を論じることはマイナーな試みだったようだ。英語を母語として受け入れざるを得なかったジョンストン師がロナガンの言語論にひかれたのは当然かもしれない。ジョンストン師はボストンでロナガンに会ったとき、「あなたが言っているのは神秘主義のことだ」と言ったら「そうだ、そうだ」を返事されたと誇らしげに自伝のなかで語っている。
(注3)門脇師はここでははおもに「存在」概念についてのトマス主義的理解を批判している。しながら、実は日本人は「理性」で「存在」を見ないから、トマス主義からは禅に近づけないと言っているようだ。ジョンストン師は自分はあくまで「トマス主義」だと言っていたから、禅に「近づく」ことはあっても、結局は門脇師や井上師のように禅や仏教に「のめり込む」ことが無かったのだと思う。といっても、元気に活躍されている門脇師に敬意を表することにやぶさかでは無い。
しかし一般的にはロナガンの名前はそれほど知られているとは思えない。公会議の文書作成に携わったわけでもなさそうだし、優秀な弟子を輩出したわけでもなさそうだ。では、一体ジョンストン師は彼のどこにひかれたのであろうか。また、著者F.カーは、なぜ、ロナガンを「カロル・ヴィイティワ(ヨハネ・パウロ二世)に並ぶ二十世紀最大の哲学者」としてピックアップしているのか。
まず、ジョンストン師側から見てみる。彼の著書『愛する』の原題は Being-in-love であることは皆さんご承知の通りです。Being-in-love は Loving(Love) とは異なること、を明らかにすることがこの本の主題でした。そしてこの言葉はロナガンの言葉なのです。『愛する』の訳者たちは、Being-in-love を 「恋する存在」と訳しており、F.カーの訳者たちは「愛のうちに存在する」と訳していて、適切な訳語の選択に苦労していることがわかる。また、ジョンストン師個人で見れば、ロナガンはイエズス会だし、その上アイリッシュ・カナダ人なので「英語」で考え、書いている(注2)。ジョンストン師は随分と身近に感じたようだ。しかも彼は名著『洞察』を書いた後、関心を霊性論に移してトマス主義神学研究から離れていくので、ジョンストン師の問題関心の変化と平行しているように思われる。
神学研究からみれば、ロナガンの『洞察』(Insight)(1957)は大きな思想的影響を与えたようだ。細井神父様は神学生時代にこの本を読まされたそうだ。まったくちんぷんかんぷんだったが、二つのことは覚えているという。ひとつは、神父様の言葉を借りると、「スコラ主義を180度ひっくり返した」哲学者(カーはロナガンを神学者というより哲学者と呼ぶべきと言っている)だと教わったという。バチカン第一公会議から二十世紀初頭まで支配していたトーマス理解(例えば、自然的秩序と超自然的秩序の機械的分離)を教会内部にとどまりながら批判し、正したという。第二は、長く続いた「恩恵論論争」(成聖の恩恵・助力の恩恵の区別をめぐるドミニコ会とイエズス会の間の論争)が実は不正確なトマス理解によるものであり、トマスの新しい解釈によれば意味の無い論争となるというロナガン説を教わったという。確かに第二バチカン公会議以降、われわれは成聖の恩恵とか助力の恩恵などという言葉を聴かなくなった。岩下壮一師の論文「成聖の神学」(1940)『信仰の遺産』(2015・岩波文庫)などを読むと、ロナガンはこういう議論を批判していたのだとわかる。)。
『洞察』で言えば、門脇佳吉師は、ジョンストン師の『愛する』への「解説」のなかで、異様と思われるほどきつい言葉でこの『愛する』を「批判」している。それはジョンストン師は「ロナガン哲学・神学を使っている」からだ、という。門脇師はローマでロナガンの講義を聴いているので、ロナガンがトマス主義者だということはよくわかっている。そのうえで、ロナガンは「トマス主義者」だから駄目だと言う(注3)。この辺は、カトリックと「禅」の関係をどう捉えるかについて、ジョンストン師・門脇師・そして井上洋治師は三者三様なのでそのまま真に受けるわけにはいかないが、私としては、何もここまで強く言わなくとも、と思う。ジョンストン師は、「禅」が持つ「力動性」、ダイナミズムを結局理解できなかった、それはネオトミズムの限界だという批判(例えば若松栄輔『霊性の哲学』)は当てはまるとは思うが、だからといってなにもそこまで言わなくともと、やはり思う。が、このテーマはまた別の機会に考えてみたい。
ロナガンは、前回取り上げたK・ラーナーと同じ年に生まれ、同じ年に亡くなっている。つまり同じ時代を生きたわけだが、「経験主義」の影響を強く受けている点では共通している。社会を「意味の世界・言語の世界」としてとらえていこうとする姿勢、共通の根源体験(referential point)を認めることで、宗教の多様性・多元性を認めようとする姿勢は、共通している。ヨハネ23世は、『洞察』を読んで、やはり公会議を開こう、と思い至ったという。この話が本当かどうかはわからないが、それほどロナガンのこの本はバチカン第二公会議を生み出す思想的背景として重要視されていたようだ。単に古いからと言ってトマス・アクイナス批判を繰り返すのではなく、トマスを読み直す、解釈し直すことによって、カトリック神学を豊かにしていくという姿勢はロナガンのレジェンドなのだろう。
第二バチカン公会議以前の神学校では、解釈学や歴史研究は御法度だったという。勝手な議論を繰り広げると収拾がつかなくなるからだという。第二公会議以降聖書研究の成果を取り入れるのは当然のこととなっている。著者カーは、「今や、聖書批評や教理史などをふくまない組織神学なるものはあり得ない」と断定している。普通に言えば、自然神学は組織神学の中に組み込まれるということだ。そういう意味では、ロナガンは第二バチカン公会議を思想的に準備した人と言えるかもしれない。カーは、それを「カトリック思想の刷新という広大なプロセス」と呼んでいる。事実ロナガン自身、「神学者たちはフランス革命まで支配的であった思想を...大転換させ、現代の後継者たちの思想・・・へと適合させていった」と述べている。
ジョンストン師からみれば、ロナガンの影響は『洞察』からのものもあっただろうけど、おもに引用されるのは『神学の方法』などロナガン後期のもの、または「霊性」論である。人間の「存在」が being-in-love になるのは、「回心」のときに無条件の愛に心を向けるときだという(『愛する』196頁)。(教会で、「改心」ではなく「回心」という言葉を使うのは、心が神の方を向くという意味を込めるため)。こういう存在論や霊性論はどうも門脇師の好みではないようだが、この第17章「愛する」はジョンストン師へのロナガンの影響がはっきり読み取れる秀作で、私の好みの論文というか、黙想のもとになっている。
(注1)トーマス・マートン師は神秘主義研究者で、特に禅とキリスト教の関係についての文献は今でも読まれるらしい。鈴木大拙、井筒俊彦、若松栄輔などによる言及がある。ジョンストン師は「感電という不慮の事故のためタイのバンコクで亡くなった」と書いているが(108頁)、交通事故死という説もあるし、また、その過激な主張のため「赤狩り」の犠牲になったという説もあるようだ。
(注2)20世紀前半のカトリック神学では前世紀のJ・ニューマンなきあと英語を使った神学者は少ないようだ。ここ10年グローバリズムのなかで英語はもはや外国語ではなく、世界語になってしまい、まるでエスペラントにとってかわったようだが、ジョンストン師の時代に英語で神学を論じることはマイナーな試みだったようだ。英語を母語として受け入れざるを得なかったジョンストン師がロナガンの言語論にひかれたのは当然かもしれない。ジョンストン師はボストンでロナガンに会ったとき、「あなたが言っているのは神秘主義のことだ」と言ったら「そうだ、そうだ」を返事されたと誇らしげに自伝のなかで語っている。
(注3)門脇師はここでははおもに「存在」概念についてのトマス主義的理解を批判している。しながら、実は日本人は「理性」で「存在」を見ないから、トマス主義からは禅に近づけないと言っているようだ。ジョンストン師は自分はあくまで「トマス主義」だと言っていたから、禅に「近づく」ことはあっても、結局は門脇師や井上師のように禅や仏教に「のめり込む」ことが無かったのだと思う。といっても、元気に活躍されている門脇師に敬意を表することにやぶさかでは無い。