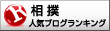ノコギリカメムシ。
焦げ茶色で、腹の縁はノコギリ状。
ヒラタカメムシ類に似ていますが、体は重厚。
(ヒラタカメムシ類は体が平べったい。)
リアルKONASUKEの部屋(笑)のベランダにて撮影。
時々こうやって、虫の方から遊びに来てくれます(笑)
ところで、2021年、筑波大学の博士課程の方の論文で、本種と糸状菌の共生についての論文が出されたようです。
PDFファイルでは、その肝心の部分は、近日 . . . 本文を読む
ブチヒメヘリカメムシ。
「ブチヒゲヘリカメムシ」となっているサイトもありますが。
「斑髭」の意味が分かりません。
昔、どこかで誤記があったせいだとか。
まぁ、「ヒメヘリカメムシ科」、だからね(笑)
この個体は♀のようです。
ネット上の交尾している画像を観ると、♂は腹の周囲の「ヘリ」の黒色部が発達し白黒まだら、♀は黒色部の発達が弱くクリーム色が強くなるようです。
①上翅は透明
②腹部末端中央は細 . . . 本文を読む
アカスジカスミカメ。
かつては生息数の少ない稀な種であったが、1980年代以降に斑点米被害の発生が報告され、2000年代以降は主要害虫とされています。
同様の被害をもたらすアカヒゲホソミドリカスミカメは研究が進み、防除方法も比較的確立しているようです。
一方で本種は、年間を通しての飼育方法が確立していなかったこともあり、研究が遅れているようです。
(コムギによる飼育方法が後に発表されています。) . . . 本文を読む
ハワードワラジカイガラムシの♀。
居たのは、ガマズミの葉かなぁ?
オオワラジカイガラムシと同様、♂はアブラムシ似の有翅の昆虫。
分類:
カメムシ目ヨコバイ亜目カイガラムシ上科ワタフキカイガラムシ科
体長:
7~10mm
分布:
本州、九州
垂直分布?
成虫の見られる時期:
5~6月(年1化)
卵で冬越し
エサ:
クワ、サクラ、バラ、ヤマブキ、サンゴジュ、ミカン、チャ、ツバキ、ブドウ、アケビ、コブ . . . 本文を読む
オオアメンボ。
中脚は6㎝もある国内最大のアメンボ。
比較対象物がないのでアレですけど(笑)
ビオトープ天神の里にて撮影。
RDB:
絶滅危惧Ⅰ類:東京都
絶滅危惧Ⅱ類:三重県
準絶滅危惧種:埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、愛知県、宮崎県
分類:
カメムシ目カメムシ亜目アメンボ下目アメンボ上科アメンボ科
体長:
♂19~26mm
♀21~26mm
分布:
本州、四国、九州
丘陵~山地
成虫の見 . . . 本文を読む
オオワタコナカイガラムシの卵嚢。
長さ約2㎝。
我が家のドウダンツツジ?に産み付けられていました。
♀成虫は、オオワラジカイガラムシが粉を吹いたような姿。
白粉に濃淡があるため、斑に見えるそうです。
オオワラジカイガラムシでは、♂は有翅で、♀とは全く形態が異なります。
ネット上では、本種の♂の姿を確認できませんでしたが、どうなんでしょうね?
分類:
カメムシ目ヨコバイ亜目カイガラムシ上科コナ . . . 本文を読む
今年初めて、ツツクツクボウシが鳴くのを確認しました。
いよいよ夏も終盤ですね。
過去の記録を復習ってみると・・・
ツクツクボウシ初鳴き
2013年 記録なし
2014年 8/7
2015年 7/31
2016年 8/6
2017年 8/5
2018年 8/1
2019年 8/7
2020年 8/10
2021年 8/1
2022年 8/6
ミンミンゼミが7月下旬なのに対して、ツクツクボウシは . . . 本文を読む
8/4、今年初めてミンミンゼミが鳴いているのを確認しました。
これまでの記録をさらってみると・・・
2013年 記録なし
2014年 7/31
2015年 7/23
2016年 7/29
2017年 7/25
2018年 7/25
2019年 8/8
2020年 8/3
2021年 7/31
2022年 8/4
アブラゼミと同時か少しあと、7月下旬~8月初旬に初鳴き、という傾向のようです。
も . . . 本文を読む
7/21、今年初めてアブラゼミを確認しました。
初鳴きの確認は、7/27。
アブラゼミは、羽化して1週間ほど成熟してから鳴き始めると言われますので、教科書通りですね。
アブラゼミの初鳴きの記録
2013年 記録なし
2014/07/29 初鳴き?
2015/07/23 数日前?に初鳴き
2016/07/27 初鳴き
2017/07/20 抜け殻を確認
2018/07/22 初鳴き(07/13 . . . 本文を読む
7/8、今季初めて、ヒグラシが鳴くのを聞きました。
明け方に一瞬でした。
その後、聞かれないところをみると、気の早い個体が鳴いてしまっただけなのかも。
これまでの記録を見てみると・・・
2013/07/08
2014/07/10
2015 記録なし
2016/07/06
2017/07/14
2018/07/08
2019/07/24
2020/07/11
2021/06/30
2022/07/ . . . 本文を読む
昨日(220619)、短時間ですがニイニイゼミの初鳴きを確認しました。
例年より10日ほど早く、昨年よりは5日遅い。
これまでの初鳴きの記録をさらってみると・・・
2014年・・・7/1
2015年・・・メモなし
2016年・・・6/30
2017年・・・7/3
2018年・・・6/25
2019年・・・7/1(先に姿を確認)
2020年・・・6/29
2021年・・・6/14
まぁ、昨年は全 . . . 本文を読む
トゲキジラミ幼虫?
類似種がいるらしく、「?」付きです。
シロダモと思われる葉の裏、葉脈に沿って、小さい昆虫がびっしり。
腹部には長い毛のようなもの。
お尻から甘露?を出している個体もいます。
こうして見ると、アブラムシに近いのかな、って思うね。
何故か成虫は見つかりませんでした。
ロウ物質も見当たりません。
何故なのでしょう?
あるいはロウ物質は、出して間もなくは透明に近く、空気に触れて . . . 本文を読む
コミズムシ。
画像が不鮮明です。
やはり、水中のモノを撮るには、偏光フィルターが必須なようですね。
それか一旦、捕獲して、シャーレとかに入れて観察するとかですね。
いずれにしても、リベンジするぞ!
ミズムシって言っても、カビの一種じゃありません(笑)。
水の中にいるワラジムシっぽいヤツでもありません。
カメムシの仲間です。
別名、フウセンムシ。
ただし、識別困難な類似種がいるとのことで。
間違 . . . 本文を読む
コブヒゲカスミカメ。
赤褐色なので、♀、ですね。
♂は全体に黒褐色。
発生時期が短いそうで、まだ見たことがありません。
頭部~小楯板の正中線上に白線があります。
幼虫①。
4/15撮影。
幼虫も♂♀で色が違うのだろうか?
近くで見つけた幼虫②。
①より少し翅が短い。
4/12撮影。
ウスモンミドリカスミカメかも知れません。
ただ、近くで成虫を目撃したことがないこと、食草がキク科植物、ナス . . . 本文を読む
ダイコンアブラムシ。
本来、黄緑色だそうですが、白いロウ物質に覆われるため、このような色になるとのこと。
うわぁぁぁぁぁぁぁ。
こんなにビッシリ
( ̄▽ ̄;)
コロニーが大変大きいのが本種の特徴のようです。
アブラナ科につくアブラムシには、主にダイコンアブラムシ、ニセダイコンアブラムシ、モモアカアブラムシがいますが。
モモアカアブラムシは淡緑色や赤褐色で、明らかに色が違います。
ニセダイコンア . . . 本文を読む