
クロテンフユシャクのオス。
今季フユシャク類9種目。

さて、冒頭の個体を、仮にクロテン①として。
クロテンフユシャクの特徴は、
・前翅に明確な濃い黒点があること
・外横線が翅頂近くで「く」の字に曲がること
でしょう。
この特徴がハッキリしない個体は、ウスバフユシャクと紛らわしい。
これまで、それらしき画像は撮れていたんだけど、イマイチ明確じゃなくて、載せるのを避けてきたんです。
この個体は明確なので、ようやくアップ(笑)

ところで、この「クロテン②(1/17)」を観て欲しい。

これも黒点は明確だし、外横線が翅頂付近で「く」の字を描いている。
典型的なクロテンフユシャクだと思う。

そしてこれが「クロテン③(1/17)」。

黒点は明確だが、外横線は、一見、緩やかな曲線に見える。
ところが・・・
実は「クロテン②」と「クロテン③」は、同一個体を別角度から撮影したもの。

ここで翻って、冒頭の「クロテン①」を観て欲しい。
翅はほぼ水平になっており、撮影角度はほぼ垂直だと思われる。
「クロテン②」も、屋根型に畳んだ翅を横から撮影したものであり、角度はより垂直に近いと思われる。
要するに、クロテンフユシャクと思われる個体、あるいはウスバフユシャクと紛らわしい個体を撮影する場合、翅に対して垂直な角度から撮影した方が、より確実に外横線の角度を把握出来るのではないだろうか?
今後の課題として、撮影角度を、翅に対して垂直にしたものと、あえて鋭角にしたものを撮り、比べてみようと思う。
もう個体数はピークを過ぎてるっぽいけどね。

分類:チョウ目シャクガ科フユシャク亜科
大きさ:オス前翅の長さ12.5~19mm、翅を広げた長さ25~31mm
メス体長9~11mm
分布:北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:11月中旬~3月初旬(地域・標高によって出現時期は異なります)
卵・蛹で冬越し
※寒冷地では、厳冬期は活動できないため、初冬と晩冬に分かれて活動します。初冬型は繁殖後、卵で越冬します。晩冬型は、厳冬期を蛹で過ごし、晩冬に羽化・繁殖・産卵します。両者は時間的に隔離されて互いに遺伝子を交換できないため、「時間的」種分化の途上にあると考えられます。
エサ:成虫・・・食べない
幼虫・・・オニグルミ、アカシデ、クマシデ、ブナ、クリ、コナラ、クヌギ、ミズナラ、アラカシ、ケヤキ、ヤマモミジ、ヤマツツジなど15種ほどが知られる
その他:大きさ、斑紋、色彩は変異に富み、他種と紛らわしい。
ウスバフユシャクよりやや遅れて発生する。
オスは前翅の黒点が濃く明確。
外横線は翅頂付近で「く」の字に曲がる。
(ウスバフユシャクでは緩やかな曲線)
外横線の外側と内横線の内側は白色で縁どられない。
オスは灯りに来る。
メスは無翅。
日没とともに動き出し、コーリング(臭い物質フェロモンでオスを呼ぶ)する。
孵化した1齢幼虫は、糸を空中に飛ばして分散する(バルーニング)。
終齢幼虫の体長は20~23mm
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
みんなで作る日本産蛾類図鑑V2
ウスバフユシャクとクロテンフユシャク
こんちゅう探偵団
京都大学
むしコラ
北茨城周辺の生き物
今季フユシャク類9種目。

さて、冒頭の個体を、仮にクロテン①として。
クロテンフユシャクの特徴は、
・前翅に明確な濃い黒点があること
・外横線が翅頂近くで「く」の字に曲がること
でしょう。
この特徴がハッキリしない個体は、ウスバフユシャクと紛らわしい。
これまで、それらしき画像は撮れていたんだけど、イマイチ明確じゃなくて、載せるのを避けてきたんです。
この個体は明確なので、ようやくアップ(笑)

ところで、この「クロテン②(1/17)」を観て欲しい。

これも黒点は明確だし、外横線が翅頂付近で「く」の字を描いている。
典型的なクロテンフユシャクだと思う。

そしてこれが「クロテン③(1/17)」。

黒点は明確だが、外横線は、一見、緩やかな曲線に見える。
ところが・・・
実は「クロテン②」と「クロテン③」は、同一個体を別角度から撮影したもの。

ここで翻って、冒頭の「クロテン①」を観て欲しい。
翅はほぼ水平になっており、撮影角度はほぼ垂直だと思われる。
「クロテン②」も、屋根型に畳んだ翅を横から撮影したものであり、角度はより垂直に近いと思われる。
要するに、クロテンフユシャクと思われる個体、あるいはウスバフユシャクと紛らわしい個体を撮影する場合、翅に対して垂直な角度から撮影した方が、より確実に外横線の角度を把握出来るのではないだろうか?
今後の課題として、撮影角度を、翅に対して垂直にしたものと、あえて鋭角にしたものを撮り、比べてみようと思う。
もう個体数はピークを過ぎてるっぽいけどね。

分類:チョウ目シャクガ科フユシャク亜科
大きさ:オス前翅の長さ12.5~19mm、翅を広げた長さ25~31mm
メス体長9~11mm
分布:北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:11月中旬~3月初旬(地域・標高によって出現時期は異なります)
卵・蛹で冬越し
※寒冷地では、厳冬期は活動できないため、初冬と晩冬に分かれて活動します。初冬型は繁殖後、卵で越冬します。晩冬型は、厳冬期を蛹で過ごし、晩冬に羽化・繁殖・産卵します。両者は時間的に隔離されて互いに遺伝子を交換できないため、「時間的」種分化の途上にあると考えられます。
エサ:成虫・・・食べない
幼虫・・・オニグルミ、アカシデ、クマシデ、ブナ、クリ、コナラ、クヌギ、ミズナラ、アラカシ、ケヤキ、ヤマモミジ、ヤマツツジなど15種ほどが知られる
その他:大きさ、斑紋、色彩は変異に富み、他種と紛らわしい。
ウスバフユシャクよりやや遅れて発生する。
オスは前翅の黒点が濃く明確。
外横線は翅頂付近で「く」の字に曲がる。
(ウスバフユシャクでは緩やかな曲線)
外横線の外側と内横線の内側は白色で縁どられない。
オスは灯りに来る。
メスは無翅。
日没とともに動き出し、コーリング(臭い物質フェロモンでオスを呼ぶ)する。
孵化した1齢幼虫は、糸を空中に飛ばして分散する(バルーニング)。
終齢幼虫の体長は20~23mm
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
みんなで作る日本産蛾類図鑑V2
ウスバフユシャクとクロテンフユシャク
こんちゅう探偵団
京都大学
むしコラ
北茨城周辺の生き物










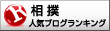

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます