田無スマイル大学としての最初の活動は、2012年に実施した「地域イノベーター養成講座」です(ふるいHPが残っていました)。
これは、第一期(3・4月)と第二期(6・7月)の2回実施しました。
別途詳細にご説明しますが、田無スマイル大学は、2010年11月にスタートした「田無ソーシャルメディア研究会(通称ソメ研)」の活動の一つとして始まったものです。
ソメ研は、昼間は、サラリーマンなどをしている人たちが地元で面白いことをやるにあたって、当時急速に広がり始めたツイッターやブログなどの「ソーシャルメディア」を活用することで、実際には、なかなか集まれなくても、思い立った人が「この指止まれ」とし、賛同する人が一緒に活動するというゆるい集まりでした。
当時、地域の居場所として「仙人の家」(*1)がまもなくオープンするというので、何か必要があればそこを拠点に集まらせてもらうという感じでした。
「ソメ研」は、いろいろな活動をしましたが、そのなかで、私がたまたまH大学大学院の「地域イノベーション論」という講座を1コマ受け持っており、その講座のために勉強したことや集めた材料がもったいないので、これを地元でも活用してみたいと現在副代表をしている鈴木剛さんに相談したことから始まります。
私は、それまでサラリーマン(ウーマン)として都心や北海道で仕事をしておりましたので、生まれも育ちも西東京市(田無)ですが、地域活動をしたことがありませんでした。
地元のことも分からないし、ネットワークもない。「地域イノベーター養成講座」をやるとしても、自分でイノベーターを起こしたこともない。とても不安でしたし、無謀な試みでしたが、これが予想外に「成功」したのです。
鈴木剛さんと相談するなかで、私が大学院で講義している内容ではなく、もっと、実践的な講座にしたいということになりました。上記のように、私は「実践」をしたことがなかったので、少々ビビりました。
巷では、当時、著名人によるベンチャー講座のようなものがあちこちで出来ていましたし、西東京といういわば田舎で、人が来るのだろうか、私に教えられるものだろうか・・と不安一杯でした。
鈴木さんは、対象を16~40歳くらいに絞ろうと言い出しました。本当に地域で活躍してもらいたいのは、この年代だからです。もちろん、実際には、その前後の人も受け付けるけど、チラシには、対象を明確にしようということにしたのです。そのため、毎日曜日の午前中を講座とし、時間に余裕のある方には、交流会として食事をしながら、12時~13時までいられるようにしました。

公民館などですと、毎月会議室を抽選で取らなければならないので、毎週日曜日午前中というような連続講座は、公民館主催でもないとやれません。また、その後、飲食を伴う交流会も、仙人の家だからできたことです。
チラシを作成し、ソメ研のお仲間に教えて頂いて、公民館などに配布したかと思いますが、この辺り、もうすでに定かではありません(^o^)
受講生の募集は、基本的にネットや鈴木さんのFB等のネットワークに依存しました。
3月4日の第一回目は、どうなることかと思いましたが、ソメ研のお仲間も半分くらい、応募してきてくれた受講生が半分くらで約20名でスタートしました。第一回目は、私の講義みたいなのと、自己紹介だったと思います。
この講座では、それほどビッグではないが、我々の先輩にあたり、既に実績のある方に8回のうち2回くらい来て頂きました(薄謝で)。その方々がやっておられることや想いに加え、現在抱えている問題点や課題を出して頂き、受講生(含むソメ研メンバー)がその問題点や課題を自分たちなりに解決する方法を考えるというのを数チームに分かれて議論し、発表しました。
これまで、先輩として大きく見えていた方々も、いろいろな課題を抱えておられるのに自信を深めたのか、皆でイキイキと解決策を考えて、発表しました(それを寛大な心で聴いて下さったゲストに感謝です)。
これをきっかけに、次からは、数人ずつ、自分が「あったらいいな」というテーマについて、発表し、全員で、そのテーマや発表者のアイデアについて、ダメ出しをするというやり方が定着してきました。
これを私たちは「まな板の鯉」方式と呼んでいます。この方法は、私が北海道で働いていた折、当時北大で経営学部の教授をされていた金井一頼先生(現在大阪商業大学)が地元の勉強会でとり入れられていたのを真似したものです。
参加者が次々と自分もやりたいことがあるので、是非、まな板の鯉になりたいと言い出し、皆に批判された人は、次までに再度案を練り直してまた発表するというようなことが続きました。
その後の交流会でも、話が弾み、毎日曜日の朝早くから、ほとんど欠席無しで、皆良く続いたものだと思います。私は、何かを教える「先生」ではなく、司会というか、ファシリテータのような立ち位置でした。
第二期にも、新しい方が数名入ってこられました。また、第二期には、第一期の受講生のプランを少しでも、具体化しようと、それぞれに合わせて、たとえば、ネットでこういうことを考えているけれども、どう思うかなどについてアンケートを取ったり、顔で体調を判断するというアイデアについて、そのようなご本を出されている先生にコンタクトを取るなどをしました。
それぞれの受講生がそれぞれ、いろいろなことを感じ、中には、その後事業化まで進めた方もおられるし、これまでの仕事に自信を持ち、さらに強化したかたもおられます。
また、受講生の故郷を活性化させたいという思いに応えて、夏には、遊びも兼ねて、千葉県久留里に希望者だけで一泊旅行もしました。 受講生のお父さんの年代で地元におられる方々が既に、独自にいろいろなことをやっておられることを知り、むしろ勉強になりました。
(*1)仙人の家は、西東京の東伏見稲荷そばにあるコミュニティカフェです。高齢の竹中夫妻が、自宅を改修し、バリアフリーのスペースを作られ、そこを地域に開いています。HPはこちらです。










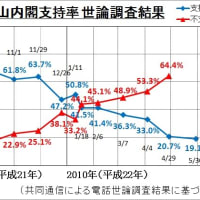
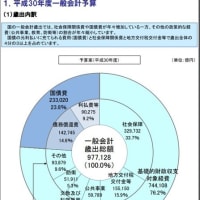
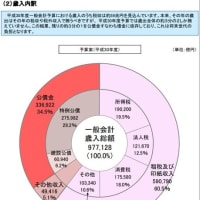
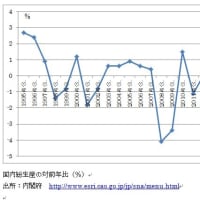
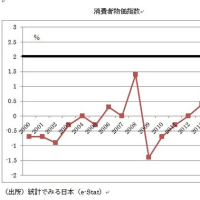



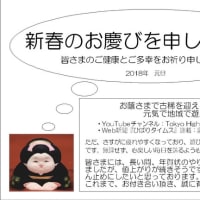


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます