その頃、「フューチャーセッション」が流行り始めていました。最初に書きましたように、「未来から考える」というのを当時明言している人は、余りいなかったと思っていたので、なんだかお株を取られたような気分がしました。
小平の「マイスタイル」さんがこの地域で初めてフューチャーセッションという名前のついた会合を開くというので、その対抗心もあって、「未来はスマ大でしょう!」という気持ちになり、スマ大も「フューチャーセッション」を独自に始めました。
フューチャーセッションというのは、あるテーマに対し、そのステークホルダーが一堂のもとに会して、その方向性や解決策を打ち出すものです。
日本では、富士ゼロックスが企業で導入し、成功したと言われています(*1)。企業の場合には、これまでは、取引先や顧客には、全ての情報を見せずに、自社にとって有利にことを運ぼうとするのが普通でしたが、そうではなく、取引先や顧客も含めて皆で最も良いものや関係を作り出していこうというものです。企業だととても分かりやすいです。取引先にただ値切るといった無理難題を押し付けるのではなく、一緒に考えてより良いものをより安く作れる方法を考えていく、顧客にもたいした機能ではないものを高く買わせるのではなく、顧客が本当は何を望んでいるのかを知って、より適したものを作り出していくというような感じです。
ですから、本当は、フューチャーセッションは、「あったらいいな」を形にする、具体的な動きに結びつかなければいけないのです。これを地域に応用するなら、行政であれば、どのような市庁舎を作ろうかを住民と共に考えて案をまとめるというようなものになります。あるいは、どのような学童保育をしたらよいかを父兄や学童保育を請け負ったNPOなどが一緒に考えていくというようなことになります。子どもを預けているお母さんたちが、どうしても、夜帰りが遅い場合でも、少なくとも〇時までは、預かっていて欲しいといった具体的な改善策を提案するのに適しています。
残念ながら、私たちのフューチャーセッションは、ただ話し合いで終わってしまいました。タイトルを「フューチャー・セッション@西東京-10年後、わたしたちがもっとワクワクするまちについて、話してみよう!」としました。
第一回が「未来を担う子ども」、第二回が「防災(避難所運営ゲーム:HUG体験)」、第三回が「眠れる地域の人財活用」、第四回が「公共空間のデザイン」でした。毎回、老若男女40名くらいが集まり、多くは、ゲストのお話を聞いた後、ワールドカフェをするというような形で進めました。皆さん、いろいろなご意見を出され、頭が刺激されて毎回良い集まりだったと思って下さったようです。しかし、本当は、そこから何かの行動DOに結びついて欲しかったのですが、アイデアを出す方がおられても、結局は、その場で終了してしまいました。
(*1)富士ゼロックスでフューチャーセッションを担っておられた野村恭彦さんが現在、幅広くフューチャー・セッションを取り仕切られています。










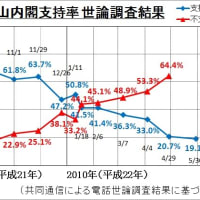
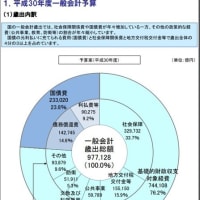
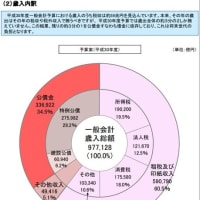
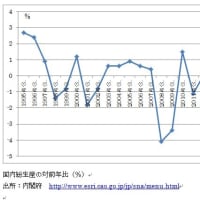
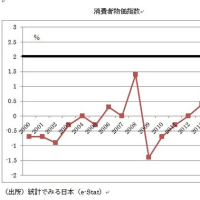



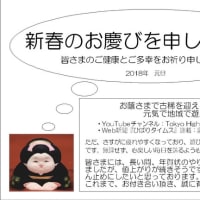


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます