前ブログで書いたフューチャーセッションの第二回(2013年2月)に防災というテーマを取り上げました。防災といっても、とても幅広いのですが、たまたま「避難所運営ゲーム」を知っている方がおられ、これをやってみようということになりました。
この時期は、2011年の3.11からもう2年経過した時期ですが、ようやく、自分たちのこととして防災に取り組まなければと考え始めた頃なのではないかと思います。
避難所運営ゲームは、その頭文字をとってHUGと呼ばれています。これは、阪神淡路大震災の折に、静岡県が開発したもので、ゲームにつかうカードややり方は、静岡県から買うのですが、その頃には、全国からの注文が殺到しており、2ケ月待ちくらいの状況でした。静岡県が貸し出しもしていて、まずは、貸し出しを受けて練習をしました。また、既に、中原小学校の父母たちが、2ケ月待てないので、独自にカードを作って実施されていたので、その方たちにやり方などもうかがいました。
静岡県が作成したHUGは、当日だけでなく、しばらくたってからの出来事などが入り混じっており、混乱の度合いが強く、ゲームに時間もかかるし、相当草臥れます。
そこで、スマ大のスタッフの一人が被災して7時間に起きることに限ったゲームに作り変えてくれました。また、使える教室の数を半分くらいにしたり、参加者の立ち位置を明確にしました。これだと、1時間くらいでゲームを終了することができます。
ゲームは、被災してきた人々を避難場所になっている学校の体育館や教室に割り振るという簡単なものですが、被災された人の体調が悪かったり、高齢だったり、さまざまなペットを連れて来たり、雨が降っていたり、トイレの水が必要だったり、インフルエンザのが人が出てきたりなど、いろいろな問題が生じるというものです。
5人くらいでゲームを進めるなかで、これが実際のことだったらどんなに大変か、避難所に行ったらお客様でいられるような気でいたが、自分たちがやれることをやらなければならないのだということが分かってきます。
また、日ごろから、自宅ではどんなことを考えておかなければいけないか、いざ避難所を開設するにしても、日ごろからその運営方法などについて心構えをしておかなければならないなぁ、などと考えるようになります。
スマ大は、「市民力を高める」というのを一つのテーマにしていますが、HUGは、「自分たちのまちを良くするのは(安全にするのは)自分たちだ」ということに気付かせるという意味では、とても有効なゲームだと思います。
私自身は、これをやると頭が痛くなるし、身寄りもないので、死んだら死んだときみたいな気持ちであるため、最初、余り好きではありませんでした。
しかし、ゆめこらぼ(西東京市市民協働推進センター)の広報を兼ねて、HUGの実施をお手伝いし、西東京市で20回くらい実施しました。そういう意味では、被災と防災を自分ごととして考える機会を得た市民がたくさんいるまちになったわけで、良かったと思っています。ただ、実際には、このゲームを体験し、それぞれの避難所地域ごとに、避難計画などを立ててシュミレーションまでやらないと血になり肉にはならないと思います。西東京市では、現在、小中学校ごとに、避難所運営協議会を立ち上げて、マニュアルづくりなどをしているはずですので、それが具現化されることを期待したいと思います。










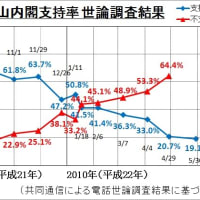
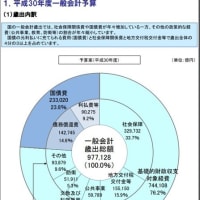
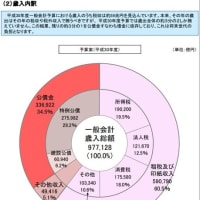
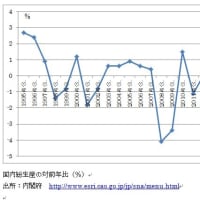
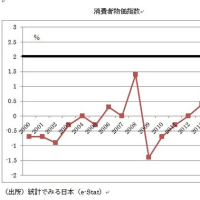



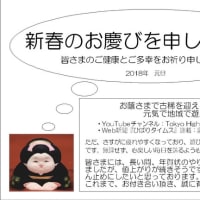


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます