7月6日(月)
「西東京市を第二の故郷と思ってもらうために、私たちに出来ること」ワークショップでの発言内容(要点のみ)を整理してみました。
- もともと福島は、コミュニティがあったが、それが震災でバラバラになってしまった。それを西東京という地元で再編成しようというのは、良い。西東京は、都市部より田舎なので、地域ネットワークが作りやすいのではないか。
- 大船渡では、コミュニティハウスが出来ている。支援に行った我々も含め、一緒にごはんを食べる。→一緒にご飯を食べると言うのは、仲よくなるのに良い。
- 「みちのくまほろば」に出てくる人は良いが、閉じこもって酒ばかり飲んでいる人もいる。男性が表に出てこないのは、避難している人だけでなく、住民全体の問題。我々も、オトパ(お父さんお帰りなさいパーティ)を2年連続でやったが、やはり、男性は、なかなか出て来ない。
- 男の人は、お酒が飲めないと出て来ないのでは。健康麻雀なんかが良いのでは。農業をやっていた人が多いのだが、こちらでは、仕事がない。市民農園を紹介する、あるいは農家の援農をしてはどうか。
- 農福連携で若尾さんがやっているのに参加してもらってはどうか。今年度は、矢ヶ崎農園でやっている。社協と「まほろば」は、関係があるので、一緒に農業をやってはどうか。→しかし、新倉さんによると、田舎の農業(作る作物が限られ、農閑期がある)と都会の農業(365日生産し、多様な作物を作る)は、全く違うというから、難しいかもしれない。
- 培ってきたキャリアを活かせるのが良い。ボランティアというより、仕事がしたい。お金が得られると良い。シルバー人材センターとは、つながっているのだろうか。農業は、本職だったので、ボランティアではなく、俺にまかせろ、俺がリーダーという活躍できる場でないとダメ。
- 陸前高田では、病院長が仮設住宅の10ケ所で畑を作り、仕事をやれる場所を作っている。これでみんな元気がでている。東京に売りに来たりすると、もともと引っ込み思案だった人がやれるようになった。
- 男の人に、出てきてもらうのには、自分が役立っている、貢献していると感じないとダメ。役割と出番づくりが重要。ポジション。大船渡では、子どもに竹とんぼを教える人を育てることをやって、10人できた。こういうのが良いのでは。
- 西東京市は、新地町と公民館同士が連携をしている。「公民館祭り」であがった収益の一部で、旭製菓さんにも協力いただいて、かりん糖バイキングをしたりしている。一昨年、昨年とほそぼそながらつながっている。向こうの公民館では、「障害者フェスタ」というのをやっており、そこに出かけている。公民館の活動団体や楽団、かっぽれなど。
- リトル福島を造ればよいと思う。リアルな故郷へは帰れないが、文化まで無くすことはない。
- 浪江町には、窯業があったが、土が違うと作れない。踊りや祭りは、各地で細々やっているが、やはり借り物だ。味噌を作る会も良いが、都会では、それを置いておく場所がない。浜通りは、昔、製鉄が盛んだったが(タタラ:県の教育委員会によると)。
- 双葉町の駅前にある大幸ラーメンがソウルフードで、皆なつかしがる。これを田無駅前に作ってはどうか。
- 浪江町の「浪江焼きそば」は、太い麺で、フルーツ味(桃など)で、B級グルメで優勝した。これをやっていた人が仙台の方で麺を作っている。町田でもやっている。これを、田無公民館で料理教室をやって、もともと西東京の人も、来て、福島の人が教えたら良いのではないか。それを皆で食べることで仲良しになる。可能なら、全部の公民館でやって、さらに、空家を借りて、居場所にもしたらよいのではないか。参考:http://item.rakuten.co.jp/namiefutomen/ganbarou-namie3-3/
- 第二のふるさとプロジェクト。田無スマイル大学で得意分野について講師をしてもらったらよいのでは。
- 味噌をつくれる人がいるそうなので、味噌づくり講座を開いて、3ヶ月後とかに、出来上がった味噌を持ち寄って味比べの集まりをするとか(味噌を育てる×食す)
- 福島の日本酒を飲む会など食にまつわることをすると良いのでは。










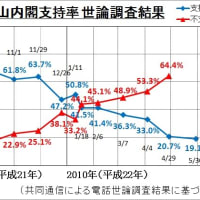
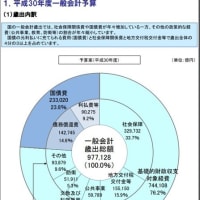
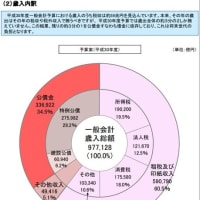
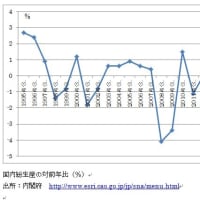
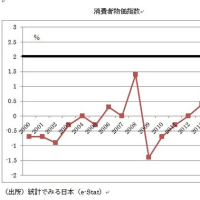



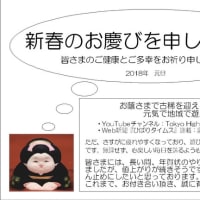


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます