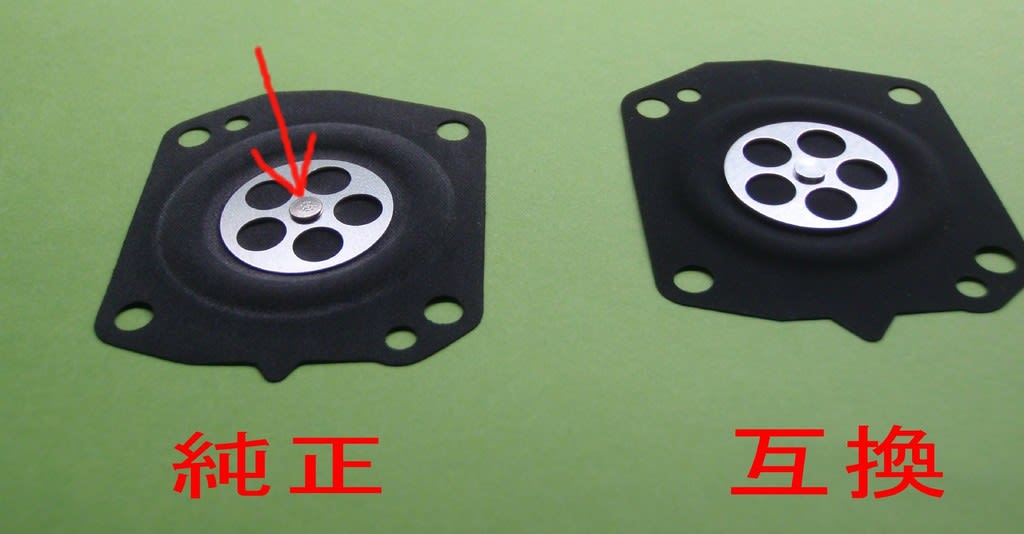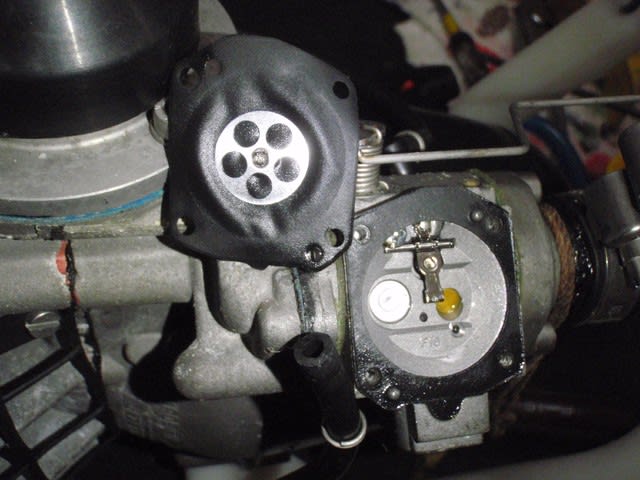当ブログの現状
閲覧有難うございます。10年前に開設し、2018年12月に第76回を以て終了したこのBlogだが、ある程度は皆様の参考にして戴けるものと考へ、閉じずにそのまま保存してきました。
しかしその後更に6年が経過し、流石に陳腐化しただろうし、自身の引退と共に抹消=退会すべきかと、昨今気にしていた次第です。 しかし、この間に機種の更新も無く、また改めてBlog閲覧状況をみると、未だに結構な訪問者数となっている。更に、大ベテランの仲間が、参考になるからと維持継続を勧める。実際、この間に、メーカーの名称は変わったり、小さな技術的変更はあったものの、実質的に同じ品が供給されている。
と言う訳で、まだ当分はこのまま残して置くことにしました。
Blogの情報が、どの程度皆様の参考になっているかは不明ですが、関西で気を吐いているK氏などの例を見ても、ここで提唱した内容が取入れられている事もあり、意義はあると信じます。
実際、私はこの6年間にも、ほぼ月例で離島へ遠征し、常にアクアスクーターを使用してきました。その間故障は繰り返し体験したものの、その内容は記載例に沿ったものばかりだった。
特筆すべきは、この間水没は全く無かったということか。これは偏に空中排気方式を採用したからと考えています。
今後も、電池式の性能向上と、価格の低下が達成されるまでは、アクアスクーターは使われると思います。ただし将来、排気ガス規制が課される様な場合は、新品の販売だけは規制される可能性があるでしょう。
残念ながら、傘寿の老化には勝てず、昨12月の遠征を最後に、私は魚突きを引退し、本機の使用も終了としました。
本Blogは様子を見ながら、数年?はこのまま保存(放置?)しますから、役立てて下されば幸いです。
閲覧有難うございます。10年前に開設し、2018年12月に第76回を以て終了したこのBlogだが、ある程度は皆様の参考にして戴けるものと考へ、閉じずにそのまま保存してきました。
しかしその後更に6年が経過し、流石に陳腐化しただろうし、自身の引退と共に抹消=退会すべきかと、昨今気にしていた次第です。 しかし、この間に機種の更新も無く、また改めてBlog閲覧状況をみると、未だに結構な訪問者数となっている。更に、大ベテランの仲間が、参考になるからと維持継続を勧める。実際、この間に、メーカーの名称は変わったり、小さな技術的変更はあったものの、実質的に同じ品が供給されている。
と言う訳で、まだ当分はこのまま残して置くことにしました。
Blogの情報が、どの程度皆様の参考になっているかは不明ですが、関西で気を吐いているK氏などの例を見ても、ここで提唱した内容が取入れられている事もあり、意義はあると信じます。
実際、私はこの6年間にも、ほぼ月例で離島へ遠征し、常にアクアスクーターを使用してきました。その間故障は繰り返し体験したものの、その内容は記載例に沿ったものばかりだった。
特筆すべきは、この間水没は全く無かったということか。これは偏に空中排気方式を採用したからと考えています。
今後も、電池式の性能向上と、価格の低下が達成されるまでは、アクアスクーターは使われると思います。ただし将来、排気ガス規制が課される様な場合は、新品の販売だけは規制される可能性があるでしょう。
残念ながら、傘寿の老化には勝てず、昨12月の遠征を最後に、私は魚突きを引退し、本機の使用も終了としました。
本Blogは様子を見ながら、数年?はこのまま保存(放置?)しますから、役立てて下されば幸いです。