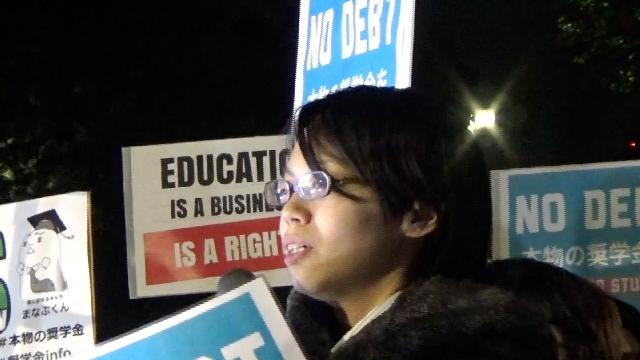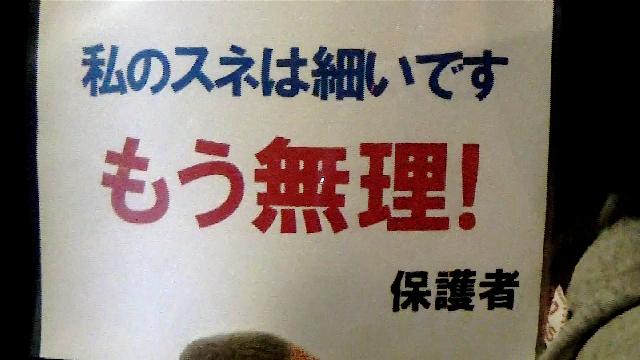官房長官「教育勅語 教材としての使用 否定されない」 | NHKニュース
文科相 教育勅語「歴史教材に用いるのは問題ない」 | NHKニュース




4・3報道ステーション
動画⇒http://www.dailymotion.com/video/x5h7m9w
(2017年4月3日)の『報道ステーション』は『教育勅語』が再び日本の教育に登場する危惧を伝えた。
:
:
教育勅語をめぐり先週、政府がある方針を示した。
●2017年3月31日閣議決定
『我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行う事は不適切であると考えているが、憲法や教育基本法に反しないような形で
教材として用いることでまでは否定されることでは無い』
〝教材としての使用を否定しない〟とはどういうことなのか。
●4月3日衆議院 松野博一文部科学大臣
「要は教え方がどうかということがポイントだということです。
中学校の社会科の教科書や高等学校の歴史公民の教科書において歴史的事実を学ぶための参考資料として掲載されている。」
:
つまり、教育勅語を歴史の理解を深める観点から社会科の教材として使う分には問題ないと松野文部科学大臣は説明した。
一方、菅官房長官は…。
●菅官房長官
「教育直後には親を大切にするとか兄弟姉妹が仲良くするとか友達はお互いに信じ合うなどといった項目もあることも事実である」
●記者質問
「政府として教育勅語を道徳を学ぶ意味で使っても問題ない?」
●菅官房長官
「教育勅語の中にはそうした(徳目)があります〝そこは否定することは出来ない〟と思っています」
教育勅語には道徳の観点からも学ぶべき点があるという菅長官。
しかし、教育勅語は戦後まもなく〝衆議院で排除の決議〟〝参議院では失効の決議〟がされている
国家の非常時には〝天皇のために命を捧げよ〟という精神は国民主権の理念とは相いれないという理由からです。
:
●記者質問
「(教育勅語は)天皇を中心とした国家観で貫かれているという指摘もある。
今回の閣議決定は教育勅語を使うことへの〝お墨付き〟を与えるのではとの批判もある。」
●菅官房長官
「戦後の諸改革の中でそれを教育の唯一の根本として取り扱うことなどは禁止されて、その後の教育基本法の制定によって
政治的、法的効力を失ったという経緯がある。適切な配慮のもとに教材として用いること自体に問題はない。
:
●記者質問
「〝戦中は悪くなかったんだ〟と(戦前戦中の国家体制を)肯定されたい方もいっぱいいる。
教育勅語を否定したのは戦後の決議であって、そこを曖昧にすることが、この問題の本質ではないのか?」
●菅官房長官
「曖昧にしてないじゃないですか」
●記者質問
「どういう配慮をすれば教育勅語を教材として使えるのか?」
●菅官房長官
「親を大切に 兄弟姉妹仲良くする友達をお互い信じ合うそういうことまで否定するべきではないんじゃないか。」(以上VTR)
●スタジオ富川アナ
「これは教育勅語ではなくても学べる道徳ですよね。」
●後藤兼次解説
「今回の閣議決定。答弁書という形をとっているが戦後、国権の最高機関である国会が失効、もしくは排除という非常に重い決議をしたのが
一部であれ〝教育勅語そのものが教育の現場にもう1回登場してくる可能性が出てきたということ。
この国権の最高機関の決議に対してたった一度の閣議で決めていいものかどうかそこが根本の問題になると思う。
しかも、この閣議の場で〝異論が出なかった〟といわれていますし、その後、自民党内でもこの議論が出てきていないと…。
そういう〝一つの方向〟にぐっと流れていく傾向がより危険だと感じる。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
過激派は本とペンを恐れます。〝教育の力〟が彼らを恐れさせます。
(中略)
無学、貧困、そしてテロリズムと闘いましょう。
本を手に取り、ペンを握りましょう。
それが私たちにとって最も強力な武器なのです。
一人の子ども、一人の教師、一冊の本、そして一本のペン、それで世界を変えられます。
〝教育こそが〟ただ一つの解決策です』
2013年、当時16歳のマララ・ユスフザイさんの言葉だ。
タリバンの銃撃に合いながらも一命をとりとめ、国連において全世界に発信した彼女が最も必要だとする〝教育〟と
日本政府が閣議決定で容認した〝教育〟とは別物である。
:
:
教育こそ国の基本だ。誤った教育は過去の日本がそうであったように国民を誤った道へと導く。
その反省の上にたった戦後72年の歩みではないのか?
今回の閣議決定では〝異論は出なかった〟という…。