暑いのでジョアンジルベルトのCDばかり聞いている。
「もう飽きた」と妻が勝手にAmazonのサイトで検索を始める。
「いや彼の声が好きなんだよ」
「ポルトガル語ならいいんでしょ」
と勝手に欧州のポルトガルの人気歌手の音源になってしまう。
けれども何か違う。
あまり英語の歌に惹かれなくなったのは
楽曲の良さや雰囲気以上に
否応なしに舞台設定を明示される窮屈さからだと考えている。
本当に英語教育って必要なのだろうかね。
絵とか音楽とか格闘技とかもっと一所懸命やればいいのに。
だから全く意味が取れないポルトガル語の響きが気に入っている。
燦燦たる陽光の中で遊ぶ若い男女を木陰から眺める
オタクな男の視点。たしかイパネマの娘の歌詞も
そんなシチュエーションだったような。
「ブラジルでは演歌みたいな扱いらしいよ、ボサノバは」
「だろうね」
そこが中年男には心地よいのよ。
タンゴのような生と死の対比の鮮やかさではなく
ヘンテコなテンションコードとシンコペーションの連続の中に
ぼそぼそとしたジョアンの声がいい。
暑い日は好きだけど水着はもういいやという気分にちょうどいい。
少しだけ飲んで。
きちんとアレンジされたアントニオカルロスジョビンの
ピアノやストリングスの入ったアレンジも最近は楽しめる。
けれど何も考えたくない時には、ライブのギターだけの弾き語りがいい。
モントルージャズフェスティバルのライブアルバムを教えてくれたのは
明大前のバーでよく会ったサラリーマンのハタノさんという人だった。
穏やかないい人だった。ギタリストになりたくて
大村憲司の付け人みたいなことをしていたとのことだった。
スタンゲッツに「この下手くそな白人に馬鹿と言ってくれ」と
ポルトガル語で毒づき「あなたのサックスは素晴らしいと彼は言っています」
と訳されたころの、わが道を行く偏屈なカリオカが
自分のギターと声だけで高級リゾートの観衆を巻き込んでいく臨場感。
フェリシダージの後半、観衆がフレーズを囁く声が会場にこだまする。
初めて聞いた時は鳥肌が立った。
それさえも暑苦しい時は2004年東京のライブ盤。
「コンバンワ」で始まる。
日本の観衆は聞き入るから邪魔がない。
良いものに対する敬意を素直に持ち、
調和に至ろうとする試みや姿勢は、大切なこと。
受容は必要な事だが言葉を発しない分、理解されにくい。
言葉と意味で区画し、世界を塗りつぶし、
それに追従せざるもの、死すべきもの。
侵略者であったポルトガル人の言葉でブラジル人が歌うと
なぜ気持ちいいのだろうか。
◎・◎・ ◎・◎・
表拍が体に合っているのだという人が居る。
私のような田舎の祭り好きに否応なく染み込んでいて
一所懸命塗りつぶそうとしても、消そうとしても
にじみ出てきてしまうリズムの好みと郷愁。
ボサノバは完全な表拍というには
複雑だけれど、それでも
ポップスやロックの裏拍とは明らかに異なる。
ビートルズに関する映画で「バックビート」
というのがあった。結局見なかったけれど
あの時代の熱狂はまさしくアフリカ起源の
バックビートと白人の言葉の世界が生み出したもの。
・◎・◎ ・◎・◎
バックビートは力だったし、力のない若者が力を
得ようと思ったからバックビートが世の中を席巻したのだろう。
そして、その形が今の大衆音楽のメインになっている。
窮屈なんだよな。
だから偏屈なブラジルのお爺さんが好きだ。
俺はオンビートなんだってね。
でもこの週末、初めて娘にピアノを教えてもらって不思議に思ったのは
イマジンという曲は、ピアノは明らかに表にアクセントがあるのに
途中でドラムやベースが入ると、裏拍のポップスに聞こえること。
娘は「これは簡単な曲だね」と言う。
確かに教わって右手と左手を別々に練習すると、
さほど難しい曲ではないことがわかる。
ジョンがポールより明らかにピアノが下手であることもわかる。
けれど弾くだけでとても静かな気持ちになる。
キースリチャーズがこんなことを言っていたそうだ。
「たまにイマジンをピアノで鳴らすことがあるんだ。ロマンチックな曲さ。
現実的でないともいえるな。でもレノンを思い出して少ししんみりする」
ジョンは表裏の無い人だったんだなきっと。
だからベスト盤のイマジンの次に入っている曲、ジェラスガイも素晴らしい。











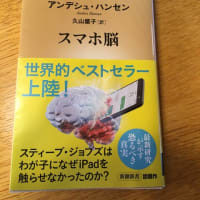



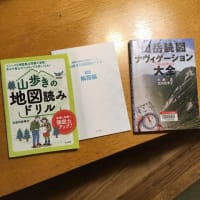




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます