○芽室町議会基本条例
第2章 議会及び議員の活動原則と政治倫理(第3条―第7条)
第4章 町長等と議会との関係(第11条―第15条)
第9章 最高規範性及び見直し手続き(第29条・第30条)
地方議会は、二元代表制のもとで、行政機関の監視、調査、政策形成及び提案機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める
地方自治の本旨の実現を目指しています。
芽室町議会(以下「議会」といいます。)は、町民によって選ばれた議員(以下「議員」といいます。)で構成し、本町の最高規範である芽室町自治基本条例(平成19年芽室町条例第3号)による議会の役割と責務に基づき、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「町長等」といいます。)と緊張関係を保持しながら、町の最高意思決定機関であることを認識し、
町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展のために活動します。
また、議会は合議制の議事機関であり、町民への積極的な情報の公開、共有と説明責任の遂行により、
町民の意思を的確に把握し、自由かっ達な討議を通じて、最も有益な結論に導いていく責務があります。
議員は、研鑽を積み、町民参加を基本としてまちづくりを推進する責務があります。
よって、議会の公正性・透明性を確保するとともに、「
分かりやすい議会、開かれた議会、行動する議会」を目指し、町民の信託に全力で応えていくことを決意し、この条例を制定します。
第1条 この条例は、議会が果たすべき自主的かつ自律的な運営を実現するための基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするとともに、町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に寄与することを目的とします。
第2条 議会は、町民の代表としての負託と信頼に応え、大局的な視点から意思決定し、真の地方自治の実現に取り組みます。
2 議会は、町政運営に関する監視、調査、政策形成及び提言機能を併せ持つ機関としての責任を果たします。
3 議会は、予算及び決算をはじめとする町政に係る様々な事項に対し、議事機関としての責任を果たします。
4 議会は、広く町民の意思を把握し、町政に的確に反映させることを目的に、議員個々の資質を高め、議会機能の強化並びに活性化に取り組み、議会力及び議員力を強化します。
第3条 議会は、全ての会議を原則公開するとともに、民主的かつ効率的な議会運営のもとに、次の活動を行います。
(1) 議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行うこと。
(2) 町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されているかを監視し、けん制すること。
(3) 議員相互間の自由かっ達な討議を通して意見を集約し運営すること。
(4) 議決責任を深く認識するとともに、重要な事項についての議案等を議決したときは、町民に対して説明すること。
第4条 芽室町議会委員会条例(昭和62年芽室町条例第2号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」といいます。)は、次の活動を行います。
(1) 審査及び調査に当たっては、資料等を公開し、町民に分かりやすい議論を行うこと。
(2) 町民に対し審査の経過及び所管する行政課題等に対処することを目的に、意見交換会等を開催すること。
(3) 委員長は、副委員長と協議のうえ、委員会の秩序保持に努め、効率的な議事の整理を行い、委員会の事務をつかさどること。
(4) 委員長は、討議による合意形成に努め、委員長報告を作成し、報告に当たっては、論点、争点等を明確にすること。
第5条 議長及び議員は、次に掲げる原則に基づき、次の活動を行います。
(1) 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行うこと。
(2) 議員は、議員相互間の討議を重んじて活動すること。
(3) 議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、自らの能力を高める不断の研鑽により、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(4) 議員は、議会の構成員として公正かつ誠実に職務を遂行し、町民全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指して活動すること。
第6条 議会は、議員の政策形成及び立案能力等の向上を図るため、別に定める芽室町議会議員研修要綱(平成24年3月30日制定)に基づき、議員研修を実施します。
2 議会は、議員研修の充実、強化に当たり、
広く各分野の専門家、町民各層等から情報を得て議員研修計画を策定し、研修会及び研究会などを積極的に開催します。
第7条 議会は、芽室町議会議員政治倫理条例(平成24年芽室町条例第33号)に基づき、議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者及び特別公務員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使しません。
第8条 議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任を十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保します。
2 議会は、本会議及び委員会並びに全員協議会(以下「議会の諸会議」といいます。)の日程及び内容は、事前に町民に周知するとともに、審議過程及び結果についても情報を公開し、共有します。
3 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、
参考人制度や公聴会制度を十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を議会の意思決定に反映します。
4
議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置付け、審査においては、提案者の意見を聴く機会を確保します。
5 議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を聴取する機会を確保し、議会、議員による政策提案を行います。
第9条 議会は、町政に係る論点、争点の情報を、議会独自の視点から町民に対して周知します。
2 議会は、情報通信技術(ICТ)の発展を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの町民が行政に関心を持つように議会広報活動を行います。
第10条 議会は、町民に対し、議会及び議員の活動内容を公表し、情報を共有することにより、議会活動の活性化を図ります。
2 議会は、議会の基礎的な資料・情報、議会の評価等を1年ごとに調製し、議会白書として町民に公表します。
3 議会は、議会の活性化に終えんがないことを常に認識し、議会としての評価を1年ごとに適正に行い、評価の結果を町民に公表します。
4 議会白書及び議会としての評価に関して必要な事項は、議長が別に定めます。
第11条 町長等と議会は、それぞれの機関の特性を活かすとともに、政策をめぐる論点、争点を明確にし、緊張関係を維持しながら行政を運営します。
2 議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行います。
3 議員は、一般質問等に当たっては、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、討議による政策論争を展開します。
4 議員は、一般質問の通告に基づき町長等から提出された答弁書をもとに、討議の充実を図ります。
5 議員は、二元代表民主制の充実と町民自治の観点から、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員に就任しません。
6 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長及び執行機関の長並びに職員(以下「町長等執行機関の長等」といいます。)は、議員の質疑及び質問に対して、議長及び委員長の許可を得て、論点、争点を明確にするため反問することができます。
7 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長等執行機関の長等は、議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対して、議長又は委員長の許可を得て、反論することができます。
第12条 議会は、町長等が提案する重要な政策等の意思決定においては、その水準を高めるため、次に掲げる政策形成過程を論点として審議します。
(4) 総合計画の実行計画及び個別計画における根拠又は位置付け
(7) 総合計画上の実行計画及び将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、政策等の適否を判断する観点から、立案、決定、執行における論点、争点を明確にし、執行後を想定した審議を行います。
第13条 議会は、決算審査において、町長等が執行した政策等(計画、政策、施策、事務事業等)の評価(以下「議会の評価」といいます。)を行います。
2 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を町長等に明確に示します。
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告
第15条 議員は、通年議会制度を活用し、休会中においても主体的・機動的な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができます。
2 議会は、文書質問の通告文及び町長等の回答文を、議会だより、議会ホームページ等により町民に公表します。
3 文書質問について必要な事項は、
芽室町議会会議条例(平成24年芽室町条例第32号。以下「会議条例」といいます。)で定めます。
第16条 議会は、議員による討議の場であり、議員相互の討議を中心に運営します。
2 前項の規定に基づき、本会議及び議会の諸会議への町長等に対する出席要請は、必要最小限に留めるものとし、議員間で活発な討議を行います。
3 議会は、委員会における委員外議員が発言できる機会を保障します。
4 議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び請願並びに陳情等を審議し結論を出す場合には、議員相互の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たします。
5 議員は、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、
議員相互の討議により議論を尽くして合意形成を行います。
第17条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題等について、議会としての共通認識を深めるとともに、政策形成能力の向上を図るため、議員政策討論会を開催します。
2 議員政策討論会について必要な事項は、議長が別に定めます。
第18条 議会は、議会費について、一定の標準率などを用いて適正な議会活動費の確立を目指します。
2 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算を確保します。
3 議会は、議長交際費を含めて、議会費の使途等を議会だより及び議会ホームページ等により町民に公表します。
第19条 議会は、議長、副議長の選出に当たり、議会活動の方向性を明確にし、議会の透明性をより一層高め、議会の責務を強く認識するため、それぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設けます。
第20条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、学識経験を有する者等で構成する附属機関を設置します。
2 附属機関に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
第21条 議会は、町政の課題に関する調査のために必要があると認めるときは、
法第100条の規定により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置します。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えます。
3 調査機関に関し必要な事項は、
会議条例で定めます。
2 議会は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図ります。なお、当分の間は、執行機関の法務及び財務機能の活用、職員の併任等を考慮します。
3 議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ町長と協議します。
第23条 議会は、
法第100条第18項の規定により、議会図書室を適正に管理し運営するとともに、その機能を強化します。
2 議会図書室は、議員のみならず、町民、町長等においても利用することができます。
第24条 議会は、町民の信頼を高めるため、不断の改革及び活性化に努めます。
2 議会は、前項の改革に取り組むため、議会活性化計画を策定し、実行と評価について全議員で協議します。
3 議会は、他の自治体議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査、研究等を行います。
4 議会は、議会制度に係る
法改正等があったとき、又は議会改革の推進の観点から必要があると認めるときは、速やかに調査、研究等を行います。
5 議会は、議会モニター及び議会サポーターを設置し、提言その他の意見を聴取するとともに、議会運営に反映します。
第25条 議会は、前条の目的を達成し使命を果たすため、会期を通年とします。
2 会期を通年とするために必要な事項は、
会議条例で定めます。
第26条 議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行います。
2 議会は、
芽室町議会傍聴条例(平成24年芽室町条例第34号)に定める町民等の傍聴に関して、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行います。
3 議会は、会議を定刻に開催し、会議を休憩する場合には、その理由、再開の時刻を傍聴者に説明します。
第27条 法第91条第1項の規定に基づき、芽室町議会の議員の定数は、16人とします。
2 議員定数の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考人制度及び公聴会制度を十分活用します。
3 議員定数の改正については、
法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案するものとします。
第28条 議員の報酬及び費用弁償並びに期末手当(以下「報酬等」といいます。)は、別に条例で定めます。
2 前項に規定する条例においては、適正な報酬等の確立を期すため、報酬の標準率又は報酬額を示します。
3 報酬等の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用します。
4 報酬等の改正については、
法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案するものとします。
第29条 この条例は、議会の最高規範であり、この条例に違反する条例、規則、規程等を制定しません。
3 議会は、議会に関する憲法、法律、その他法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に定める理念、原則に照らして判断します。
第30条 議会は、1年ごとに、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、公表します。
2 議会は、前項による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、全ての議員の合意形成に努めたうえで、この条例の改正を含めて適切な措置を講じます。
3 議会は、この条例を改正する際には、いかなる場合でも改正の理由、背景を町民に説明します。
1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。
2 芽室町議会の議員の定数を定める条例(平成14年芽室町条例第48号)は廃止します。
3 議会事務局設置条例(昭和33年芽室町条例第8号)は廃止します。
4 芽室町議会の議決すべき事件を定める条例(平成23年芽室町条例第3号)は廃止します。
(芽室町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止)
5 芽室町定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成23年芽室町条例第14号)は廃止します。











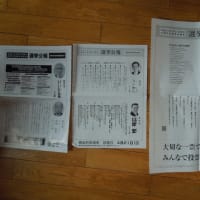

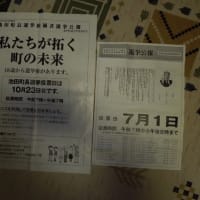

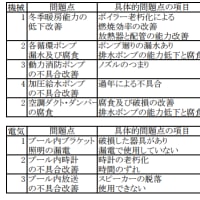
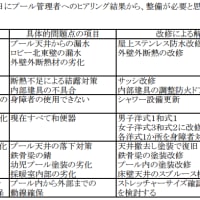
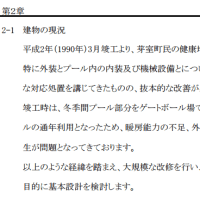


行政機関の監視、調査、政策形成及び提案機能を十分発揮しながら、・・・
そして緊張関係が肝要とのこと。
町民もまちづくりに参加。さまざまな声や要望を反映させる、と。町民はイエスマンではない行政との間で異論もあるはず。
それを、じゃまくさい、と排除しないで納得させる説明が必要ですね。
議会基本条例は勉強になりました。